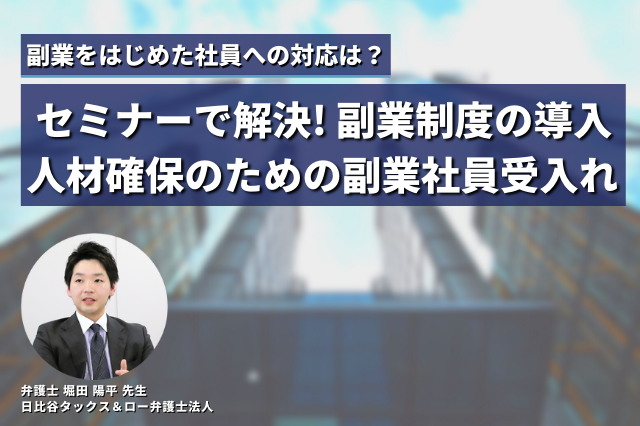
日比谷タックス&ロー弁護士法人に所属する堀田 陽平先生を講師に迎え、特別ウェビナー(Webセミナー)“【副業をはじめた社員への対応は?】 セミナーで解決!副業制度の導入と人材確保の副業社員の受け入れ”を開催しました。
 2017年頃から企業の副業解禁が進み始め、さらに近年、コロナ禍での環境変化によって1つの企業のみに依存する生活への危機意識の高まりによって、副業希望者が増加していく傾向があります。勘違いしている企業がまだまだ多いのですが、原則、副業を禁止できません。
2017年頃から企業の副業解禁が進み始め、さらに近年、コロナ禍での環境変化によって1つの企業のみに依存する生活への危機意識の高まりによって、副業希望者が増加していく傾向があります。勘違いしている企業がまだまだ多いのですが、原則、副業を禁止できません。
本セミナーでは、「副業をはじめた社員への対応が分からない」、「会社はどのような副業制度を整備をすればよいのか」、また、「優秀な副業社員を受け入れるためにどうしたらよいのか」など、知っておきたいポイントや注意点を解説しました。本記事では、ウェビナーの中でご紹介した企業の副業対応について一部抜粋してご紹介します。
堀田陽平(ほった・ようへい)弁護士
石川県出身。2020年9月まで、経産省産業人材政策室で、兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。現在は「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行う。
【情報発信等】
日経COMEMOキーオピニオンリーダとして働き方に関する知見を発信。
著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)
政府も推進する副業・兼業促進政策
働き方改革実行計画以後 、柔軟な働き方のひとつとして、テレワークと並び“副業・兼業”が推進されています。
政府で行われてきた具体的な推進施策は、原則禁止だと言われていたものを原則OKに是正した“①モデル就業規則改定”をはじめ、“②副業・兼業ガイドライン策定”“③副業・兼業ガイドライン改定”。
2021年6月に出された2021年度成長戦略実行計画においても、引き続き“副業・兼業”を推進していく旨が明記されています。

出典: 経営ノウハウの泉
副業には優秀人材の獲得、新たな知見等の獲得など企業へのメリットも!
「社員の副業が本業にどう影響するか気になる……」という経営者の声は多いと思います。しかし、コスト感覚が身につくなど、社内で得られない経験により成長できるといった“人材育成”の一面や、副業人材を受け入れることにより他社の優秀な人材のノウハウを共有してもらえる“優秀な人材の獲得”、収入アップや自由な働き方を求める“人材の流出防止”、“新たな知識・顧客・経営資源の獲得”に繋がるなど、企業としてのメリットも多いです。
実際のデータから見ても、副業者は本業へのモチベーションや効率が低下したという人はほぼおらず、懸念事項として最も大きい点である“本業への支障”は気にしなくても良いと堀田先生は述べています。

出典: 経営ノウハウの泉
副業は原則として禁止・制限できない
「ウチは副業を認めてない」と禁止する企業も多いですが、法律的には原則として企業は社員の副業を禁止・制限はできません。労働者は就業時間以外の時間については自由に利用することが可能+職業選択の自由があるため、原則として副業は自由に行うことができます。
例外的に副業を禁止、または制限することができるのは、以下の場合に限られます。
①労務提供上の支障がある場合
②業務上の秘密が漏洩する場合
③競業により自社の利益が害される場合
④自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
したがって、企業側は副業を禁止し続けると、不許可行為が“許可義務違反”として不法行為責任を問われる可能性があります。
副業の労働時間の考え方と留意点
では、副業人材を受入れたい場合はどうすればよいのでしょうか?

出典: 経営ノウハウの泉
副業人材の活用パターンは、大きく以下の2つの契約形態があります。
・本業先で雇用されていて、なおかつ副業先でも雇用されているパターン(雇用×雇用)
・本業先で雇用されていて、副業先では業務委託とするパターン(雇用×非雇用)
いずれをとるかによって、法律の適用は異なり、留意する必要のあるガイドラインも異なります。雇用×雇用の場合は、労働関係法令(『改定副業・兼業ガイドライン』)、雇用×非雇用の場合は、競争法(『フリーランスガイドライン』)が適用されます。今回は、労働時間などが問題になりがちな前者のケースを解説します。
雇用副業の場合:労働時間の計算や割増賃金の支払はどうなる?
副業では何時間まで働いてもらうことができるのでしょうか? 厚労省の解釈通達によれば、事業主を異にする場合、つまり本業先と副業先の労働時間は通算するとされています。学説上は、非通算説が有力(最高裁はない)ですが、 安全策を取るのであれば厚労省の解釈に従うほうがリスクは低いでしょう。
通算が必要とされるのは、法定労働時間の1日8時間/週40時間(32条)、働き方改革で規定された時間外労働の上限単月100時間/複数月平均80時間 (36条6項2号・3号)、割増賃金の支払(37条)があります。※休日については対象外。

出典: 経営ノウハウの泉
通算した結果、割増賃金の支払いなどは、どちらの企業が負うものなのでしょうか? 本業企業、副業先企業のどちらが労基法上の責任を負うかについては、基本的には副業先が負う場合が多いため、副業人材の受入れの場合には注意が必要です。
『改定副業・兼業ガイドライン』では、まず所定労働時間については“労働契約の先後”(=労働契約をした順番、下図であれば企業A→企業Bの順)で足し合わせ、次に所定労働時間外については“労働の先後”(=実際に労働した順番、下図であればパターン①:企業B→企業Aの順、パターン②:企業A→企業Bの順)で足し合わせ、結果として、法定時間外に労働させた方が法的責任を負うとしています。

出典: 経営ノウハウの泉
なお、厚労省は、『改定副業・兼業ガイドライン』で、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定する、自己申告も不要の“管理モデル”という簡便な労働時間の管理方法も提示しています。
雇用契約で外部人材を受け入れる場合は、“労基法上の責任を負う可能性があること”、“自己申告制度を設計(管理モデルの場合を除く)”、“自社の解釈スタンスを決めておく”などが大切です。
リスクから考える副業の制度整備のポイント
禁止できない“副業”のために、企業はどのような規定を設けるとよいのでしょうか。

出典: 経営ノウハウの泉
隠れて副業をする「伏業」とは?
副業の原則禁止はできませんが、労働者の労働時間を適切に管理するために、副業する際には会社への届け出をしてもらうように“許可制”にするなど規定を設けることは可能です。しかし、本業の会社に副業の届け出をしても「不許可にされそうだからこっそりやろう……」と“伏業”で副業を行われるケースも少なくありません。
堀田先生いわく、“伏業”にされないために、副業ルールとして“許可基準の明確化”が必要とのこと。許可基準としては、『モデル就業規則』の内容から考えることができます。
『モデル就業規則』(2018年1月改定)では、副業・兼業について、“会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者は当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる”とし、副業を禁止・制限できるケースについて以下の4つを挙げています。
①労務提供上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する場合
③会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④競業により、企業の利益を害する場合
また、企業によっては時間数等をより具体化することも多いですが、画一的判断は難しいためオススメできないと堀田先生は述べました。
「伏業」された時の企業のリスク
隠れて副業をされる「“伏業”で起こるトラブルが怖い」と警鐘を鳴らす堀田先生。
“伏業”では副業の内容・状況が見えないため、かえって企業利益を毀損するリスクがあり、しかも、企業がとり得るのは事前予防ではなく事後対応となってしまいます。何をやっているのかよくわからない状況では、懲戒処分を行っても、不許可事由にあたらない限り懲戒処分は無効となります。

出典: 経営ノウハウの泉
副業トラブルを防ぐための制度と誓約書
“伏業”でのトラブルを避けるために、副業については、事前申請、許可制度、取消制度といったルール整備が重要。
『モデル就業規則』にあるような不許可事由に該当する場合には、会社の利益が害されるので不許可にできます。そのため、該当するのかどうか、会社の利益を守るために“事前申請”を受けて、予め審査する“許可制度”が必要です。さらに、事後的な報告を受けつつ、不許可事由が生じた場合には取消が必要になってくるため、“取消制度”も取り入れるべきです。これには、“安全配慮義務の履行”という重要な意味もあります。
こういった、副業制度を明確化し、企業と労働者で認識の齟齬を生じさせないために、“誓約書の提出”も大切です。誓約書には下記のような内容を含め、採用時の誓約書のみならず、副業にあたっても、再度誓約させておくことが望ましいです。副業にあたっても、再度誓約させておくことが望ましいです。
・不許可事由に該当する副業は、企業の利益を害するものであるので、この点の表明・保証を得ておく
・申請内容が真実であることの表明・保証
・情報漏洩禁止を再確認
・副業先が反社でないことの誓約、その他
なお、副業を認めた社員に対して、残業をさせたときに「副業を認めたのに残業を命じるの?」と本業の業務命令を拒否するケースもあります。副業を認めたからといって、残業命令権を放棄したわけではなく、残業命令拒否等は、人事考課や懲戒処分の対象となります(副業の不許可・取消事由にも)。これを認識させる等の目的でも、誓約書の提出を受けることが適切です。
副業制度はまだ日本企業では一般的とは言いがたく、正確な法的理解がされていません。誓約書もそうですが、十分な説明をしっかりと行い、認識の齟齬がないようにコミュニケーションを取っていくことが必要不可欠です。
今回のウェビナーでは、堀田陽平先生を講師に迎え、企業の副業対応や副業制度のルール整備のポイントについてお話ししていただきました。
副業の事前申請でチェックしておきたい細かな項目など、詳しくは資料に記載されているので、ダウンロードしてご覧ください。
セミナー終了後に寄せられた質問と回答はこちら
【質問①】
ソフト設計をする技術者が、会社を通さずに、個人で請け負うケースがあり。
競業するため禁止としたいが、可能か。
【回答】
競業避止違反は、副業を禁止制限できる事由の一つではありますが、会社ノウハウや企業秘密の漏洩の可能性があるかという点を検証する必要があります。
裁判例でも、これらの具体的な事由があるとして懲戒解雇を有効とした例がある一方で、運送会社従業員が運送のアルバイトをしていたという事例では競業を検討することなく懲戒解雇を無効としたものもあります。
ご質問の副業を禁止できるかは、上記のように具体的なケースによってきますので、競業の場合は禁止という旨の規定をおきつつ、申請・許可制度を設けて個別に判断される方がよろしいかと思われます。
【質問②】
過重労働による労災発生の際に本業先が責めを負う可能性があるということで、副業を認める場合は本業での残業時間+副業先での勤務時間の合計が80時間以内になることを条件に、副業の許可書面を発行するつもりでおります。このような形で許可を行うことで本業側は安全配慮義務を果たした(結果として月80時間を超えて健康障害が生じた場合は就業者本人或いは副業先の責にできる)という認識で宜しいでしょうか?
【回答】
まず、ご質問のように合計80時間以内となることを条件に許可することは、有効とされる可能性高く、問題ないと思われます。
他方で、安全配慮義務については、裁判例上様々な事情が考慮されるため、ご質問の条件を付すことは会社側に有利な事情として斟酌されるものの、確実に安全配慮義務違反を免れるということにはならない可能性が高いと思われます(従業員側がどのような理由で請求を行うかにも左右されます)。
具体的には、例えば、自社での労働だけでは考え難いような疲弊の状況等がみられる場合に、漫然と放置していると、会社の責任ありとされると考えられています。
会社としては、そうした状況が見られる場合には原因を確認し、それが副業によるものであるのであれば、「労務提供上の支障がある」(これは副業の禁止・制限事由の一つです)として、一度許可した副業を取消すことが考えられます。
こうした事後的な措置までを行うことが、安全配慮義務との観点では要求される可能性があります。
こうした措置を講じることができるよう、許可をした後も一定の報告義務を課したり、許可の取消を規定しておいた方が良いかと思われます。
【質問③】
許可後に残業指示の時間帯に副業勤務時間が含まれることについて、本人は拒否できるのですか?(本業の就業に支障がでていると判断は可能ですか)
【回答】
質問のご趣旨としては、「副業を許可した場合には、従業員は、副業を理由に残業命令を拒否することができるか」というご趣旨と理解しました。
これを前提に回答いたしますと、副業の許可を行った場合でも、当然に残業命令を排除することとなるわけではありませんので、会社は副業を行う時間帯であっても残業命令を行うことができ、従業員はこれを拒否することができません。
結果的に、残業命令違反が生じた場合には、人事考課や懲戒処分によって対応が可能ですし、「本業に支障が出ている」として副業を取消すこともできます。
ご質問のような相談はよく聞かれるところでありますので、従業員にもこの点を誤解されないよう、誓約書等で「残業は命じる場合があることを理解した」旨誓約させることが有効と思われます。
【質問④】
“夜間宿直を副業にするスタッフがいます。
通常の1日8時間とは、午前0時からの24時間で考えるのでしょうか?
例えば
PM9時~AM5時の勤務は、3時間分は前日分。5時間は翌日分となるのでしょうか。
その場合、休憩を0時までにとったのか、0時以降にとったのかも確認する必要がでてきますか?
そもそも、宿直のみ(監視又は断続的労働)の勤務は、労働局で通常の勤務時間とは異なる対応がされており、賃金形態も異なると思うのですが、どのように把握すればよいのでしょうか。
【回答】
まず、1日8時間については、就業規則において特段の定めがない限りは、ご指摘のとおり午前0時からの24時間となるとするのが厚生労働省の解釈です。
そのうえで、2暦日にまたがる労働については、別に分けるのではなく、始業の時から連続して労働時間を算定するとするのが厚生労働省の解釈です。
そのため、15日午後9時00分〜16日午前5時まで連続して勤務した場合には、ご理解とは異なり、8時間労働したこととなります。
宿直勤務を副業にするスタッフがおられるとのことですが、そうした宿直勤務の者は、ご指摘のとおり、労基署の許可を得ることで労働時間規制の適用を受けないこととなります。
改定副業・兼業ガイドラインでは、そうした労働時間制度の適用を受けない労働者については、労働時間の通算は不要であることを明言していますので、この場合は、通算は不要となります。
ただし、管理監督者と異なり、労基署からの許可が必要となりますので、当該許可を受けているのかどうかはご確認されるとよろしいかと存じます。
なお、副業の事前申請・許可制度を設けることで、そうした情報を予め収集することが可能になります。
登壇資料とセミナー動画ダウンロードはこちら
メールアドレスをご登録頂きますと、資料ダウンロード用のURLをご案内いたします。またご登録頂きました方には経営ノウハウの泉メールマガジンをお送りいたします。個人情報の取り扱いについては個人情報保護方針をご参照ください。なおCookieの取り扱いに関しては、Cookie情報の利用についてを、個人情報保護方針の定めに優先して適用いたします。










