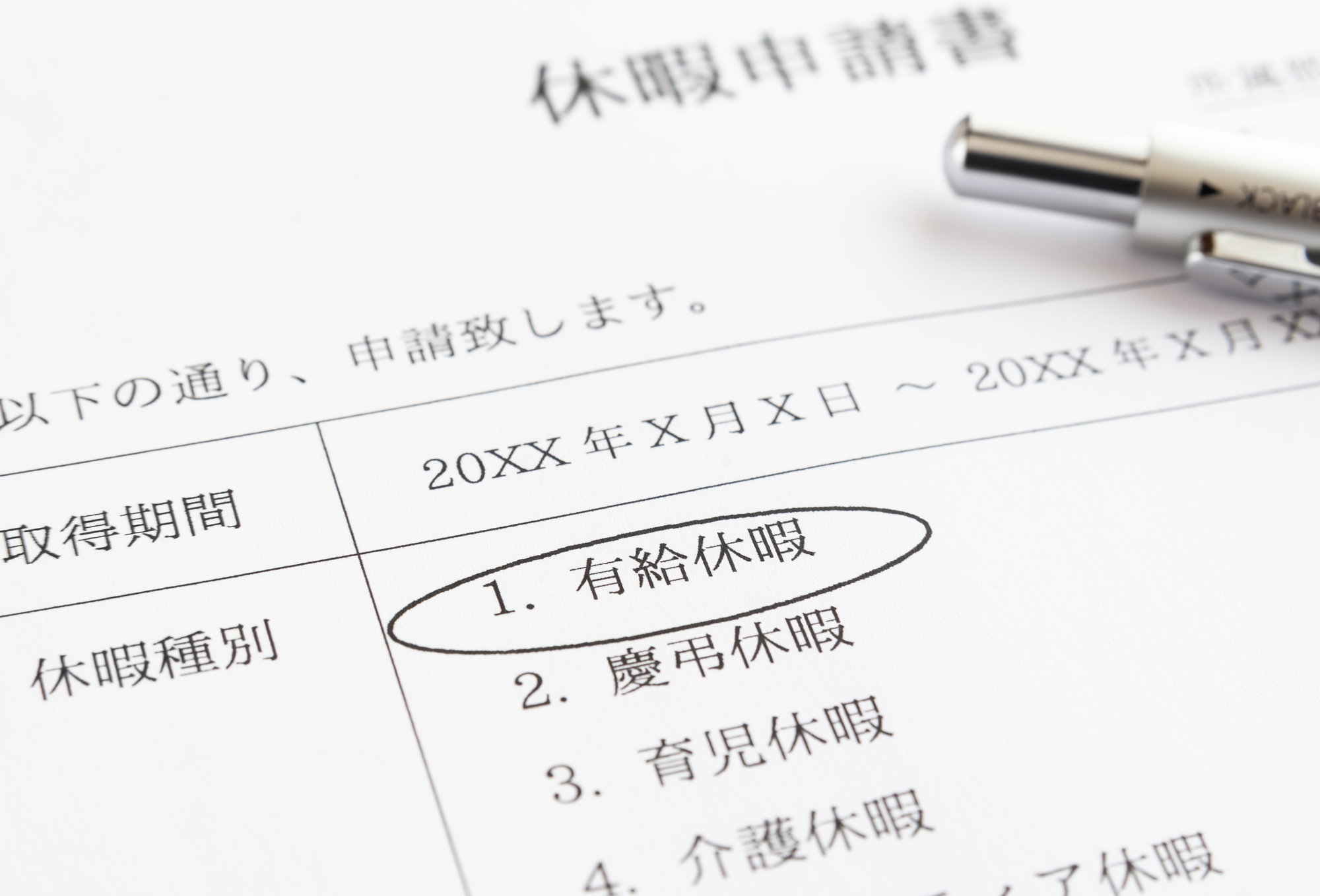
昨今よく耳にする“働き方改革”という言葉ですが、働き方改革の一環として、年次有給休暇制度の法改正がありました。年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させなければならないというものです。
これは、大企業・中小企業に関わらず実施しなければなりません。対象になる労働者も、正社員だけでなくアルバイトやパートといった非正規労働者も含まれます。
今回は、年次有給休暇の基本的な事項から法改正に関する事項までを解説していきます。
そもそも年次有給休暇って?
年次有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月継続して働き、その間の全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。ここでいう全労働日とは所定労働日、すなわち、雇用契約上の労働義務のある日をいいます。事業所の営業日ではありません。
たとえば、月曜から金曜の週5日勤務の雇用契約であれば、それが所定労働日となり、週2日勤務の雇用契約であれば、それが所定労働日となります。
ここで説明した内容は、労働基準法に定められた最低基準なので、これより労働者に有利な制度を会社独自で設けることは全く問題ありません。たとえば、“出勤率7割以上で年次有給休暇を付与する”、“入社すぐに年次有給休暇を付与する”といった定めをすることは可能です。
そして、年次有給休暇については、正社員だけでなく、アルバイトやパートといったいわゆる非正規労働者であっても付与されます。もちろん、週5日勤務者と週2日勤務者とでは、付与される年次有給休暇の日数には違いがあります。
しかし、たとえ週1日、1回1時間の勤務であっても、雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。また、管理監督者であっても年次有給休暇は付与されます。
2回目以降の年次有給休暇付与については、付与日から1年経過ごとに付与されます。その際には、その1年間の出勤率が8割以上という要件を満たす必要があります。
理由なく年次有給休暇の取得を会社側は拒否できない
年次有給休暇は、労働者が取得を希望したときに与えるのが原則です。会社が理由もなく年次有給休暇取得を拒否したり、取得時季を指定することはできません。
ただし、労働者から年次有給休暇取得の希望があった時季に与えることが“事業の正常な運営を妨げる場合”には、他の時季に取得するようにと断ることができます。ちなみに、“事業の正常な運営を妨げる場合”とは、一律に線引きできるものではありません。
事業所の規模や、年次有給休暇を希望する労働者が従事する業務の内容や性質、繁忙期かどうか、代わりの者を配置することが容易かどうか等によって異なってきます。また、年次有給休暇取得が1日、2日といった短期なのか、それとも、数週間に及ぶ長期取得を希望するのかにもよっても変わってきます。
そして、年次有給休暇は、付与されてから2年経つとその権利が消えます。したがって、入社6ヶ月後に与えられた年次有給休暇は、使わなければ、入社から2年6ヶ月経つと消えてしまいます。
ところで、労働者は、年次有給休暇取得希望をいつまでに会社に伝えなければならないか? というのが問題となることがあります。会社の定めとして、3日前や1週間前、シフト制などの場合にはシフトが出る前までにといったルールが定められていることもあるでしょう。
しかし、法律上は何日前までといった定めはありません。そのため、3日前や1週間前に会社に申請すると定めたからといって、必ずしも、その定めが有効となるわけではありません。年次有給休暇取得を会社が認めるかどうかは、あくまで「事業の正常な運営を妨げるかどうか?」という判断によって行われなければなりません。
2019年4月に法改正実施 その内容は?
ここからは、法改正に関する話をしていきます。
2019年4月から、「年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、会社は、年5日の年次有給休暇を取得させなければならない」という法改正が行われました。この法改正について、いくつかポイントを挙げていきます。
・ポイント1 年10日以上の年次有給休暇が付与されていればアルバイトも対象
年間10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者が対象です。これは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどのいわゆる非正規労働者であっても、年10日以上の年次有給休暇が付与されていれば対象となります。
・ポイント2 有給付与日から1年以内に取得させる必要がある
年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
・ポイント3 労働者が自ら取得しない場合、会社側から時季を指定し取得させる必要がある
労働者自ら年次有給休暇を5日以上取得していれば何の問題もありませんが、そうでない場合、会社が年次有給休暇の取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
この際、労働者本人から意見を聴かなければならないことになっています。これについては、労働者自ら年次有給休暇を5日以上取得した場合には、会社は年次有給休暇取得を指定することはできません。
・ポイント4 会社側が年次有給休暇の時季指定を行う場合、就業規則に記載が必要
会社が年次有給休暇の取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる場合、就業規則への記載が必要となります。
これは、就業規則への記載がなければ今回の法改正による時季指定ができないというよりは、休暇に関する事項については就業規則への記載が必要とされているためです。
また、年次有給休暇管理簿を作成することも、会社に義務付けられました。年次有給休暇管理簿には、年次有給休暇付与日や取得日数、年次有給休暇を取得した日付などを記録する必要があります。
以上のように、年次有給休暇について、大きく法律が改正されています。今までは、労働者から年次有給休暇取得の希望があっても、それを許さない会社もありました。
いまだに、「うちの会社には年次有給休暇はない」などと言い張っている事業主もいるようです。しかし、もう、そういう時代ではありません。今どき、年次有給休暇をまったく取れない会社など、労働者からソッポを向かれてしまいます。まず優秀な人材は集まってきません。
インターネットなどから、誰でも年次有給休暇についての知識を得られますし、会社の評判も調べられます。労働者は、中小企業だから年次有給休暇が取れなくても仕方がないなどとは思ってくれません。行政の目も厳しくなっています。今後、この流れに対応できない会社は淘汰されていくことになるでしょう。
※CORA / PIXTA(ピクスタ)








