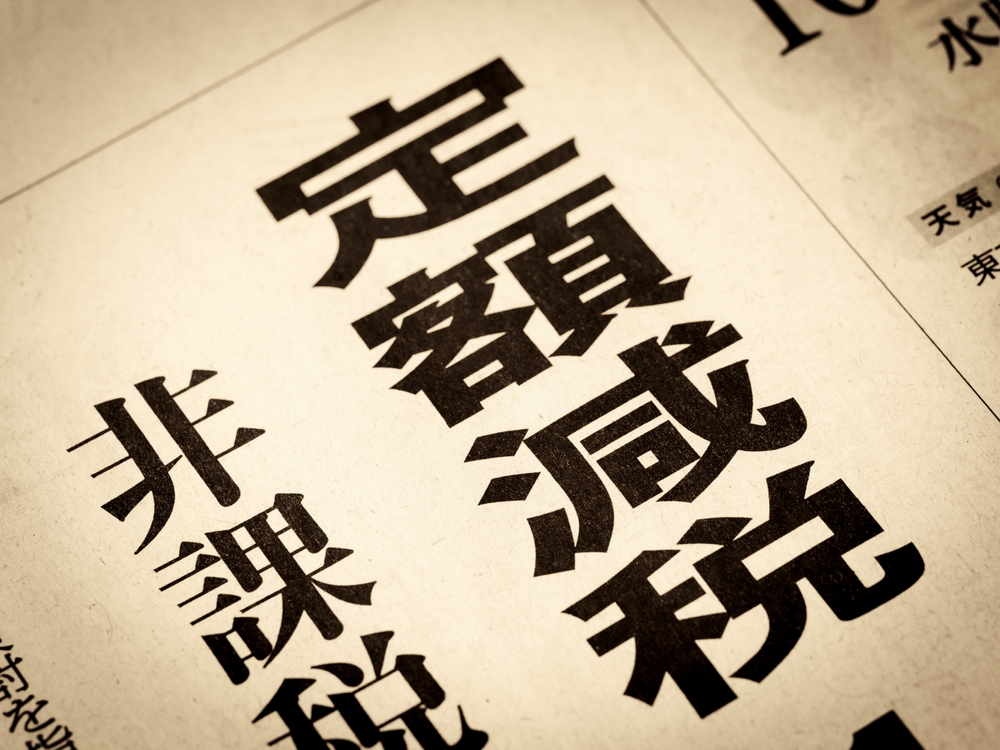
【2024年6月スタート】定額減税の事務処理対応、これで大丈夫?担当者のお悩みをチェック!
2024年6月より「定額減税」がスタートします。
国民の税負担を減らすことが目的のこの施策、代わりに現場の事務処理負担が増えることになり
対応担当者は「これであっている?」と不安に感じることもあるのではないでしょうか…?
今回は現場の「定額減税」に関するお悩みをピックアップしました。
同じように対応に悩む方の質問を見て、自社の対応の参考にしてください。
1.定額減税の所得税と住民税の対応はこれでよい?
質問日:2024年3月25日
◆質問内容(一部抜粋)
(前略)
定額減税の仕方について2点教えて下さい。
① 毎月の所得税額が変動する場合
6月分:5,000円
7月分:6,500円
8月分:7,000円
↓
6月分(定額減税30,000円-5,000円=25,000円)
7月分(繰越の定額減税25,000円-6,500円=18,500円)
8月分(繰越の定額減税18,500円-7,000円=11,500円)以後、控除しきれるまで続く・・・の考え方で合っていますでしょうか?
② 住民税の定額減税
計算は事業主がするのでしょうか?それとも、市からの特別徴収決定書に既に計算されたものが送付されるのでしょうか?調べてみてもいまひとつ理解ができずこちらにお願いした次第です。
宜しくお願い致します。
◆総務の森に寄せられた返信はこちら
回答①
(前略)
> ① 毎月の所得税額が変動する場合
はい、控除しきれない部分は順次控除するそうです。> ② 住民税の定額減税
計算された通知書が送られてくるはずです。
また定額減税の対象者の場合、6月は徴収せず7月から5月までの11分割になるようです。
回答②
こんばんは。
そろそろ税務署から定額減税について内容の判るものが送付されてきます。
既に送付されている事業所もあります。
先ずはそちらで確認されるといいでしょう。
単に減額するだけではなく個人別管理表の作成も必要になりますので。
住民税は該当市町村のwebに説明がされていますので該当市町村のwebを確認されるといいでしょう。
結論として国税は概ねその考え方で合っています。
住民税は元々役所が計算しますので事業所で何かをすることはありません。(後略)
回答②への返信
(前略)
弊社は定額減税の仕方のパンフレットが送付されたので確認したのですが、何となくの理解に終わったので相談させて頂きました。住民税の計算が不要と知り安心しました。
ちなみにですが、個人別管理表の作成は義務なのでしょうか?また、月ごとの減税ではなく、年末調整でまとめて処理するのは間違いなのでしょうか?
回答③
現状では出来ません。
最終結果として年調対応とはなりますが月次減額の対象者は毎月減額処理をすることになります。(中略)
各人別事績簿は所得税額が各人で異なるため3万に至るまでの残高管理をする必要があります。
3万を超えて控除は出来ませんし3万に至らない場合や最終清算は年調時ですからその際に各人の状況管理が必要になりますので事績簿不要とはならないでしょう。
国税庁はあくまでサンプルですから自社で管理しやすい台帳でもいいようです。(後略)
回答③への返信
(前略)
まとめて年末調整ではなく、毎月の減額処理をしていかなければなりませんね。従業員にも給与支給の際の明細にも減額を記載しなくてはならないようですね。税務署のパンフレットより断然と分かりやすいご説明に感謝です。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『 定額減税(所得税・住民税)について』
2.定額減税を機に扶養家族を追加したい場合の会社対応
質問日:2024年5月16日
◆質問内容(一部抜粋)
定額減税についてご教示をお願いします。
弊社のある従業員からの申し出です。
(なお、この従業員は甲欄で、扶養親族は0です。定額減税の対象者です)「今年、自分の配偶者が退職をした。退職金の支給により今年の所得が定額減税の対象条件を超えてしまうため配偶者は定額減税の対象外となる。定額減税の対象外となった場合、その扶養親族も定額減税の対象外となってしまう。これまで配偶者の扶養となっていた子ども二人を自分の扶養に変更したい」
(なお、お子さん二人は10歳と17歳、扶養親族の要件は満たしています)。
当従業員の申し出通り、お子さんを新たに扶養に入れる場合は、どちらを提出してもらえばいいのでしょうか。
*「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(R5年度の年末調整時に提出済みなので再提出となる)
*国税庁の定額減税特設サイトにある「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。
また、配偶者は今のところ再就職の予定は決まっていないそうですが、退職所得だけで当従業員の年間所得は超えています。共働きなどの場合、「原則今後1年間の収入見込みの多い方」の扶養に入れるとの規定があるようですが、変更できないのでしょうか。(後略)
◆総務の森に寄せられた返信はこちら
回答①
(前略)
> 当従業員の申し出通り、お子さんを新たに扶養に入れる場合は、どちらを提出してもらえばいいのでしょうか。
どちらの方が好ましいのか分かりませんが
扶養親族に異動があるという理由で、基準日までに「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらえば良いのではないかと思います。> そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。
これは分かりません。
> また、配偶者は今のところ再就職の予定は決まっていないそうですが、退職所得だけで当従業員の年間所得は超えています。共働きなどの場合、「原則今後1年間の収入見込みの多い方」の扶養に入れるとの規定があるようですが、変更できないのでしょうか。
収入の多い方の扶養に入れるというのは社会保険の話で
税扶養に関しては本人が選択できるのではないでしょうか。
(御社で家族手当支給などのルールがあれば、話が別かもしれませんが)
回答①への返答
ご回答ありがとうございます。
扶養親族に異動があるという理由で、基準日までに「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらえば良いのではないかと思います
こちらを提出してもらいます。
そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。
この件についてはネット上でも明確な答えが見つからない状態です。
最終的には税務署に問い合わせするしかないかと考えています。収入の多い方の扶養に入れるというのは社会保険の話で
> 税扶養に関しては本人が選択できるのではないでしょうか。こちらについては勘違いしていました。
大変助かりました。ありがとうございました。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『定額減税を機に、扶養親族を追加したい』
定額減税のほかにも!確認すべき税制改正のポイント!
令和5年12月22日、令和6年度税制改正大綱が閣議決定されました。今回の税制改正は、法人の賃上げやイノベーションの創出を進める目的での賃上げ税制の強化やイノベーションボックス税制の創設、個人の生活負担の軽減等の目的での所得税、個人住民税の定額減税や住宅ローン控除の拡充等がなされています。
そのほか、今回の税制改正大綱には、扶養控除の見直しや防衛力強化に係る財源確保のための税制措置等、社会的耳目を集める内容もありますが、本稿では中小企業経営者に特に関心のありそうな改正内容についてポイントを解説します(なお、本稿は税制改正大綱に基づく解説であり、実際に成立する改正法とは異なる可能性もありますので、予めご注意ください)。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『中小企業の経営者必見! 令和6年度税制改正大綱の変更点と注視すべきポイント【弁護士が解説】』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。
*yoshi0511/ Shutterstock








