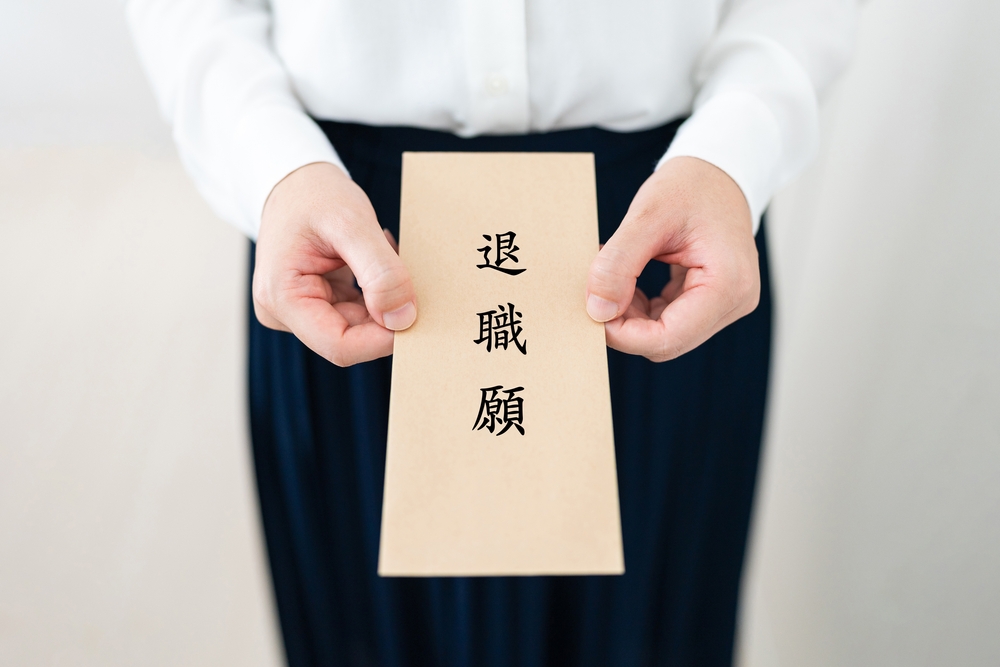
「こんな場合はどうしたらいい?」漏れなく進めるために!退職手続きに関するお悩み
10月は秋入社のタイミング。その裏で、9月に退職する人が増えてくる時期です。人事部などの退職手続き担当者の皆さん、対応手続きに困ったことはないですか。特に繁忙期には、予想外のケースや複雑な手続きが発生し、対応に追われることもあるのではないでしょうか。
本記事では、退職手続きに関するお悩みについて取り上げました。退職日が迫り、迅速な対応が必要になることもあるかと思います。ぜひ参考にしてください。
1. 退職後、健康保険の限度額適用認定書の使用は?
質問日:2024年7月22日
◆1. 質問内容(一部抜粋)
(前略)
退職予定の社員ですが、転職先も決まっており、そこで健康保険証を交付される予定です。
その社員の家族の医療費が高額のため、現在限度額適用認定書を交付されております。
その様な社員からの相談ですが、転職してすぐに限度額適用認定書の交付申請が
心理的にしにくい。
よって、任意継続制度で現在の健康保険組合に加入し、交付されている限度額適用認定書を使用したい。
転職先では、資格喪失証明書の提出は求められていないようですが、このようなことは可能でしょうか。
会社としては、保険資格抹消、新会社での限度額適用認定書の申請の方向で話をしますが、本人が勝手に任意継続の手続きを行えばこの様なことも可能になると思います。
この様な事例をご存じのかたがいらっしゃれば、ご教示をいただきたいのですが・・・。
◆1. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
すぐに再就職するのであれば、そのようなことはできません。
任意継続について、就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したときに資格を喪失することになっています。
なので、再就職後も任意継続を利用するということがそもそもできません。(後略)
●回答②
社員が任意継続制度を利用し、現行の健康保険組合に加入し続けることは理論的には可能です。ただし、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。
1. 任意継続の条件:
– 退職後20日以内に申請すること。
– 退職前の2ヶ月間以上継続して健康保険に加入していたこと。2. 限度額適用認定書の使用:
– 任意継続により、現行の健康保険組合に引き続き加入する場合、現在の限度額適用認定書がそのまま使用可能です。3. 転職先での対応:
– 新しい会社が資格喪失証明書の提出を求めていない場合、任意継続での対応が可能かもしれません。ただし、新しい会社の健康保険制度に加入しないことで問題が発生しないか確認が必要です。4. 注意点:
– 任意継続保険の保険料は全額自己負担となります(会社負担分も含む)。
– 任意継続は2年間しか利用できません。その間に新しい会社の健康保険制度に切り替えるタイミングを見計らう必要があります。社員がこの手続きを行う場合、現在の健康保険組合および新しい会社の総務部門に相談し、具体的な手続きや影響について確認することをお勧めします。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『退職予定の社員の健康保険について』
【関連記事】漏れはない?実務チェックシートで確認!
下記は、退職手続きに関する実務チェックシートです。細かな処理の漏れがないように、チェックシートを参考に手続きを進めませんか。実務内容のToDoリスト化や申請手続きに必要な参考情報リンクを載せておりますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『従業員が退職する場合の対応チェックシート』
2. 立替経費、この場合は雇用保険を徴収する?
質問日:2024年7月3日
◆2. 質問内容(一部抜粋)
(前略)
弊社では月末締め当月25日払いで給与を計算しております。
立替経費の精算が1か月遅れで給与に反映されてくるので、
退職した社員の経費精算が退職後に発生することになります。たとえば、6/30退職の場合、6/25支給給与で
・6月分の給与支給
・5月分の立替経費精算
をおこない、7/25支給にて、
・6月分の立替経費精算
となります。この場合、7/25支給分では雇用保険料は徴収するのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
◆2. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
こんにちは。
社員立替分ですよね。
給与ではありませんのでそもそも雇用保険の対象にはならないと思いますが。
今までは雇用保険対象支給とされていたのでしょうか。
そちらの方が問題のような気がします。
(後略)
●回答①への返信
(前略)
交通費の精算ですので対象としておりました。
(交通費以外の経費精算については、対象外として計算しております)
社労士がそのように計算しておりましたので、引き継いでからも同じようにしていたのですが、そもそもそれが誤りだったということでしょうか?
無知で申し訳ございません。
ご教示いただけますでしょうか。
●回答②
横からですが…
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/koyou-07.pdf
「交通費」の範囲の問題になりますが、通勤手当は雇用保険の対象となりますが、出張時にかかる交通費の精算は雇用保険の対象になりません。
●回答②への返信
(前略)
交通費については通勤にかかる交通費になります。
弊社(派遣会社)に在籍している社員で、日によって出社先が異なる場合が多く、かかった交通費を翌月精算する形を取っています。
それ以外の出張交通費は別で経費精算項目を作成し、雇用保険の計算の対象には含めておりません。
●回答③
(前略)
それであれば社労士が処理していたように、雇用保険の対象で良いと思います。
最初の質問に戻りまして、
退職後に支給する給与ということで迷われたのだと思いますが、
変わりなく雇用保険料を控除してください。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『退職後に支給する給与の雇用保険料について』
【関連記事】他にもある!退職手続きに関する悩みを解決
転職が当たり前になっている昨今。新たな社員を迎え入れると同時に、会社を離れる社員もでてきます。そこで生まれる悩みが退職者への対応。特に金銭に関わることは、退職者や担当者、さらには経営者にとっても大きな問題になりかねません。上記の他、退職に関するお悩みを見ていきましょう。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『退職時のこの対応はOK?NG?退職に関する皆さんのお悩み』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考ください。
※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。
*yu_photo/ Shutterstock







