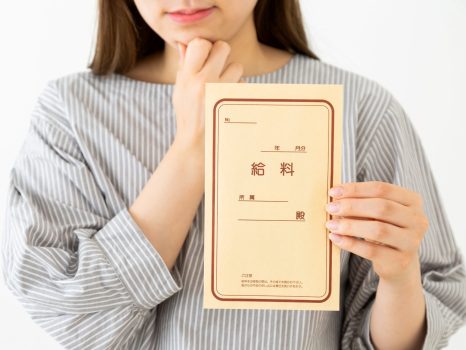社員のエンゲージメントが向上する”福利厚生”導入のために!皆さんの福利厚生に関するお悩み
社員のエンゲージメント向上のために、「福利厚生の導入」を検討する企業様も少なくないのではないでしょうか。しかし、『これは福利厚生として扱ってよいのか』『所得税が発生してしまうのではないか』と、足踏みしてしまいなかなか導入が進まない…となってしまっては本末転倒です。
そんな今回は、福利厚生に関するお悩みをご紹介します。実際に導入しようとした際の悩みから、自社に導入する際の参考にしていただけますと幸いです。
目次
1.自由な「物」の購入は福利厚生にできる?給与課税となる?
質問日:2023年12月11日
◆質問内容(全文)
法人です。年末の企画で、福利厚生企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(特定します)で各自が何でも購入して良くて、いつもの経費精算時に精算する、という通達が出ました。
社員の中には「福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいる一方、形のある「物」を購入することを望む社員もいます。また、ギフト券はだめ、というルールもあります。
今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか。
▼総務の森に寄せられた回答例
回答①
こんばんは。
ギフト券は給与課税です。国税庁に記載されています。
またなんでもいいというのも給与課税に該当します。
慶弔関係でギフトブックというのがありますがこちらが何でもいいものに該当し給与課税と国税庁にあります。
品物限定・選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能です。
福利厚生ですから全員平等というのは基本ですが何でもアリではありません。自由選択…カタログギフト… 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm永年勤続についてですが判断は同様でしょう。
商品券…ギフト券等… 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm金券についての判断です。
(後略)
回答②
横からすいません。
>選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能
これは、根拠等ありますでしょうか。
ほんとにOKならば、弊社としても考えてみたいなあと思うところなのですが・・・
回答③
逆説的解釈です。
本人が自由に選択できるものであれば給与課税の問題が発生する。
であれば自由選択が出来ないものであれば給与課税は発生しない。
ただ記念品でもなくお祝い品でもないとなると多少希望が通ったとしても問題ないのではないか。
実際永年勤続祝い品等は本人が指定物品から選択できる場合もあります。
税務署お得意の社会通念上という判断から物品指定…ネクタイやハンカチ、シャツやバッグ等…で色、形違い等で2,3種類であれば自由選択とまではならず多少の希望が叶うのではないかと考えます。
この中から選んでねとなると事業所指定とも言えますから自由選択とはならないと考えます。
物品指定ですから金額も同一になると思います。
以前ネットでも同様の税理士解釈を見たことがあります。
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか』
2.社内インスタント販売の費用補助、注意点は?
質問日:2023年7月11日
◆質問内容(全文)
社内の食事に関する福利厚生・補助についてご質問させてください。
今回、社内の福利厚生としてインスタント食品の販売サービスが始まりました。
オフィスグリコのようなもので、冷蔵庫が設置されその中に冷凍食品が入っており、
各自自由に購入して電子決済を使って料金を払うというものです。
冷凍食品の商品代の半額を会社が負担、残りの半額は本人が負担(※)するということになったのですが、
食事代を負担するということになるので、所得税や標準報酬などに影響してきますでしょうか?※定価400円のものであれば、社員は購入金額200円を支払う。
月末に販売サービス会社が差額の会社負担分を計算し弊社に請求という流れになります。注意点などありましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
▼総務の森に寄せられた回答例
回答①
(前略)
所得税については下記の2点をクリアしていれば非課税になるかと思います。
1. 従業員が半額以上を負担。
2. 会社負担額が月額で3,500円以下であること。詳細は下記の国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
次に社会保険では2/3以上を本人負担の場合は0円ですので、半額では社会保険の計算の際に、現物報酬として加算されることになります。
詳細は下記の年金事務所のHPをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/0000027877bYkqWHPcfN.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
労働保険については、下記の厚生労働省のURLより、1/3以上徴収しているので福利厚生とみなし加算はないと考えられます。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038571.pdf
(後略)
回答①への返信
(前略)
課税等については既に出ていますので別の視点で…
食費補助月3,500は個別に計算できるものでしょうか。
会社負担分の請求書に個別明細があり精算出来るのであればいいですが正直現実的ではないように思います。
経験則では給与手当…食事手当等…として支給して補助としていました。
月の利用額が多くても少なくても手当ですから固定支給です。
その上で本人は食事代を支払うという形をとっていました。
個別精算の手間を考えると手当支給も方法かと考えます。(後略)
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『社食の補助について』
「福利厚生」は導入すべき…?中小企業で導入できる福利厚生をご紹介!
労働力不足が叫ばれるようになって久しい昨今では、雇用した社員がすぐに辞めてしまうなど、社員の定着率に懸念のある企業は少なくないでしょう。このような企業におすすめしたいのが”福利厚生の充実”です。しかし、中小企業の場合、「大企業のような大掛かりな福利厚生は必要ないのでは?」と思う経営者がいるかもしれません。
ここでは、中小企業でも導入を検討すべき福利厚生とはどのような内容か、紐解いていきましょう。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『大手じゃないから「福利厚生」なし?中小企業でも導入検討すべき「福利厚生」は』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは「総務の森 利用規約」をご確認ください。
*fizkes / Shutterstock