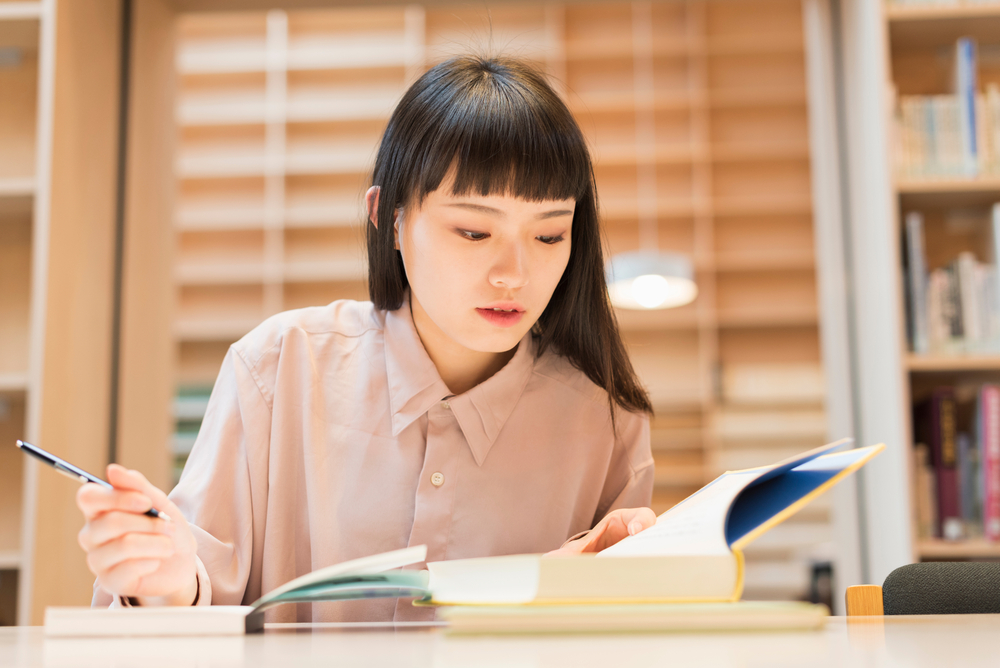
【あなたの会社はどうしてる?】資格取得で社員のスキルアップ!の前に考えておきたい資格の管理方法のお悩み
4月に入り、新たな目標を考える時期かと思います。
スキルアップのために資格取得を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社経由で資格を取得する場合は、会社で管理する必要があります。
必須の資格や昇給・昇格に影響するものもあり、経費や社員への働きかけなども考慮する必要があります。
個人に紐づくものだからこそ、会社での管理や運用に悩むこともあるかもしれません。
そんな悩みを今回はピックアップ。ぜひ参考にしてください。
1.社内の資格管理はどのように管理すべき?
質問日:2024年2月9日
◆質問内容(一部抜粋)
各部署の取得資格の管理のために、毎年4月に計画表を作成しています。
部署数、資格数、従業員数とも増加していく中で現状の管理方法では運用できなくなっています。
現状は自社作成したDBで管理しています。
資格取得状況一覧作成、更新期限、承認帳票作成、受験回数管理、受験費用等です。他の会社ではどのような管理方法を行っているか教えてください。
管理はどこの部署が行っているか?
どのような管理方法をおこなっているか?
などです。(後略)
◆総務の森に寄せられた返信はこちら
回答①
当社の場合、取得計画と資格保有者については別管理です。
取得計画は部署が取得のための費用含めて管理しています。所詮「取らぬたぬき」の話です。ちなみに当社は資格取得に関しては部長権限なので、人事部は関与しません。これは年度内に資格挑戦者や資格内容を変更するなど柔軟に対応できる反面、会社運営のための必須資格を「取らせる」力が働かないので、退職者が出て初めて真っ青になる可能性があります。会社運営の必須資格とその保有者については人事部が独自にリスト化しているようです。
取得済みの資格は人事情報に紐ついています。こちらは資格保有者の話ですので、誰がその資格を使って選任業務につくかは人事と当該部署との折衝により決まります。上記で述べた会社運営にとっての必須資格が手薄と人事部が判断したら、年度計画策定時に各部に対し⚪︎⚪︎の資格を取得してください、という指示連絡が来ます。従うかどうかは各部判断です。私はここが弱いと感じています。
回答①への返答
ご説明ありがとうございます。
各部門ですか、取得状況と、申込自体も各部門で行っているのでしょうか?(後略)
回答②
部門メンバーの公的資格取得状況管理は部門で一覧表にしています。ISOの要求事項なので、毎年改定しています。また新規資格取得のための受験申込等も部署で行なっています。
衛生管理者申込時の実務経験証明書のように受験資格がある場合の証明書類についても同様です。会社が証明するので会社印の捺印は総務が行なっていますけどね。
(後略)
>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『資格管理について』
2.入社後に会社負担で資格取得、その後すぐに退職した場合はどうしたらよい?
質問日:2023年9月4日
◆質問内容(全文)
建設業を営んでいます。
若い社員に積極的に資格取得を推進しております。
各種建設機械の資格・主任技術者の資格など様々な資格や講習等があります。
全額会社負担(休業補償等含む)で取得をさせていますが、高額な資格などがあり取得後数年して退社してしまう場合もあり得ると思います。
社員が買い取ってくれるのかそのままお持ち帰りなのか何か取得前に約束事のような
物があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
◆総務の森に寄せられた返信はこちら
回答①
(前略)
「買い取ってくれる」というのが、会社が負担した取得に要する費用を支払え、という意味であれば、できないです。労働基準法に反する行為です。
回答②
(前略)
まず、作業主任者や主任技術者等の資格は、会社に帰属するものではなく、個人に帰属するものですから、社員に買い取らせる、ということはできません。
初めからその人のものです。資格の取得にかかる費用を会社が負担したのであれば、その返還ルールを事前に決めておくことはできません。
賠償予定の禁止に抵触します。可能なのは、会社が取得費用を本人に貸し付ける形です。
一定の年数の勤続で、返還を免除する条件にすることで、資格取得後すぐに退職されてしまう、ということを防ぐ効果を得られます。
ただしこの場合でも、会社の業務上絶対に必要な資格であるような時には、返還請求が認められないようなこともあるようです。
回答③
(前略)
資格は個人について回るものなので、会社が買い取ることはできません。
社員の自己都合退職時に会社が負担した資格取得費用を返還させるのは、他の方の回答にもある通り労働基準法違反(第16条 賠償予定の禁止)となります。ただし、会社が取得費用を社員に貸し付け、資格取得後一定の期間が経過したら、返還義務を免除する、という方法は合法です。ただし「一定の期間」は公序良俗に反しない程度の期間である必要があります。(5年程度が多い)これは、社員を社費留学させて学位を取得させる際によく使われる方法です。
(後略)
回答④
(前略)
直接の回答は皆さまのとおりで、私見です。
結論としては、割り切るしかないと。
建設・土木関係では資格がないと就けない業務等あり、会社として推進せざるをえませんよね。
当然自己負担で「とれとれ」と言っても進捗はせず。必要なものは会社負担も止む得ないところもあると。その上で、取得した方全員がお辞めになるわけでもないとすると、資格を取得してお辞めになられる方に拠出した分は、ある程度のコストと割り切るしかないとの認識です。かかったお金よりもその様な人が辞めていく事に損失を感じ、辞めさせたくないという心理なのかもしれませんが。
退職リスクと自己に任せて資格者がなかなか出てこない場合の会社のリスクとの比較考量でしょうか。
「取得後何年かは辞めません」等の念書も、心理的な歯止めに少しはなるでしょうが、法的には役に立たないものとの理解です。
>詳しくはこちら
総務の森<相談の広場>『資格所得について』
資格を取得して成長?!会社と個人の成長のために「スキルマップ」を活用!
新しい人材を採用するだけでなく、今いる人材を活用することも会社の成長には重要な考え方です。
社員としても自身の成長を感じられないと働くモチベーションが低下してしまうでしょう。
会社と個人それぞれを成長させるために必要な”スキルマップ”の作成方法について解説します。
自分自身で成長の管理をするためにも、ぜひご活用ください。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『【テンプレート付】「スキルマップ」とは?作り方や活用方法を解説』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。
※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。
*FOUR.STOCK/ Shutterstock








