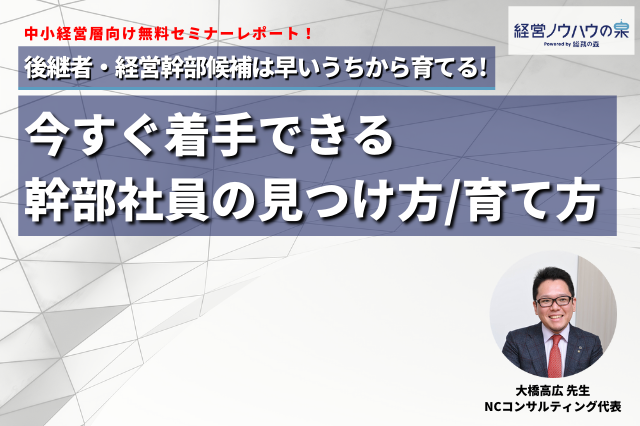次の候補がいないのはなぜ?管理職不足に陥る中小企業にありがちな3つの原因
筆者の知人の経営者が「定年を過ぎても管理職として働いてもらった社員が、いよいよ退職を迎えるが次の適任者がいない……」と嘆いていました。その会社では、管理職候補の中堅社員はいるものの、その中堅社員の業務を引き継ぐ若手社員が不在なため、管理職への登用が難しい状況に陥っていました。
なぜこのような管理職不足になってしまうのでしょうか? そして、この状態を回避するためにはどうすればよいのでしょうか?
本記事では、中小企業診断士である筆者の経験をもとに、管理職不足に陥ってしまう会社の3つの原因をとその対策について考えてみたいと思います。
原因その1:会社で働く上での「長期的なキャリアパス」が不明瞭だから
そもそも社員の多くが早い段階で辞めてしまい、慢性的に人材が不足しているというケースです。要因としては、会社で働く中での最終的な目的や、そこへ向かっていくための道筋であるキャリアパスが不明確という場合が多いです。
「この会社で働き続けて、どのような業務経験を積んでいくことができるか」「経験や能力を身に付けた先にはどのようなキャリアに到達できるか」というようなことが明確でないと、「今の仕事の先にどのようなことがあって、その時自分はどのくらい成長しているか」というようなイメージがしづらくなるでしょう。そうするとキャリアの目標が設定できず、ただ日々の仕事をこなすだけになってしまうかもしれません。
会社で働き続けることで目指せるキャリアの目標が明確であれば、そこに向かって具体的な課題を設定して取り組むことができます。その結果、人材の成長にもつながっていくことでしょう。逆に、目標を持ちづらい環境であれば人材の成長が停滞し、気づいたら「管理職を担える人材がいない」ということが起こってしまうかもしれません。
■対策
例えば、若手・中堅・管理職といったように会社の階層を設定し、それぞれの役割・責任や具体的にどのような業務を担うかということを明確にするとよいでしょう。
そうすると「今の仕事がどこにつながっていくか」という成長の段階がイメージしやすくなり、「目標に到達するために不足していることは何か」というように課題を設定しやすくなります。課題を意識しながら日々の業務を行うことで人材育成を促し、将来的に管理職を担う人材を創出していくことにもつながっていくでしょう。
原因その2:計画的に管理職育成を図る仕組みがないから
次の管理職が育っていないという理由で、ある社員が定年を迎えても引き続き管理職的な役割を担ってもらうということがあります。
定年を迎え本来は役職を下りるべきところ、人材が不足しているということでそのままの役割を維持するというケースです。
本当に人材不足でやむを得ないということもありますが、「管理職が自分の後継者を育ててこなかった」ということに起因することもあります。
定年を迎える年はあらかじめ決まっており、それまでに必ず「自分の後継者を育てる」ということを意識して、具体的な育成計画を立て実行に移していれば上記のようなことは起こらなかったかもしれません。
■対策
あらかじめ後継者となり得る部下を選定し、定年を迎えるまでの数年間は後継者育成を最優先の目標に設定するということが挙げられます。
毎年どのような業務を教えていくかというような管理職育成の計画を作成し、会社のバックアップのもと実行に移していきます。現管理職が直接指導するOJTに加え、管理者が身に付けるべきテーマについて外部研修で学ぶという風に組み合わせることも有効です。
後継者となる管理職候補に対して、事前に意向を確認した上で管理職育成を図ることでよりスムーズな移譲にもつながるでしょう。
原因その3:管理職としての責任ばかり重くて権限が少ないから
管理職として、担当する組織について様々な責任を負っている一方、それを達成するための十分な権限がないという場合です。
例えば、管轄する組織の売上目標達成を目指すために部下へ指示命令する権限がなければ、当然ながら目標達成は難しいです。高い目標に対する責任を負っていながら、達成するための創意工夫する余地が少ないことや、自らが実行者として動かざるを得ず疲弊してしまうでしょう。このようなことが起これば、それを見ている若手社員は管理職を目指すことに対して希望を失ってしまうかもしれません。
「管理職になっても大きな責任を持たされるだけで魅力がない」という風になってしまえば、そもそも管理職を目指したいという社員がいなくなってしまいかねません。
■対策
管理職として担うべき責任とそれを果たすための権限の大きさが一致しているか確認しましょう。
例えば、組織の売上や利益目標に責任を負っているのであれば、それを達成できる経営資源の配分や指示命令などを行えることが前提になります。
面談などを行い、目標自体に対する同意や実行するための計画立案のフォローを行い、管理職と経営層で目線をすり合わせることも有効でしょう。
もし管理職不足に陥っていると感じていて、ここで挙げた3つの原因が該当するということであれば、ぜひ対策の検討をしていただきたいです。
きっと管理職不足解消の一手となることでしょう。
* kouta / PIXTA(ピクスタ)