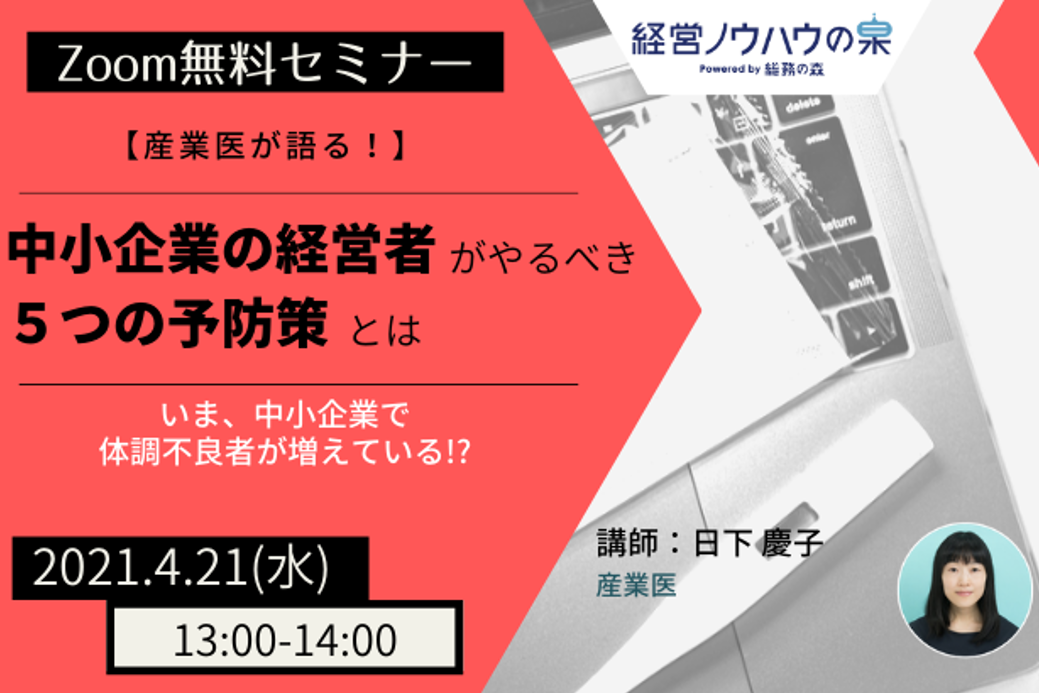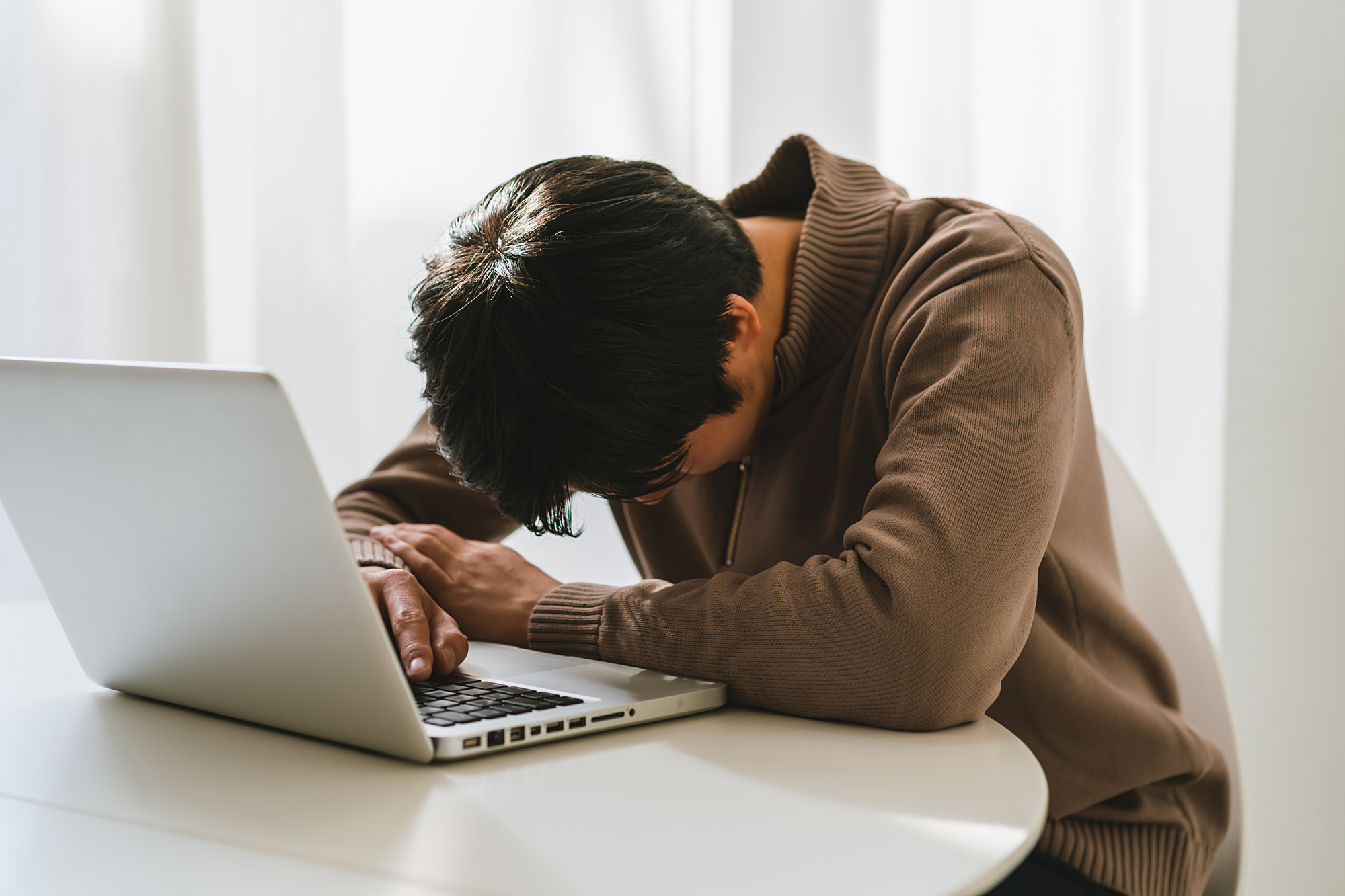
あの人がどうして?誰でもなり得る「心が壊れる前兆」と経営者として取り組むべきこと
「なぜ社員がメンタル不調になるのか?」という悩みを抱える経営者は少なくありません。早めにそのサインに気づくことで、社員の休職や離職を防ぐことができるはずです。
そこで今回は、メンタル不調に陥る人の兆候と原因について解説します。記事の後半では企業や経営者が取り組むべきことを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
心が壊れる前兆とは?メンタル崩壊の症状
メンタル崩壊の症状で1番に着目すべき点は、体から出るSOSのサインです。たとえば、疲れ、痛み、炎症・微熱の症状がある場合は心が壊れる前兆かもしれません。兆候の例として以下が考えられます。
・頻繁に鎮痛剤や胃腸薬を飲みながら仕事をしているのに改善しない
・お腹を壊して下痢になる
・37度台の微熱が出て体にだるさを感じる
体は心の疲れに正直ですので、メンタル不調のSOSを無視しないようにしましょう。
中小企業における人材の重要性
人材確保は会社の存続を左右するほどの重要課題です。多くの中小企業は“人が足りないこと”に悩みを抱えています。その背景には労働人口の減少や、求人倍率の高さがあるようです。厚生労働省が発表した『一般職業紹介状況(令和4年1月分)について』によると、有効求人倍率が増加傾向にあります。これは、求職者に対して人材を確保したい企業側の数が多いことを示しています。つまり、企業の人材確保競争が激しくなり、人材不足に陥るリスクが高まる可能性があるということです。
欠員が出ても代替できる人的リソースが潤沢にある前提での業務遂行が難しくなり、優秀な人材を流出させないためにできる限り不満を減らす施策を考えて実行しなければなりません。メンタル不調への対策もその一つです。もし、いくら施策を講じても社員の心に響かず空振り感を抱いているなら、表面的な課題解決ではなく、社員がメンタル不調になる要因を根本的に理解する必要がありそうです。
メンタル崩壊の原因とは
メンタル崩壊の原因の1つとして、自信のなさや自己肯定感の低さが挙げられます。
たとえば「後輩に出世のスピードを追い抜かれた」「同僚の方が先に資格試験に合格した」「あの人の方が先輩に好かれて優遇されている」などです。他人と比較して「自分は負けた」と認識することで自信を失い、落ち込んでしまうことがあります。
社会人になると自分の努力だけではどうにもならないこともありますが、それに気づくことができないまま、自分を責め続けてしまうのです。
あの人がなぜ?メンタル不調は誰にでも起こり得る
メンタル不調は誰にも起こり得ることです。「絶対大丈夫だ」と思っていた人が突然陥ることもあります。
ここでは、タフな人がメンタル不調に陥った2つのケースをご紹介します。
ケース1
Aさんは新規事業の立ち上げで業務量が増加して疲労を感じやすくなり、長時間労働に辛さを覚えるようになりました。他のメンバーが自分のサポートをしてくれないことへの苛立ちもあります。疲労が蓄積してだんだん働きづらさを感じるようになり、「どうして自分だけ」と不平不満が出てくるようにもなりました。
誰かがミスをすれば乱暴な言葉が飛び交い、雰囲気も悪化しています。はじめは「休めば何とかなる」と思っていた程度の疲労が、毎日の職場で嫌なことが起きるたびにマイナス感情が増えて、「眠れない」「イライラする」「不安が増大する」などの問題に発展していきました。
仕事へのやりがいも薄れていき、今まで楽しく前向きに取り組んでいた仕事も、だんだん後ろ向きになっていきます。「この仕事に向いてないのかもしれない」とマイナス思考に陥り、最終的には体調不良による遅刻や欠勤が発生して、メンタル不調を引き起こしました。
考えられる原因
考えられる原因は多岐に渡りますが、職場に関するものでは主に以下の3つが考えられるでしょう。
・企業の求める業務量と社員の考える対価に対する業務量のギャップ
・本人の能力を超える業務内容・業務量による負荷
・困った時に気軽に相談できる窓口がない
ケース2
Bさんは上司から業務を細かく決められることが精神的圧迫になり、働きづらさを感じるようになりました。「干渉が行きすぎている。これはパワハラじゃないか?」と思うようになり、やる気の低下や気持ちの落ち込みを自覚するようになります。周りに対して「あの上司は嫌いだ」といった発言をすることが増え、職場内での人間関係が悪化していきました。
考えられる原因
原因として考えられるのは、大きく分けて3つあります。
・上司の高圧的な態度による負荷
・能力に合わない業務の遂行による負荷
・同僚との比較によるマイナス感情の増幅
このケースでは、上司のコミュニケーション問題以外にも、部下の能力と業務内容のミスマッチの可能性も考えられます。
人にはそれぞれ得意・不得意があります。不得意なことを多く任せると想像を超える努力が必要となり、メンタル面に悪い影響を与えることもあるのです。
経営者として取り組むべきこと
ここからはケース1とケース2それぞれの事例に対して、実際に起こった場合に経営者が取り組むべきことを紹介します。
今一度、業務量や勤務態度を見直し、当てはまるところがあればぜひ参考にしてみてください。
ケース1
疲労が溜まっている社員を早期発見し、社員が取り組んでいる業務量の見直しを行い、心身状態の悪化を食い止めることを最優先にしましょう。具体策としては、管理職による現場での声かけ、過重労働時の心身健康を確認する問診の実施、産業医面談の実施を行ってください。
まずは社員が抱えている業務量を正確に把握するところから始めましょう。そのあと業務に優先順位をつけ、会社内で再分配できないか、外注できないか、システムに代替できないかを検討します。ワークフローシステムを導入し、全社的な業務フローの見える化を測ることも一つの手です。
業務マニュアルを作成し業務手順を揃えておくことも大切です。なかには、任された業務を1人で抱え込み、周りに助けを求められないケースもあります。なるべく早い段階で助けを求められるように、マニュアルに加え、確認フローを整え、進捗状況をリアルタイムで共有できる環境を作るようにしましょう。目標管理ツールなどを用いれば、簡単に社内共有ができます。
ケース2
経営者および管理職の“マネジメントの3要素の理解”が必要です。マネジメントの3要素とは以下の通りです。
(1)業務管理:目標設定、業務計画の作成、業務指示、進捗管理
(2)評価:部下の評価実施、評価の伝達
(3)精神的サポート:キャリアサポート、1on1ミーティングなど会話機会の創出
まずは経営者自身が、以下を意識するところから始めてみてください。
・成長目標を掲げ続ける
実現が明らかに難しい目標ではなく、実現可能かつ今までの水準を上回る目標設定をしましょう。そして、市場がどんなに変化しても「前年より必ず成長する」という意識を持って仕事に取り組むことが大切です。チームで問題を共有してみんなで解決していく姿勢を忘れないようにしましょう。
・視野を広げる
マネジメントにおいては、下記2つの意味で視野を広げることが重要です。
・高い位置から俯瞰する
・時間軸を長くする
問題に直面したときこそ、一歩引き、一時的な感情で判断することのないようにしましょう。
・社員の声を受け止め関係を築く
社員の声にしっかり耳を傾け、相手に敬意をもって接しましょう。ミスをしたのであれば、リーダー自ら率先して素直に認め、改善に努めることが大切です。「自分は間違っていない」と否定せず、「そう言われるということは、何か間違いがあるのかもしれない」と現場の声を真摯に受け止めるように心がけてください。
・社員の感情に関心を持つ
精神的サポートはすぐに取り組みやすいでしょう。社員の“感情”に関心を持つことが重要です。1on1ミーティングなどコミュニケーションを図る機会を設けましょう。
マネジメント層への啓蒙はどう進める?
では、経営者はどのように“マネジメントの3原要素を管理職に理解させるとよいのでしょうか? おすすめは社内研修を実施することです。管理職の役割に対する認識を社内で揃えることができます。オンライン学習や外部の研修講師に依頼するなどやり方はさまざまです。後者の場合、「自社の管理職に足りないスキルは何か?」「管理職が社内で求められていることは何か?」を把握したうえで、講師や研修講座を選びましょう。
また、管理職の人それぞれの特性や課題にあわせた研修を取り入れることも重要です。例えばプレイヤー思考が強い管理職の場合は、「マネジメントの必要性」「プレイヤー業務に偏ることで生じるデメリット」などの研修を用意しましょう。
【管理職必見】メンタル崩壊を防ぐ方法
いつでも相談できる窓口を周知しておく
一度メンタル崩壊に陥ると、ずっと引きずってしまい、「何もうまくいかない」と思い込んでしまう人がいます。そのような人の共通点は、ネガティブな気持ちを吐き出す場所がないということです。友人や家族などの身近な人に話しにくい場合は、社内の相談窓口を活用してもらえたらと思います。
明らかに自分の限界を超えるような辛い出来事であれば、一人で抱え込むべきではありません。心が壊れる前兆があった時は、なるべく誰かに気持ちを吐き出して相談するようにしましょう。
心が落ち着く環境を整える
気持ちを落ち着かせる方法として、アロマオイルの活用をおすすめします。
とくにラベンダーの香りは、昂った交感神経の働きを抑えてリラックスさせる効果があるため、落ち込んだり、イライラして落ち着かなかったりするときに向いています。
実際に、精神科をはじめ、産婦人科や緩和ケア科などでは診療にアロマオイルを使い、リラックスした空間を提供する病院もあります。
目標を立てて成功体験を増やす
メンタル不調があっても早い段階で回復できる人の共通点の一つに、自信を持っていることが挙げられます。
目標を立てて成功体験を増やすことで自信を持つことができ、モチベーションも上がって集中力や思考力も高まるという好循環を生み出すことができます。
ポイントは以下の3つです。
・目標を自分で決める
・今の自分ができる範囲で目標を決める
・目標を誰かに伝える
目標を伝える相手は家族、友人、会社の同僚や先輩など誰でも構いません。
ただ、メールや掲示板で伝えるよりは口頭で伝えることをおすすめします。
まとめ
メンタル不調は誰にでも起こり得ます。社員が1人で不安を抱え込まないよう、企業全体で連携しながらサポートできる仕組みを整えていきましょう。
*mits、tokinoun / PIXTA(ピクスタ)