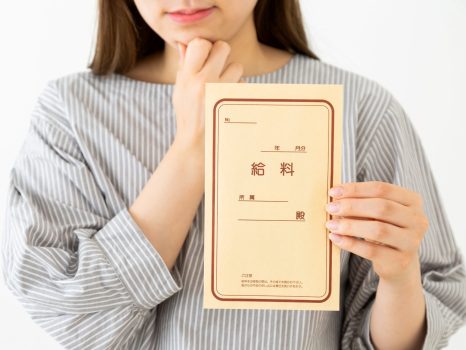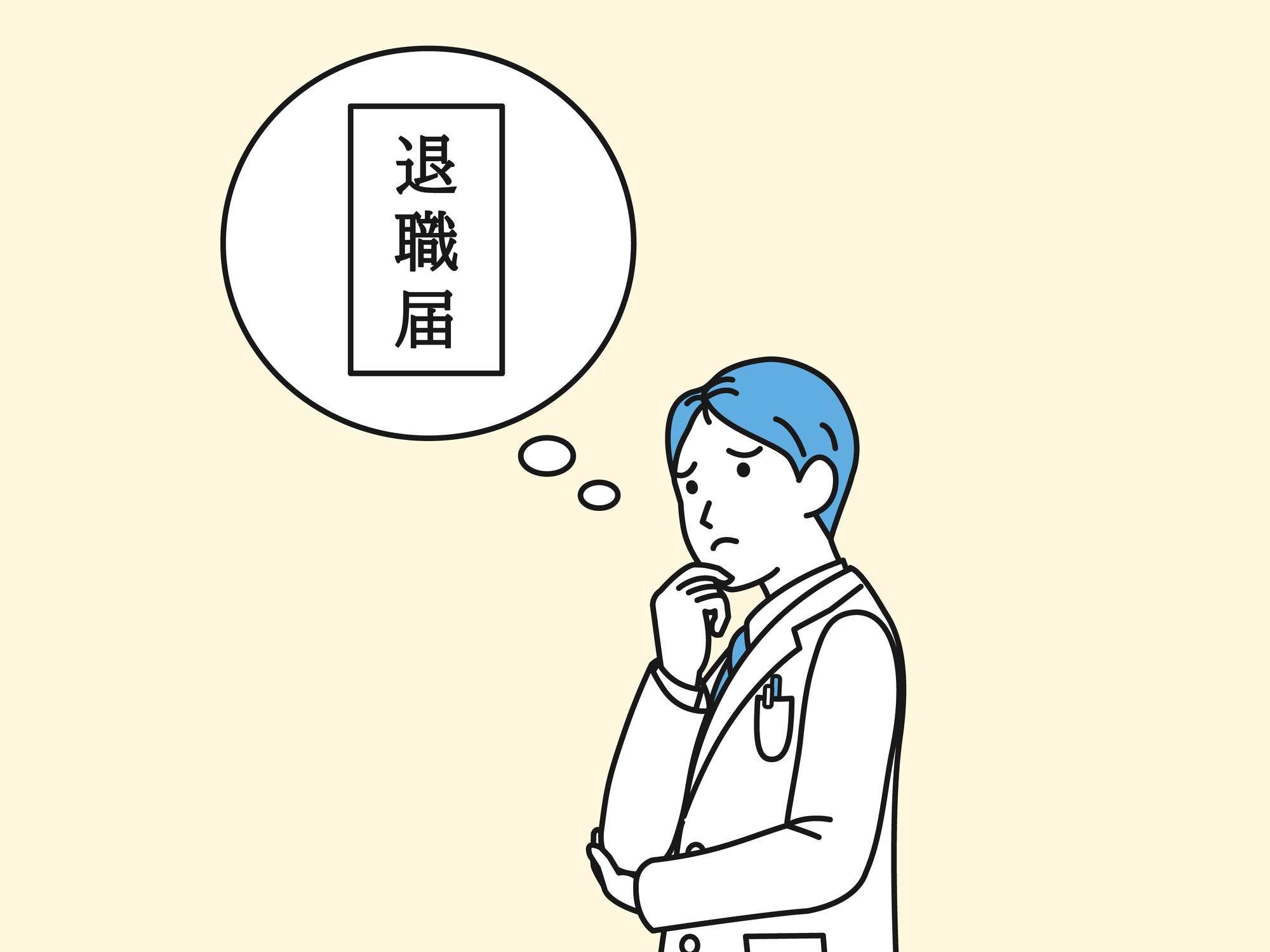
エースが退職「まさかやめるとは…」人材流動化にどう対応する?
「これからの自社を担うと期待していたエース人材から退職の申し出があった……」「他の社員からも数名退職の相談がある……」コロナ禍を経て人材の流動化が進み、このような話を聞くことが増えてきました。仕事面でも人間関係としても1名でも社員が退職するインパクトは大きいものです。ましてや、エース人材やキーマンの退職ともなれば、業務や役割だけではなく精神的なインパクトが生じてしまいます。
しかし、転職者数が増加する昨今、人材の流動化を止めることは難しいでしょう。もちろん、退職しないことが理想ですが、「エース人材が在籍する期間に会社として何かヒントを得る」という考え方もあるかもしれません。今回は、エース人材の能力を自社で活用する方法を解説します。
目次
なぜエース人材は離職してしまうのか
エース人材が離職してしまう理由として大きく3つ挙げられます。
1)キャリアの道筋を描きにくい
組織が小さいゆえに昇進・昇格の機会が限られる場合があります。また「キャリアアップを望まず専門性を深めていきたい」と考える社員もいるでしょう。そのため「この会社では、希望するキャリアを歩めない」と判断した際、他企業への転職を考えることがあります。
2)ワークライフバランスが悪い
責任や業務量の多さがストレスとなり、誰にも相談ができずに「この会社では働き続けることができない」と判断してしまうケースがあります。
3)コミュニケーションが不足
上司や同僚など社員同士の間に信頼があり、安心感のもとで業務に取り組める職場かどうかは、定着率にも大きく影響します。“成功循環モデル(ダニエル・キム)”でもいわれているように、関係性がよくないと、個々のマインドにも悪影響が生じます。結果、パフォーマンスが下がり、成果にも影響します。そして、周りからの承認や成長機会を得られないと、モチベーションが下がり、退職意思が高まるという悪循環が起きてしまうのです。
給与が低い・残業過多など、目に見えることに焦点をあてた退職理由で理解するのではなく、その背景や深層にある「表には見えづらい・言葉にはしづらい理由として何があるのか」ということに耳を傾けましょう。すべてを改善することは難しいかもしれませんが「機会を次へ活かす」という発想をもち、打ち手を管理職で検討していく取り組みを進めることが重要です。
これらは、エース人材に限らず、従業員全員に当てはまりやすい退職理由です。思い当たる部分があれば、社員を巻き込んで改善していくほうがよいでしょう。
【キーマン社員の退職についてはこちらもおすすめ】「あの社員だけは辞めない」と思い込んでいませんか?キーマンが退職して起こる組織崩壊
エース人材が働き続けるためにできること4つ
では組織として、エース社員の退職はどのようにして防ぐことができるのでしょうか。
①明確なキャリアパスの提示
エース人材は、自己成長やキャリアアップを望む傾向があります。そのため、企業側は、明確なキャリアパスを提示し社員が将来像を描きやすいポジションや役割を示すことが大切です。
②公正な評価・報酬の提供
他の社員よりも優秀な成果を示しているエース人材に対しては、公正な評価制度のもと、適正な報酬を分配していくことが必要です。これらは、単に「給与を上げる」ということではなく、納得感と理解度の高い人事制度を組み立て、金銭的報酬だけではなく教育・成長機会といった非金銭的報酬も分配していく仕組みを考えることです。また、組織の声を反映していくために、社員も参画してもらい、人事制度の見直しを行うことも効果的です。
③成長機会の支援
新たなスキル習得や専門性の深化、成長機会を増やしていくため、学びの機会として研修・セミナーなどを積極的に開催したり、自身が選択して学べる制度を設けましょう。また、会社として社外コミュニティ活動への参画を支援することで「この会社での仕事を通して、人間的にも成長できる機会を得られた」という実感をもたせることも重要です。
④コミュニケーションの活性化
エース人材は、企業のビジョンや理念への共感が高く、組織の方向性についても理解しています。そのため、企業側は、コミュニケーションを積極的にとり、エース人材の意見や提案に耳を傾けることが必要です。「どのような環境・状況や働き方によってやる気が高まるか」という要素は、社員一人ひとり異なります。また、それらは随時変化していきます。そのため、日頃から1on1面談の場をもち、手短にでも高頻度のコミュニケーションの機会を定期的につくりましょう。それぞれの“働くワクワクの源”や“将来像”を確認し、自社におけるキャリアビジョンが立ち消えないように支援していくことが重要です。
【社員とのコミュニケーションについてもっと詳しく】どうしたら社員の本音を掴める?経営者が知るべき「社員とのコミュニケーション術」3つ
果たして、人材の流動化はよくないのか
人口減少や高齢化による労働力不足が予想され、労働市場が縮小する中で、エース人材やキーマンの流出は、職場に大きな影響を及ぼすだけでなく、企業の競争力低下につながります。しかし、働き方やキャリア観の多様化により「生涯同じ会社で勤め続ける」という意識が変化している点にも留意が必要です。厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概況」によると、男性の転職率は24.2%、女性の転職率は26.9%と、約4人に一人が転職をしているという結果でした。
大切な人材の流出や流動化は、採用・教育コストが無駄になったり、イノベーションが起こりづらくなったりするといった問題があり、マイナスに捉えられることも多いでしょう。しかし、前述のように転職が前提となりつつある今、会社として退職防止策以外にどういう手段がとれるのでしょうか。
【参考】令和3年雇用動向調査結果の概況/厚生労働省
①エース人材をどう活用できるか考えてみる
転職が当たり前になりつつある現代では、退職を完全に防ぐことは難しいでしょう。その場合、優秀な人材が社にいる間に何を残せるかを考えることも一つの手ではないでしょうか。たとえば、エース人材がもっている「次世代のトップセールスの育成」「キーマンの活動プロセスの理解・マニュアル化」といったスキルを標準化し、組織としてエース人材を再現することができれば、組織として有力なノウハウを得ることができます。
エース人材がどのように活動しているのか、ポイントは何なのかを把握するためにも、新入社員に教える機会を設けてみてもよいでしょう。
②外部人材として活用する
また、エース人材が退職後に起業・独立した場合に、良好なつながりを維持しながら外部人材として業務を委託し、ある程度は退職の影響を減らすことも手段の一つです。副業可能な企業も増えているため、エース社員も引き受けてくれるかもしれません。
③出戻り制度の導入
転職先の環境が合うかどうかは、入ってからではないと分からないことも多いものです。退職してしまったエース社員が「前の方がよかった……」と思うこともあるでしょう。そのような、他社を知った上で再び自社で働きたいという人が再入社できる“出戻り社員制度”などを取り入れることも有効です。
まとめ
自社におけるエンゲージメントを高める工夫を施していくことがエース人材の流出を防ぎます。しかし、自社に問題があるのではなく他の環境が魅力的であり、退職をとめることが難しいという場合もあるでしょう。辞めてしまうということにばかり目を向けるのではなく、どうすればエース人材のノウハウをどう再現できるか、どう活用できるかを考えてみてはいかがでしょうか。そうすることで、若手の育成も進み、組織の安定化を図ることができるのです。
【連鎖退職への対策はこちらもおすすめ】「退職が止まらない…」連鎖退職したらどう立て直す?内部改善に向けたファーストステップ
*川竜, emma, Gugu, OKADA / PIXTA(ピクスタ)