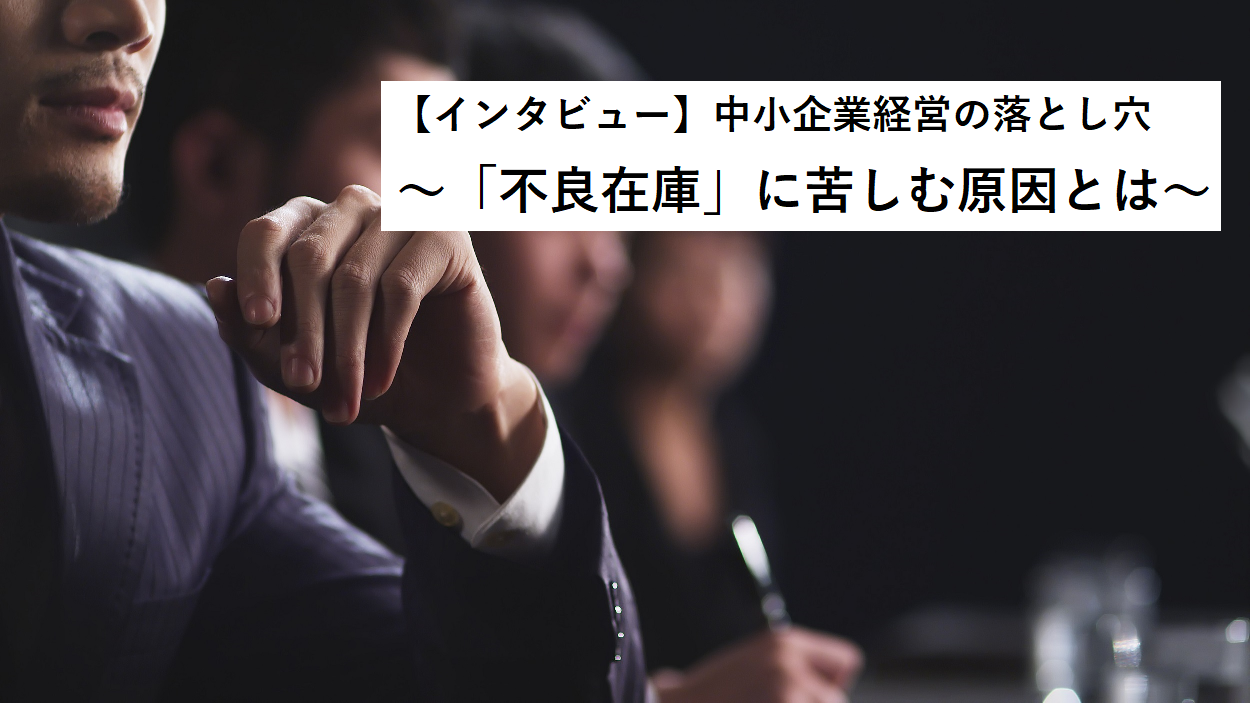売上98%減!絶好調ベンチャー企業にふりかかったコロナ危機をどう乗り越えたか(前編)
2020年に起き、2021年現在も社会経済に大きな影響を与えているコロナショック。
今もなお、多くの会社の経営者がこの荒波を乗り越えるために、苦慮し、試行錯誤を繰り返しているのではないでしょうか。
そんな中、前例の無い未曾有の危機に見舞われながらも、苦境を乗り越え、ピンチをチャンスに変えた経営者は数多く存在します。
今回は、リクルート出身で、インバウンド観光ベンチャー『WAmazing』を創業し、活躍している同社代表取締役の加藤史子さんにお話を伺ってきました。
WAmazingはコロナ禍という危機においても、とにかく「生き残る」ために必要なアクションを積極的に取ることで、危機を乗り越えただけでなく、この危機を逆に組織や事業を強くするチャンスへと変えていきました。
同じくこのコロナ禍という危機に立ち向かう中小企業の皆様には必見の内容となっております。

出典: 経営ノウハウの泉
「日本の観光産業を盛り上げ、地域活性を実現したい」急成長ベンチャー“WAmazing”とは
加藤さんが創業したベンチャー企業“WAmazing”は、「日本中を楽しみ尽くす、Amazingな人生に。」をビジョンに掲げ、2016年に創業。
台湾・香港・中国など主に中華圏のユーザーに対して、情報収集から宿泊予約、EC、交通・各種アクティビティなどの予約、決済までをワンストップで可能にする訪日旅行者向けプラットフォームサービスを提供する観光ベンチャーです。
創業以来、急速に成長を遂げ、2020年までに従業員数も100人を越え、日本人のみならず外国人社員も数多く在籍。加藤さん自身も、様々なメディアにて取材を受けるなど注目の企業になりました。
しかし、ここまで一見、順調に見える成長を遂げてきたWAmazingに、コロナの危機が襲いかかります。
突然やってきたコロナショックによる倒産の危機
加藤さんが、コロナウイルスの危機対応の必要性を強く感じ、動き出したのは、2020年2月14日、台湾の渡航注意アラートが発令のニュースを耳にした時からだったそうです。
「WAmazingを利用してくださるお客様で一番多いのが台湾の方。その台湾から訪日旅行客が制限されると分かった時に、これはとんでもないことになるぞ、と強い危機感を持ちました。」
その影響はすぐに現れ、予約キャンセルが相次ぎ、瞬く間に売上は98%減。このままだと3ヶ月後の5月には資金がショートしてしまう。そんな危機的状況に追い込まれたのです。
加藤さんは役員とともに、すぐに対策案を検討。「3月には対応策の打ち手を決めて、行動に移していました」(加藤さん)
運転資金を稼ぐための受託案件の獲得や、コストダウン、さらには資金調達など、やることは山積み。でも行動あるのみ、と迅速に動き出したのが大きかったと加藤さんは言います。
計画は悲観的に気持ちは楽観的に。9か月の苦闘
まず着手したのは、行政案件の受託や、外国人社員を多く抱えていたことから翻訳事業など受託で売り上げを稼ぐこと。
「まず私自身が自分で企画書を書いて受託案件を受注したり、SNSで翻訳事業の宣伝をしたりと動きました。私自身が動いて背中を見せることで、社員たちも”できるんだ!”と動き出すのです」(加藤さん)
早くに動き出したおかげで、5月の連休明けには受託案件の提案活動や翻訳事業の業務は軌道にのりはじめ、引き続きの推進は、社員に任せることができるようになります。同時に着手したのがコストダウン。
まず全社員に対して「人が一番大事だと考えているので、雇用を維持する」ことを表明。その上で休業や他社への人材出向といった処置をとることで、人件費の軽減に取り組みます。
しかし、それでもWAmazingが生き残るためには、まだまだ資金は必要でした。資金調達は2月から動き始めていたものの、難航していました。加藤さんは資金調達に集中的に取り組みます。
「2020年始まった頃には、もともと4〜5月頃に資金調達しようと、予定していたこともあり、政策金融公庫などの金融機関や投資家と話はしていたのですが、コロナがやってきてその多くはキャンセルになってしまいました」(加藤さん)
なんとか政策金融公庫より融資のゴーサインは出たものの、その条件として課されたのが、あと融資の金額とは別に5億円の資金調達。しかし、コロナ禍により「社会が停止していた」(加藤さん)のもあり、その資金調達は困難を極めます。
通常、WAmazingのような急速な成長を目指すベンチャー企業は、事業収益とは別にベンチャーキャピタルや金融機関、時には事業会社などへ資金調達活動を行います。2020年より前は、WAmazingは順調に成長していたため、多くの企業や金融機関が出資・融資をしてくれていました。しかし、コロナ禍になってから様々な会社や金融機関へアポイントを取っても、来る日も来る日も断られる毎日。
「最初、アポイント先をスプレッドシートでリストにしてひとつひとつ管理していたのですが、断られすぎて途中からもう更新しなくなったくらいです」(加藤さん)
でも、加藤さんは「計画は悲観的に、でも気持ちは楽観的に」考えることを大事にして、決して折れることなく一つ一つ商談を積み重ねていきました。
受託案件が売上を伸ばしたことも政策金融公庫に評価されて、目標額は4億円に減額になったものの、資金調達活動を始めてから、その4億円の資金調達の目処がついてきたのは9月半ば。そこから様々な手続きを経たり、外資系ファンドもあったので財務省の許認可の申請などの手続きも経て、最終的に資金が入金されたのが11月6日。
実に9ヶ月に及ぶ長い経営危機から、まずは生き残ることができたのです。

出典: 経営ノウハウの泉
問題の本質を捉え行動する。苦境を乗り越える思考法
9ヶ月にもわたり、次々と降りかかる問題への対処がなぜできたのでしょうか? 加藤さんは自分が超人だったからではなく、「問題や不安をそのまま受け止めるのではなく、常に『問題の本質って何か』を考え、それを一つ一つ細かく分解してやるべきことを順番に実行していっただけなんです」と語ります。
加藤さんがリクルート時代に手掛けた仕事の一つに、スキー場への若年層需要活性化をはかるキャンペーン”雪マジ19”というものがあります。その”雪マジ19”のアイデアを考えた着想法こそ、その問題の本質を捉え、それを分解して行動していくためのヒントがあるのです。
「当時、日本中のスキー場の多くは若者がスキー場に来なくなった理由として、”スキー/スノボ離れ”が原因だとして、スキーやスノボ以外の魅力を作らないといけないと言う方が多かったのですが、私はそこに疑問を感じていました。大自然の中をすごいスピードで滑走するスキーやスノボみたいなアクティビティの魅力って他にない楽しさがある。だから原因は他にもあるのではないか、そう考えたのです」(加藤さん)
加藤さんは、“スキー/スノボの魅力が低下してスキー場にお客さんが来ない。だから違う魅力を作る必要がある”という事が問題の本質ではなく、“レジャーが多様化し、スマホゲームや都市型BBQなどに可処分時間奪われているので、まずスキー場に来るきっかけを作らないいけない”という事が問題の本質であると仮説を立てます。
そこから、アンケート調査で、スキーやスノボに時間を使ってもらいリピートしてもらうのに一番相関性の高い要素をアンケート等で調べると「上達すること」というのを突き止めます。だから「上達保証プラン」を作ったり、シーズン中に3回いくと上達の手応えを感じ、その後も継続して毎シーズン、スキー場に通い続ける人が増えることがわかり、シーズンに3回行かせることを重要なKPIとして施策の判断を実行。
問題の本質に対し、一つ一つ分解して、打ち手を実行していくことで、”雪マジ19″を成功に導きました。
今回の危機の場合は「とにかくコロナ禍の状況をサバイバルすること」という目的にフォーカスし、一番大事なのは、「会社に資金を残すこと」と設定。
なのでそこで分解してやるべき活動を、(1)「お金をかけないで新規事業をやる」(2)「コストダウン」(3)「資金調達」と、大きく3つに分けて、一つ一つタスクを整理してブレることなく動いていったのです。
「コロナ禍で既存事業が落ち込んだから、今ニーズがありそうな新規事業をやろうとして、広告費や設備投資にコストをかけて対応する会社を多く見ましたが、私はそれをやっても意味がないと思っていました。なぜなら自社に既存リソースを持っておらず先行投資を必要とする新規事業をやると、会社にお金を残すことが大事なのに、新規事業が売れる前にさらに寿命を縮めてしまうからです」(加藤さん)
「コロナ禍で危機と言っても、打ち手も策も無限にあるし、やれることは無限にあるから可能性しかない。そう考えるようにしていました。ベンチャー企業も中小企業も諦めたら終わりで、周りが退場していく中、とにかく生き残れたら勝ちなんです。危機は、それを乗り越えることで逆に組織を強くするものなのです」(加藤さん)
インタビュー後半では、危機を乗り越えることができた強い組織づくりと、「人が一番大事」と語る加藤さんの経営哲学を紹介します。