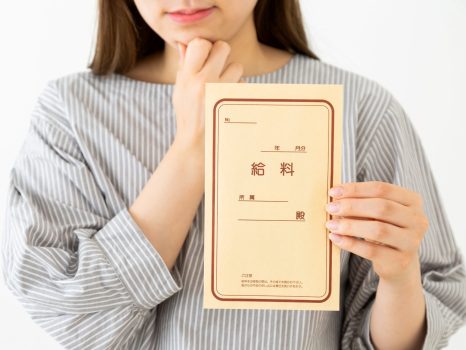法人税の中間申告(予定納税)は経営のキホン!期間や手続きをカンタン解説
会社が活動をする上で欠かせない義務の一つに、法人税の申告・納税が挙げられます。法人税は、株式会社や合同会社など、いわゆる「法人」が事業を行って出した利益に対してかかる税金のことです。
この法人税を申告・納税する方法の特徴に、年度途中で行う「中間申告」があります。
今回は、この法人税の申告方法として重要なポイントとなる中間申告の内容やスケジュール、手続きの流れなどを順に解説していきます。
中間申告には、さまざまなメリットがあります。健全な企業活動を行うため、中間申告を正しく理解し、適切な形で納税の手続きを進めていきましょう。
法人税の中間申告の内容とは
中間申告とは、納めるべき税金を前払いする制度のことです。会社の決算期間の途中の段階で、その期間中にかかる税金を前払いし、決算期間が終了した後に精算を行います。
決算期間が終了して確定した法人税額が、中間申告時の金額より多くなった場合は不足分の納付を実施し、少なくなった場合は払い過ぎた税額の還付が行われることになります。
中間申告には、期の中間時点でいったん申告を行うことで、企業が年に一度の確定申告時にまとまった金額の法人税額を算出するリスクを防ぐ狙いがあります。
また、税金を受け取る国や自治体側としても、一定期間ごとに法人税額を受け取ることで安定した財政収入を得ることが可能になるため、双方にとってメリットのある仕組みといえるでしょう。
中間申告の期間・対象とは
法人税の中間申告はいつ行っても良いというわけではなく、期限があります。
申告は、“事業年度が開始された日を基準とし、以後6ヶ月を経過した日の前日から数えて2ヶ月以内”に行う必要があります。注意すべきポイントは、経過日の「前日」である点です。間違えないように注意しましょう。
4月1日に事業を開始した法人の場合を例に挙げてみます。
この場合、中間決算日は6ヶ月を経過した日の前日であるため、9月30日です。つまり、9月30日から数えて2ヶ月後である11月30日までに中間申告書を提出し、税額を納付しなければなりません。税額の納付方法については、税務署や銀行の窓口で直接現金で行う方法や、コンビニでの納付、クレジットカードによる納付、「e-Tax」というシステムでネットバンキングを利用した納付などが挙げられます。
また、中間申告はすべての会社にとって必須ではなく、以下の通り対象者が定められています。
【中間申告の対象となる法人】
前期に確定した法人税額が20万円を超える場合(中間申告で納税する額が10万円を超える場合)
【中間申告の対象外となる法人】
(1)前期に確定した法人税額が20万円以下、もしくは赤字だった場合
(2)公益性のある法人
(3)設立初年度の法人(設立1年目のため、基準となる前期が存在しない法人)
ただし、合併により設立された法人の場合は対象外ではありません。この場合は、法人が合併する前の決算期間が対象になる点に注意が必要です。
中間申告の種類・計算方法とは
中間申告には、予定納税・仮決算という2種類の方法があります。
毎年どちらの方法で納税をするかを法人側で選択することができるため、状況に応じて年度ごとに使い分けることも可能になります。
(1)予定納税による方法
予定納税とは、納税者である法人の前期の実績を基準として行う中間申告のことで、原則として採用されることが多くみられます。具体的には、前期に支払った法人税額のほぼ半額を中間納付額とする方法です。
予定納税を行うメリットとしては、すぐに手続きができるという点がまず挙げられます。
例として、前期に確定した法人税額が400万円である場合を挙げてみましょう。下記の数式で算出をしていきます。
400万円÷12ヶ月=33万3,333円
33万3,333円×6ヶ月=199万9,998円
結果として、中間納付額は199万9,900円になります。端数が出た場合は100円未満を切り捨てましょう。なお、単に400万円を2で除して、200万円を中間納付するということではない点に注意が必要です。
(2)仮決算による方法
事業開始の年度より6ヶ月を経過した時点で中間決算を行い、その際に割り出された課税所得額に法人税率を乗じて中間納付額を決定し、中間申告をすることです。
法人税率は法人(資本金)の規模や所得額に応じて異なり、原則として規模や所得額の大きい法人ほど税率が高くなる仕組みを取っています。
仮決算による方法を採用する場合は、確定申告を行う場合と同様の流れで決算の処理をする必要があるため、ある程度の時間と労力がかかります。
しかし、今期に業績が著しく悪化し思うような利益が出なかった場合などは、予定納税による出費が企業にとって大きな負担となる場合があります。このようなケースに陥った場合は仮決算による方法を採用し、企業負担を減らすことが可能です。
ただし、仮決算により割り出された中間納付額が、前期の確定法人税額の半額を上回る場合は、仮決算はできません。このルールは、たとえば決算期の前期に集中して利益を挙げることのできる会社が、半年後に本決算で還付の申告を行う際に受け取ることのできる「還付加算金」目当てで意図的に仮決算を行うケースを防ぐために設けられたといわれています。
まとめ
中間申告には、法人の状況に応じた方法があることがお分かりいただけましたでしょうか。
特に仮決算による申告を実施するか否かについては、企業の資金繰りと決算の手間を考慮した上で判断する必要があるでしょう。
なお、中間申告を実施する対象は今回解説をした法人税だけではなく、住民税や事業税などの地方税も対象になります。法人税で中間申告を行う対象となっている企業は、それに連動する形で地方税も中間申告をしなければならない点についても覚えておきましょう。
*show999 / PIXTA(ピクスタ)