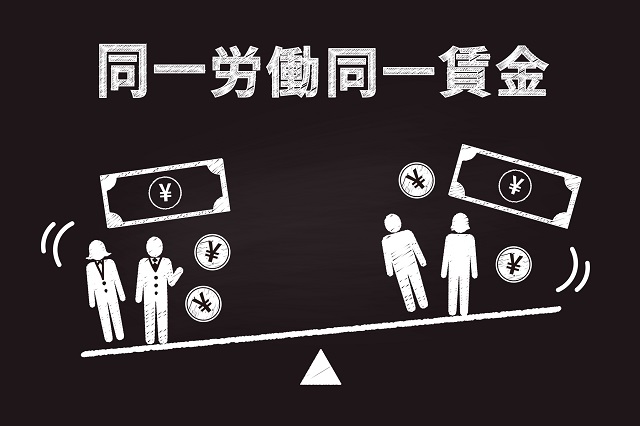【同一労働同一賃金】「待遇差の説明義務強化」と実施ポイント
2021年4月から中小企業でも同一労働同一賃金制度がスタートしますが、それに合わせ、同一労働同一賃金制度に実効性を持たせるため、パートタイム・有期雇用労働法が中小企業に対しても施行されます(大企業は2020年4月1日より)。
この法律により、短時間・有期雇用労働者に対しての説明義務が強化されましたので、今回はその点について触れていきます。
説明義務の強化って?
この説明義務の強化についてですが、短時間・有期雇用労働者が“正社員との待遇差の内容やその理由”について説明を求めた場合、会社側はそれに対して説明を行わなければならないというものです。
そのため、同一労働同一賃金制度ために賃金制度などを見直すことはもちろん、単に形を整えるだけではなく、待遇差がある場合はその差がある理由について合理的な理由を説明できるようにしておかなければなりません。
「○○手当は▲▲という理由で正社員には支給しているが、パートタイマーはこれには該当しないから支給しない」が問題かどうかは、合理的な説明ができるかどうかがポイントになります。むしろ、ここで合理的な説明ができないのであれば、手当の付け方の見直しをしなければなりません。
理由もあれば何でも良いというわけではありません。こじつけで理由だけ作っておくことがないように検討が必要です。
さて、この説明義務に関して内容を確認していきますが、(1)誰と比べての待遇差について説明するのか(2)待遇差について、何を説明すれば良いのか(3)どのように説明をすれば十分と言えるのか、の3点について説明します。
(1)誰と比べての待遇差を説明すべきか
短時間・有期雇用労働者から待遇差についての説明を求められた場合、そもそも誰との待遇差について説明をすべきかという点ですが、待遇差の説明においては、比較対象は“職務の内容等が最も近い通常の労働者”とされています。
例えば、週3日・6時間/日勤務のアルバイトの方から説明を求められた場合、正社員の中からこの勤務形態に近い従業員(例えば時短の正社員等)との待遇差について説明を行うということになります。
働き方が1通りしかないという場合は良いのですが、正社員やアルバイトという同じ区分の中でも、働き方が複数パターン(短時間勤務など)ある場合は、働き方を整理して対象となる従業員をピックアップできるようにしておきましょう。
(2)待遇差について、何を説明すべきか
待遇差の内容と理由については、下記を説明することが求められます。
・通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の待遇の決定基準の差異について(例えば賃金テーブルについて比較できるよう示す)
・通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の待遇の個別具体的内容、待遇の決定基準について
待遇の決定基準については、例えばぞれぞれの雇用形態の賃金テーブルを示し、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の賃金水準の差異が分かるよう説明する必要があります。
この点の説明は具体的な水準が把握できるように説明しなければならず「賃金は能力、経験等を考慮して総合的に決定する」といった説明では不十分とされています。その上で、待遇の個別具体的な内容(各手当がどのような判断のもと支給されているか・いないか等)の説明が必要です。
そして、待遇差の理由については、決定基準が同一である場合は、基準が同じにも関わらずなぜ支給額に差が出るのかという点について説明しなければなりません。一方、決定基準が異なる場合は、なぜ決定基準に差異を設けているのかを説明しなければなりません。
意識すべき点としては、なぜ待遇に差があるのかということに対して個別具体的に説明することです。誰のための説明義務かというとやはり労働者のためです。
一通りの説明をしたとしても、内容が抽象的であったり、会社側の裁量で総合的に判断しますといった内容で終えてしまうのは、労働者側からすると「結局、私はなぜ正社員と待遇が異なるの?」といった疑問が解決できない可能性があります。そうすると、やはり説明義務を果たしたとは言いづらいということになります。
(3)どのように説明すれば良いか
説明の仕方については、必ずこの方法で説明しなければならないという決まりはありませんが、質問をした短時間・有期雇用労働者が待遇差について理解できるように資料を示しながら口頭で説明をする方法が原則となります。
口頭に限らず、説明資料を作成・配布して確認してもらう方法もひとつの方法として有効です。パート・アルバイトの労働者が多く、1人1人説明をしていたら膨大な時間が掛かるといった場合には、先に資料を配布して確認してもらったほうが結果的に早く労働者の疑問を解決できる場合もあるでしょう。
もっとも、目指すべきところは労働者の理解ですので、「あなたには資料を渡したからもう会社は何も対応しません」では、やはり十分な対応とは言えず、資料を確認した上で、疑問点が残る労働者がいるのであれば、その解消に向けて説明の場を設けるなどの対応は必要です。
また、この説明義務は1回説明したらもう対応しなくて良いというものではなく、説明を求められた場合は都度対応しなければなりません(同じ内容を何度も質問された場合は説明義務は発生しません)。
会社にとってはしっかりと事前の準備をすることが求められる内容となっています。十分な対応が可能か、準備が整っているか、早急な確認が求められます。
*EKAKI / PIXTA(ピクスタ)