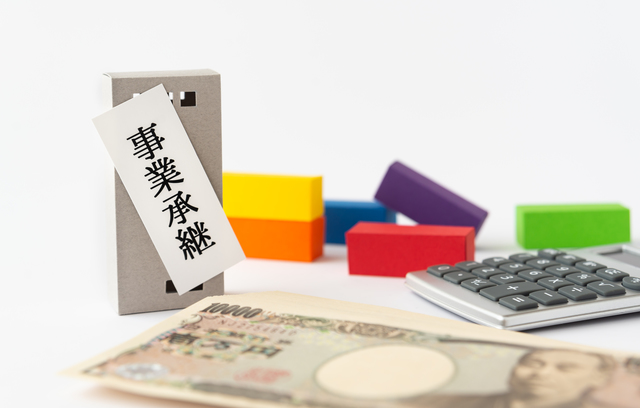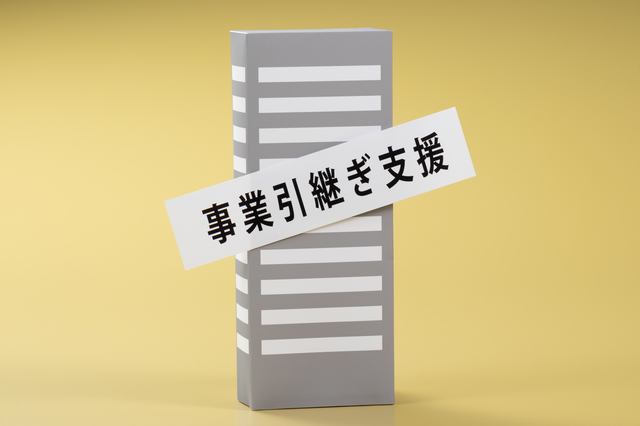まだまだ先と思ってない?事業承継を今すぐ考えるべき理由と支援制度まとめ
筆者は主な役割として地方創生を領域とした経営コンサルタントとして普段全国を巡っております。そんな日々でよくお会いするのが、中小企業の事業承継に悩む経営者の方々です。
特に、親族内での事業承継の場合、準備不足のなか、大わらわで対応するといった事態を多く拝見します。事業承継は親族内であっても、想像以上にやることが多く、時間、資金、人手がかかるものなのです。
そこで今回は、親族内の事業承継を少しでもスムーズに進められるように、さまざまな支援制度をご紹介しましょう。「事業承継はまだまだ先」と考えている企業の方もぜひご一読ください。
※最終更新:2022年3月
目次
事業承継のタイミングは予定通りに行くとは限らない
まずいちばん大事な前提として、心していただきたいのは事業承継の準備は、まさに今すぐにでも検討すべきということです。
経営者自身がある程度の年齢になったら初めて考え始めるものという認識の経営者の方が多いですが、これは大変なリスクをはらんでいます。
実際に自分が直近で引退・勇退する計画が無かったとしても、突然のアクシデントなどでいつ経営者自身が日常通りの活動ができなくなる事態が起こるかは予期できません。当たり前のことに聞こえますが、ほとんどの経営者がそのような事態に備えることができていないのです。
もちろん、まだまだ成長期に入ったばかりでそんな余裕はない企業も多いことでしょう。そのような背景も鑑みると、事業承継の準備を始めるのは「考えることが可能になった時」です。
今回は制度面についてもお役立ち情報を紹介いたしますが、最も肝心なのは経営者自身が動けなくなったときに、それぞれの業務をいかに回し続けるかという運用設計を少しずつ整備しておくことです。予期せぬアクシデントによるリスクを最小化できるよう備えることも、経営者の重要な役割であることを心得て事業計画を推進しましょう。
【もっと詳しく】意外と時間がない?「事業承継計画書」で事業承継の進め方を明確にしよう
1:相談窓口とおすすめ資料
とはいっても、どこから手を付けたら良いのか、すぐにテキパキ取り掛かることができる方は多くないと思います。そんなときに役に立つ公的な相談窓口と筆者おすすめの資料をご紹介しましょう。
相談窓口
中小企業基盤整備機構が用意している『事業承継・引き継ぎ支援センター』では、“事業承継診断”による事業承継の早期・計画的な準備ついて現在の自社の状況・課題の整理を支援してもらったり、“事業承継計画策定支援”を通じて具体的なアクションプランを作成するためのアドバイス/支援を受けることができます。
まずどこから手を付けたら良いのか、承継にあたる課題がどこにあるのか、などの俯瞰的な整理を行いたいときには便利な窓口です。
おすすめ資料とツール
また、事業承継や伴って考えうるM&Aについて、一通り検討すべき項目や一般的な課題をまとめたノウハウ集もさまざまのものがあります。目を通しておくことで全体的な作業俯瞰イメージを持つことができるでしょう。
ガイドライン・マニュアル
・事業承継ガイドライン
・事業承継マニュアル
・中小M&Aガイドライン
・中小M&Aハンドブック
チェックシート・支援ツール
・事業承継診断チェックシート
現状の課題を簡単に識別できます。
・ローカルベンチマーク
企業の経営状態の把握、いわゆる“企業の健康診断”を行うツールで、経済産業省のホームページで提供されています。診断の内容が各種補助金の申請にも活用できますので金融機関や支援機関と相談する際にはこちらを活用して現状把握することも現状把握と後次の対策にも役立つでしょう。
・経営デザインシート
企業の現状把握と将来構想を策定するための考え方を提供するツールです。なかなか長期経営計画を考えるのもどこから手を付けてよいか戸惑ってしまうことも少なくありません。そんなときのガイド役として活用できます。実際の策定計画も事例に入っていますのでそちらを参照しながら自社の構想を練ることができます。
2:資金面での支援制度
具体的な計画ができたとしても、既存の体制・運営を刷新していかねば承継後の事業継続に課題が残ってしまう場合があります。かといってそこには本業を継続することとは別のノウハウ・工数および場合によっては資金が必要なことがあります。
事業承継・引継ぎ補助金
『事業承継・引継ぎ補助金』は、事業再編、事業統合を含めて、事業承継時に必要となる経営革新や経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助してくれます。実例では、販路確保やマーケティング策の拡充など事業全体を見渡して事業承継をするにあたって組織・業務・戦略など広範囲に必要な変革を対象として支援を受けられます。これまで築き上げてきた経営資源を、承継時に新しい世代に引き継ぐために必要な『経営革新』全般を成し遂げることを企図する際には大変心強い支援です。
【もっと詳しく】承継後の取り組みまで!幅広く活用できる「事業継承・引継ぎ補助金」とは?
なお、『事業承継・引継ぎ補助金』に伴って、事業再編/統合も検討する場合、中小企業庁ではM&Aを支援する機関の登録制度も整えています。上記補助金制度を活用する際は合わせ支援機関活用も検討しましょう。 詳しくはこちらから確認してください。
経営承継円滑化法による金融支援
経営承継円滑化法による各種支援もあります。
金融支援
同法の金融支援では、通常の信用保証枠にかなりの追加保証枠のある融資・保証制度や、現経営者の個人保証を外すための借り換え支援制度などが用意されています。
遺留分に関する民法の特例
同法で規定された『遺留分に関する民法の特例』では、相続における遺留分についても事業承継者に優先的に相続させることも可能です。この場合は相続人の合意を得た上で、家庭裁判所および中小企業庁への届出をへて許可を受ける必要があります。
所在不明株主に関する会社法の特例
資金的な援助ではありませんが、都道府県の認定を得ることで、同法の『所在不明株主に関する会社法の特例』の適用を受けることができます。所在が不明な株主の承認が得られないために手続きが進められない場合、救済措置を受けることができます。
ファンドから投資
少しハードルが高い選択肢とはなりますが、事業自体に今後の成長性や市場の拡大性などの期待できる魅力がある場合にはファンド支援を受けることも可能です。
中小企業基盤整備機構の支援を受けながら検討することも可能なので、承継を期に新しい挑戦も視野にいれる場合はファンドの活用も考えてみてはいかがでしょうか。詳しくは以下リンク先よりご確認ください。
3:税制措置
忘れずに活用したいのは、非上場の株式等の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする(または猶予)特例措置です。
2023年3月までに特例事業承継計画を提出し、2027年までに事業承継を実施する必要があります。相続の負担は相当に重いものですので、親族内承継を検討する中小企業にとっては逃さず活用を検討すべき制度です。
申請マニュアルは、中小企業庁のサイトにそれぞれ法人・個人事業者向けに下記のページで整理されています。
・法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定について
・個人版事業承継税制の前提となる認定について
M&Aに伴って経営力向上計画について所轄省庁から認定を受けるとさまざまな減税支援も受けられます。認定の受け方や支援の範囲については以下リンク先より確認しましょう。
同様にM&A時に不動産の登記移転や免許登録の追加にかかる税の軽減措置もありますので、知っておくとよいでしょう。
4:事業承継者の育成支援
ここまでは比較的緊急な承継作業の支援についてご紹介してきました。しかし、事業承継には、長期的な視野に乗って着々と準備を進めておくことこそも重要です。
そして一番の懸案事項になる承継者の育成を支援するための制度もあります。早めに準備を開始しておくことが、当人の心構えの面でも将来の不安やリスクを低減する手当となります。
・中小企業大学校(中小企業基盤整備機構)
・アトツギ甲子園(中小企業庁)
【こちらの記事も】なぜ後継者が育たないのか?後継者不足に陥る会社の特徴3つ
事業承継は今から始めよう
事業承継については国も自治体も大変手厚く支援体制を整えています。この記事を読んでいる方は、事業承継について関心をお持ちと推察します。であれば、着手するにあたって早すぎるということは決してありません。
逆に経営力をアップさせたり、長期的経営戦略をブラッシュアップさせる好機にする機会になるかもしれません。まずは自分ひとりで悩まずに活用できる支援は積極的に支援さえることをおすすめします。
【あなたにおすすめ】
後継者がいないから会社をたたみたい…ちょっと待って!廃業する前に検討すべきこと3つ
事業承継問題の解決策として注目! 中小企業のM&Aメリット・デメリット【事例付き】
【参考】
『中小機構』 / 中小企業基盤整備機構
『事業承継・引継ぎ補助金』 / 事業承継・引継ぎ補助金事務局
『事業承継・引き継ぎ支援センター』 / 中小企業庁
『ローカルベンチマーク』 / 経済産業省
* CORA、artswai、mits、amadank / PIXTA(ピクスタ)