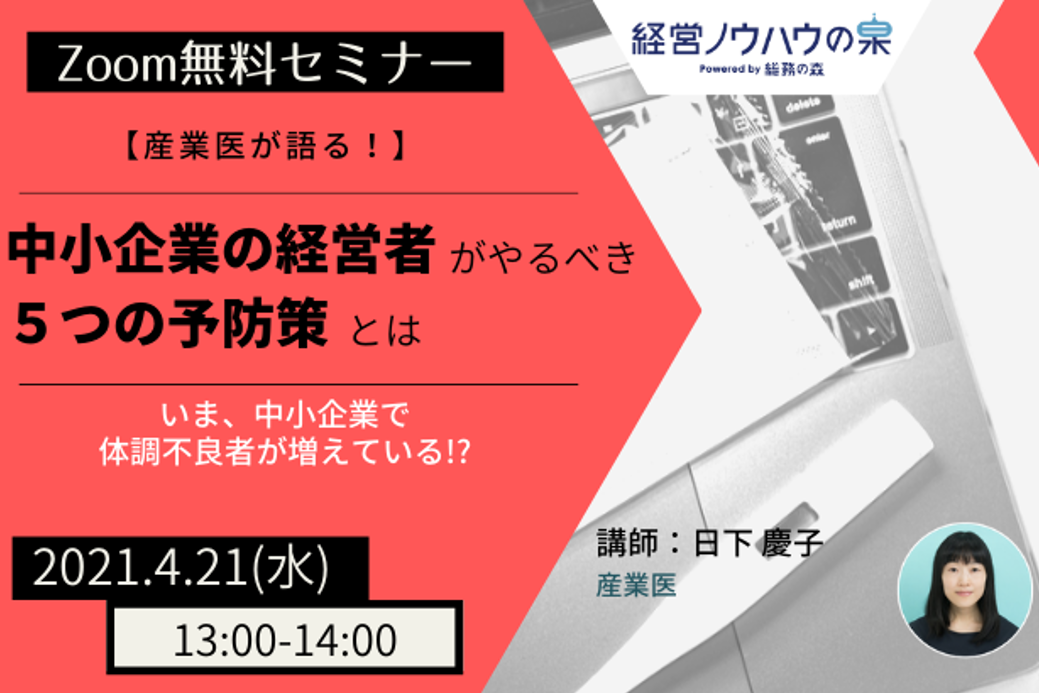連休明けのメンタル不調はなぜ起こる?4つの要因と対策【5月病】
4月から新年度が始まって1ヶ月経った5月ごろに、「仕事に集中できない」「何だか体が重い」などの悩みを抱える人は多いです。昔は5月病とも言われていました。新入社員に起こりがちなメンタル不調の1つだと思われがちですが、誰しもなりうる可能性があります。
そこで今回は、連休明けのメンタル不調のサインと対策法をご紹介します。
目次
5月の連休明けのメンタル不調とは?
そもそもメンタル不調とは以下のような定義づけがされています。(※参考:厚生労働省「職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」)
「精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むもの」(引用:職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~ / 厚生労働省)
連休明けのメンタル不調を訴える人は全体の約8割いる*1と言われています。理由は「連休後の疲れ」「早起き」「溜まった仕事」の3つが挙がっています。連休中とのギャップが生じてストレスを抱えやすいようです。
特に朝起きた瞬間に1番辛いと感じる人が多く、疲労が溜まった状態で仕事を始める人の割合が多いことがわかります。中には連休明けに仮病を使って休んだり、集中力が低下して仕事でミスを繰り返したりするケースもあります。それだけ社員の生産性が下がっていることのあらわれでしょう。
新入社員にとって5月の連休は入社後初めての大型連休ということもあり、新しい環境に馴染めなかったり人間関係でうまくいかなかったりして、仕事への意欲が減少することがあります。
企業からすれば優秀な人材を失うことになりかねないため、連休後の社員へのサポートはしっかりと行う必要があるでしょう。
なぜメンタル不調になってしまうのか
1:生活リズムが乱れるから
普段は仕事の関係で朝早く起きていても、連休に入ると夜更かしをしたり朝遅くに起きたりする人も多いです。連休中くらいはゆっくりしようと思って朝寝坊などを繰り返していると、生活リズムが乱れやすくなります。起きる時間と寝る時間があまりにも異なると、体内時計が崩れて時差ぼけのような状態になってしまうからです。
この状態は眠気、食欲不振、集中力低下などを招くと言われています。それだけでなく日中に突然眠気が襲ってきたり、夜中に目が冴えて眠れなくなったりするケースもあります。
2:連休中の疲労が溜まっているから
連休中にゆっくりする人もいれば、予定を入れすぎてかえって疲れてしまう人もいます。例えば帰省したり旅行したりなど普段と違う行動をとると、それがストレスとなって疲労が溜まりやすくなります。軽い運動やレジャーは良い息抜きになります。
ですが、休憩なしで運動をしすぎたり体力を消耗するようなレジャーをしたりすると、疲労回復までに時間がかかってしまいます。結果的に連休が明けても疲れがとれないという状況に陥りやすくなります。
3:気候などの変化が激しいから
5月ごろは寒暖差も激しく、風邪や冷え性などの体調不良を起こしやすいです。また、気圧変化などの影響もあり、身体の調節機能がうまく働くなることもあります。人によっては自律神経失調症になるケースもあり、頭痛やめまいや倦怠感などの不調を起こすこともあるようです。
4:精神的ストレスを抱えているから
連休中は趣味を楽しんだりリラックスしたりなど、自分の好きなように時間を使えます。ですが連休明けの前日の夜になると「明日からまた仕事が始まる」「朝早く起きなければならない」というネガティブな思考が強くなります。「連休前の元の生活スタイルに戻さないといけない」というストレスが、メンタル不調の原因になることもあるようです。
社員のメンタル不調のサイン
社員のメンタル不調には十分気をつける必要があります。働く日々に慣れていく中で憂鬱さが解消されていくことの多い“5月病”とは異なり、メンタル不調は適切な対策を取らないと時間が経っても改善されることはありません。
メンタル不調の症状は以下の通りです。
・不安感に襲われる
・仕事で些細なミスが増える
・身だしなみに気を遣わなくなる
・憂うつな気分が続く
・やる気が起きない
・頭痛や吐き気がする
・めまいや倦怠感がある
・集中力が低下する
大きく分けると、「気持ち」「身体」「仕事への態度」の3つのカテゴリーで変化が見られるようです。
メンタル不調になった時の対策
ここからは、社員のメンタル不調を回復するための対策について解説します。連休明けの離職を防止する方法についても述べていますので、ぜひ参考にしてください。
1:仕事量を調整する
連休明けの社員の仕事量を調整しましょう。そうすることで不安や焦りを軽減することができます。連休明けは生活リズムの乱れから集中力が低下していたり、仕事が始まるというプレッシャーから憂うつな気分のまま働いている社員もいます。
あまり社員を追い込まず、連休明け初日は業務量を抑えてあげる配慮も必要でしょう。社員それぞれの仕事量を調整するためにも、事前に作業計画を立てておくことも重要です。
2:目標設定をする
連休が明けてから少しずつやる気を取り戻してもらうために、社員一人ひとりに目標設定をしてもらいましょう。目標設定をした上で小さな成功体験を積んでもらうことが目的です。なぜかというと、メンタル不調を抱える社員は自分に自信がなく、不安や焦りを増幅させやすい傾向にあるからです。
ハードルの高い目標を設定してそれが成し遂げられず落ち込んでしまい、仕事へのモチベーションを失ってしまうこともあります。具体的にどんな目標を立てたのか社員と共有したり、仕事の様子を教えてもらったりしましょう。
3:メンター制度を取り入れる
メンター制度を活用するのも1つ方法です。メンター(育成者)がメンティ(社員)の心の支えとなって、面倒を見て励ましたり、寄り添って話を聞いたりします。具体的にはキャリア形成やスキルアップ、人間関係の悩みなどの相談を受けながらアドバイスをして社員の成長を促していくものです。
メンター制度を取り入れることによって社員のモチベーションアップにもつながり、メンタル不調からの回復を早めてくれる効果も期待できます。
4:社内ルールへの理解を深める
1on1面談や研修などを通して、社内ルールへの理解を深めてもらいましょう。会社のミッションや経営方針、経営理念などを改めて伝えることも大切です。今後の方向性について話すことは、その社員が会社で働くことの意味を考えるきっかけにもなります。
ここがきちんと理解できているほど「もっと会社に貢献したい」「自分はこういう仕事をやりたい」という意欲も湧いてきて、目標設定もできるようになるでしょう。
また、メンタル不調になる前から、社員の心の健康を守るために上記のことに取り組んでいけるとよいですね。
まとめ
今回は連休明けのメンタル不調のサインと改善法についてお伝えしました。しっかりと対策を打たないと、連休明けに退職や転職を考える社員が出てくる可能性もあります。離職率を下げるためにも、本記事の内容を参考にして職場環境の改善を行ってみてはいかがでしょうか。
【参考】*1「連休明けの仕事」に関するアンケート調査
*Graphs、そうまる / PIXTA(ピクスタ)