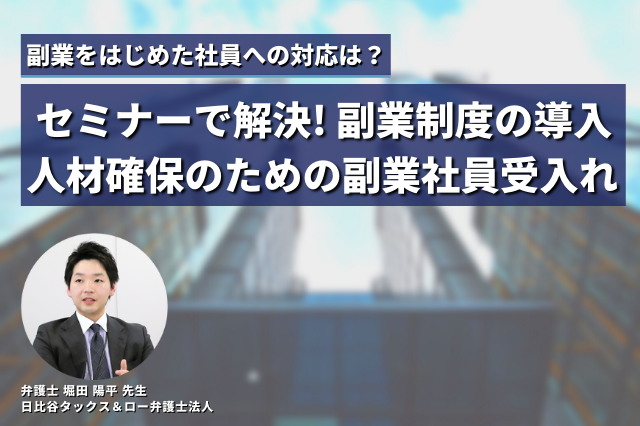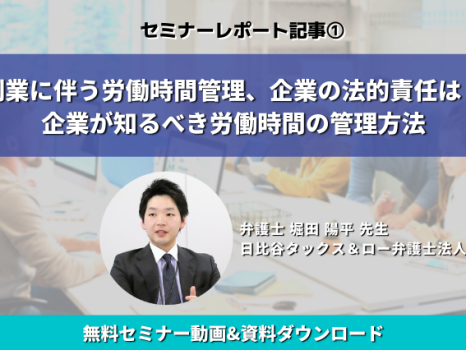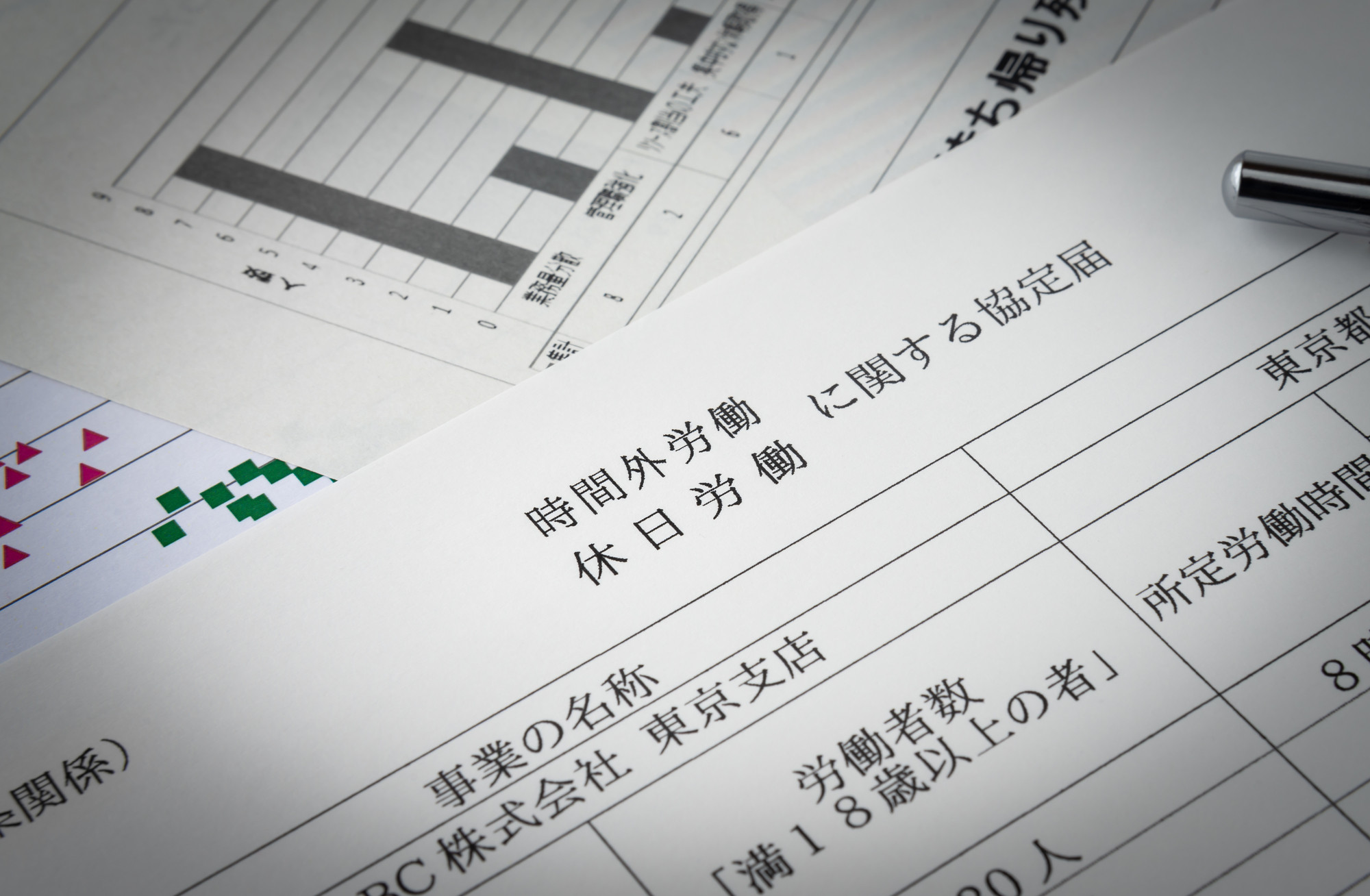
罰則は?労働基準監督署の調査・指導・是正勧告の概要と気を付けるべきこと
一昨年と昨年は、コロナ禍ということもあり、各官公庁の調査も自粛されていたと言われています。コロナ感染症が収束に向け見込みが立てば、各調査が増えるとの予測も。
そこで今回は、労働基準監督署に関する調査・指導・是正勧告への対応とその罰則についてご紹介いたします。
目次
突然、労働基準監督官が来たら…
税務調査官や警察官や検察官は、ドラマでもよく観ることがあるので馴染みがある人も多いと思いますが、労働基準監督官は、馴染みがない、知らないという人も多いのではないでしょうか。
労働基準監督官の仕事の権限は、労働基準法令を施行することにあります。通常は、事業所を査察し、労務や労働安全衛生に関する指導等を行うことがメインの業務です。監督官の行政指導に従わず、繰り返し法令違反を犯した場合や、死亡労働災害を発生させた場合などは、刑事訴訟法による特別司法警察職員の職務遂行に切り替えられることがあります。
査察の場合に、帳簿など見る権限も与えられています。もし、これを拒んで査察を拒否したり、邪魔したり逃げたり、わざと提出しなかったりした場合、罰金30万円の定めもあります(労働基準法第120条第4号)。その他の罰則については、後述いたします。労働基準監督官の行う業務には以下の4種類があります。
①定期監督・・・その年度の監督計画に従って法令全般にわたり行う
②申告監督・・・労働者からの法令違反の申告があった場合に行う
③災害時監督・・・一定以上の労働災害が発生した場合に実施する臨検監査
④再監督・・・定期監督、申告監督、災害時監督の結果、発見された違反が是正されたかどうか確認するために行う
監督官は、予告なしに監督活動を行い、違反があった場合には是正勧告、指導事項があった場合には、指導票を出します。これは、行政指導です。
突然、労働基準監督官が来て対応に困った企業の話を聞くことがありますが、労働基準監督官には、管轄の事業所を訪問監督する権限が国から与えられていると言えます。書類の準備がどうしてもできない場合や担当者が不在の場合は、その旨を伝え、対応できる日をできるだけ早めに伝えて対応するようにしましょう。
罰則は4段階ある
労働基準法に違反した場合、違反事項によっては、懲役や罰金などの刑罰を科される可能性があります。罰則ごとに代表的な労働基準法違反をご紹介します(※すべてではなく代表例のみ)。
1:1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
違反行為:「強制労働の禁止」
労働基準法で最も重い罰則となります。
2:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反行為:「労働者からの中間搾取」、「最低年齢未満(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの)児童を労働させる行為」など
3:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる違反行為
違反行為:「均等待遇」、「男女同一賃金の原則」、「解雇制限期間の解雇」、「解雇予告義務違反」、「時間外労働」、「深夜労働」、「休日労働についての割増賃金の不払い」、「労働者に違法な時間外労働をさせる行為」など
時間外労働に関しては、上限規制があります。36協定で定めた範囲を超えて労働させることや法令で定める絶対的上限時間を超えて労働させることは、違反行為になります。
4:30万円以下の罰金となる違反行為
違反行為:「労働条件を明示しない行為」、「就業規則の作成、届出義務違反」、「休業手当の不支給」など
どのようなことに気を付ければいいのか
労働基準監督署は実行部隊として全国に321署あり、各都道府県労働局の上には、厚生労働省(本局)があります。ILO(国際労働機関)81号条約および労働基準法第97条により、労働基準監督機関について、中央、地方を一貫して国の直轄機関であることを定めています。その他、労働局・ハローワークは、雇用関係助成金を利用する事業主向けに不正受給防止の調査を行っていることを公表しています。
今回は「誰もが安心して働き活躍できる元気な大阪」をスローガンに、働き方改革を中心とした行政推進をおこなっている大阪労働局を例に挙げ、行政運営方針から調査に関連するポイントを紹介します。(各地の労働局は、厚生労働省の策定する地方労働行政運営方針を踏まえ、各局の事情に即した重点課題を盛り込んだ行政運営を図ります)
(1)コロナ過においても長時間労働等の過重労働が生じている事業所への集中的対応
※月80時間超の時間外労働行う事業所へは過重労働撲滅対策班(通称カトク)による査察対象とされている
(2)建設業における「命綱GO運動(いのちつなごう運動)」展開
※「命綱GO運動」では、改正された政法令に基づき要求性能墜落制止用器具の適正な使用の徹底とフック付け替え時の墜落を防止する二丁掛け墜落防止用器具の仕様促進等を進めている
(3)製造業での「はさまれ、巻き込まれ災害」禁止のため、リスクアセスメント導入率向上と残留リスク低減措置の実施を推進
(4)1月から3月期の死亡災害を減少させることが、年間の死亡災害発生件数の抑制に効果的なことから「冬季死亡災害防止強化月間」を設定し、墜落・転落・交通労働災害の防止を図る
(5)大阪府と「いわゆるブラック企業の撲滅に向けた共同宣言」について各種セミナーの実施とキャンペーン期間における集中取り組み
※2018年3月27日に大阪労働局が大阪府との間で、労働者を使い捨てにする企業は許さないという趣旨に基づき実施した共同宣言
(6)最低賃金の履行のため、監督指導等の実施、行政機関等との連携
(7)ハラスメント防止対策を事業主への是正指導、周知徹底を図る
過労自殺など精神疾患認定調査のポイント
過労死等防止対策推進法第2条における定義では“過労死等”とは「業務における過重な負荷における脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神疾患」が該当するとされています。
また、厚生労働省では過労死ラインといわれる長時間労働の危険性を示す基準を設定しています。発症前1か月間に概ね100時間を超える時間外労働が認められる場合、発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たり概ね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性は強いと評価できるとしています。
過労自殺事件については、電通事件の損害賠償請求事件の最高裁判決(2000年年3月24日)の影響が大きいと考えます。この事件は、労災申請しない段階で遺族が会社を相手として安全配慮義務又は注意義務違反が会社にあるとした裁判です。これ以降、精神障害の労災請求件数が大幅に増え、審査の迅速化を図るため、2001年12月26日に新たな認定基準が設けられました。
認定基準のポイント
①わかりやすい心理的負荷評価表*
② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からすべての行為を対象として心理的負荷を評価
③ すべての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい場合のみに限定
過労自殺等精神障害の認定調査では、長時間労働があったことを勘案して業務上か否かを判断されます。人の内面を明らかにしていく作業ですので“いつ、だれが、どうような状況で、何について、どのように言ったか”そして、それに対して、被災者は“どのように反応して、どのような表情で、何と言ったか”などを細やかに聴き取り認定していきます。
まとめ
労働基準監督署の指導に、心から納得している経営者はいないと思います。これは、税務調査の指導なども同じと考えます。経営者は、いつも激しい市場競争にもまれて、戦い続けているからです。その競争と逆行するような行政指導に対して、どうしても反発する感情は理解できます。
「同業の他の会社は、どうなっているの」と口に出てしまうのは当然です。しかし「原因はすべて我にあり」と考えて、調査や是正勧告を受けた場合は、根本的に改善することをおすすめいたします。
労働基準法の出発点は、憲法から成立しています。憲法第25条は「すべての国民は、健康で文化な最低限度の生活を営む権利を有する」、憲法第27条は「賃金、就業時間、休息その他の勤労上限に関する基準は、法律でこれを定める」と定め、これらを具現化しているのが労働基準法であり、労働関連法令です。
労働基準法第1条では「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と定められています。人たるに値する待遇を会社として行っているのか、そこからスタートして再考してみることも良いかもしれません。その“人たる基準”が、最低賃金、時間外規制、安全衛生に具現化されています。
“人たる基準”が幅広く、高度化しているのは事実です。労働基準法設立の戦後以降、裁判結果は労働者有利に積み重なってきていますので、労務管理制度も高度化する必要があります。
* CORA、soraneko、starmix / PIXTA(ピクスタ)