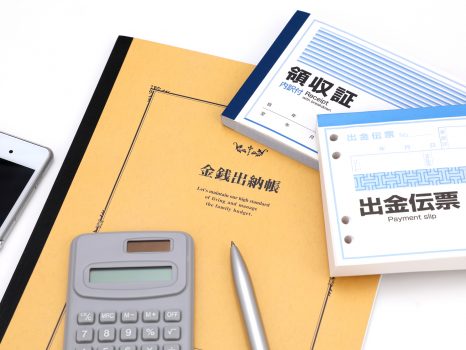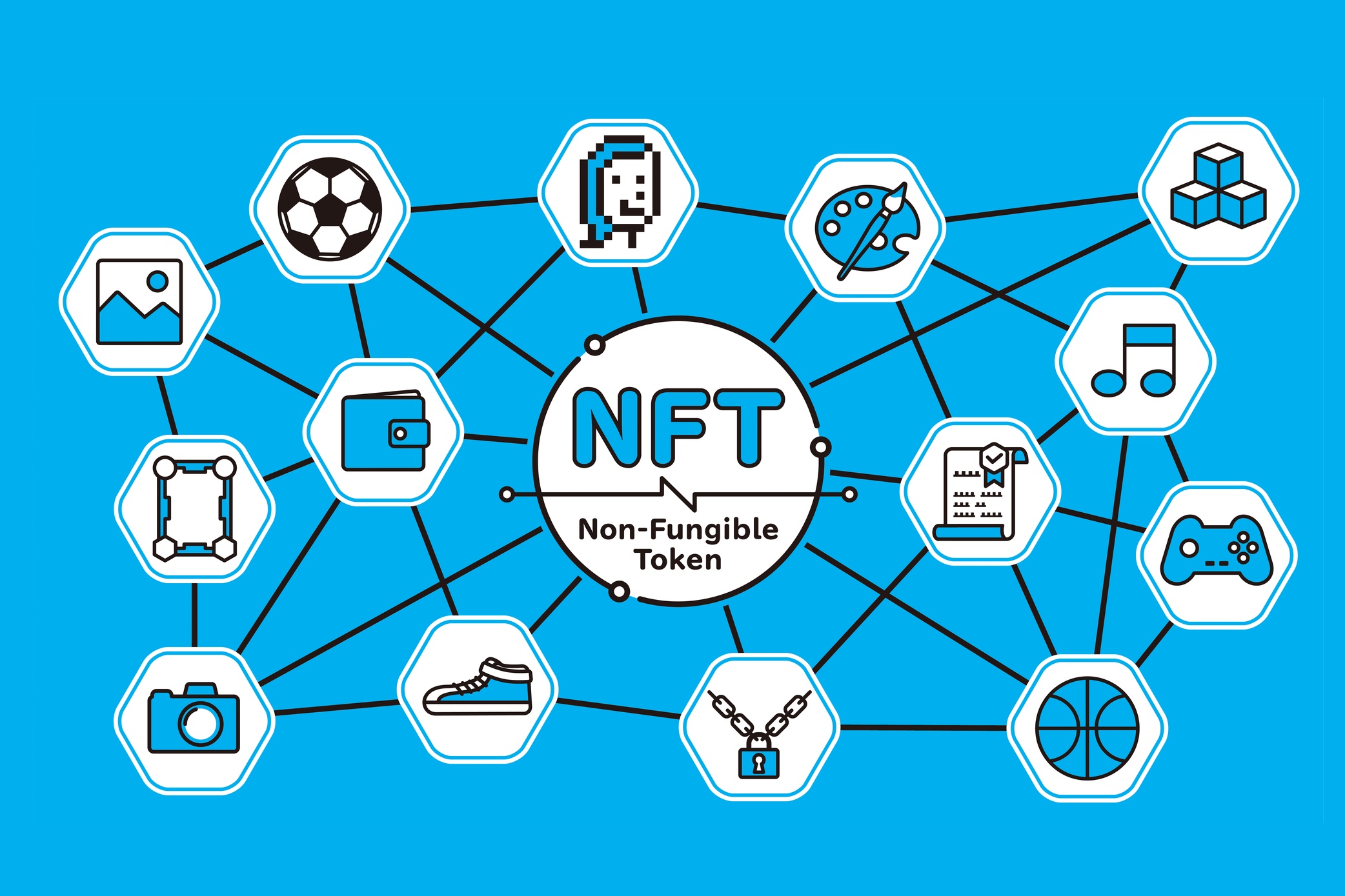
Web3.0とは?よく聞くNFTやメタバースとの関係も【わかりやすく解説】
Web3.0(ウェブスリー)という言葉がビジネス界隈を賑わせています。しかし、それが何なのか、なぜ注目されているのか、まだおぼろげにしか理解できていない人も多いのではないでしょうか。Web3.0は次世代のインターネットと言われており、今後発展していくと予想されている分野です。本記事ではWeb3.0の概要をわかりやすく解説します。
目次
Web3.0とは?Webの歴史を踏まえて解説
Web3.0の意味
Web3.0とはバズワードの一種です。バズワードとは正式な専門用語ではないが業界などで流行している言葉を言います。
つまりWeb3.0という商品や技術があるわけではなく、定義も明確には定まっていません。ただ、おおむね以下のような概念を指すようです。
- 中央集権的な管理体制から脱却したWeb
- 特定の企業の独占を解消したWeb
- データの所有権の分散と共有が進んだWeb
これだけだと抽象的で、何を意味しているのかいまいちわからないかもしれません。正確に理解するにはWebの歴史から理解する必要があります。
Webの歴史
Web1.0(1995年〜2005年)
Web1.0は今から20〜30年前のWebを指します。このころのWebは今のように大勢の人々が自由闊達にコミュニケーションを取るような場所ではなく、少数の発信者が多数の閲覧者に一方向に情報を発信するだけの場所でした。
多くのサイトはHTMLのみで書かれた静的なページで構成され、現在のように動的なリッチコンテンツはなかったのです。
また、現在のようにホームページの作成がプラットフォーム化されておらず、Web開発の技術を持った人でなければ自分のホームページを作れませんでした。必然的に発信できるのはごく少数の人たちのみという状態でした。
Web2.0(2005年〜2018年)
Web1.0から進化したWeb2.0は現代の皆さんが良く知っているWebの姿だと考えて良いでしょう。携帯電話やスマートフォンの出現により、IT技術に詳しくない人でも簡単にインターネットが利用できるようになりました。
Web1.0との最も大きな違いは双方向性です。ブログサービスやSNS、動画共有プラットフォームなどが出現し、それまでは開発技術を持った一部の人だけの特権だった情報発信が誰でもできるようになりました。
メッセージアプリやチャットなどのコミュニケーションの手段も発達し、インターネットが社会のインフラとなったのもWeb2.0からです。
Web3.0(2018年〜現在)
Web2.0の進化形であるWeb3.0は双方向性をさらに発展させた“分散と共有”のWebと言えるでしょう。
Web2.0が社会のインフラとなり、生活に無くてはならないツールとなったのは先述したとおりです。しかし、それはGAFAM*などのプラットフォーマーの巨大化と一極支配という弊害も生みました。
個人情報やデータは完全にこれらのプラットフォーマーに支配され、アメリカ企業でありながら国境を越えて全世界の人々の暮らしに強い影響力を持つ存在となっています。
Web3.0はそのような巨大プラットフォーマーに集中してしまったインターネットの権力を個人へと分散し、共有しようとする概念といえるでしょう。
* 世界に影響力をもつといわれるアメリカのIT企業5社Google、Amazon、Facebook(現Meta)、Apple、Microsoftの頭文字をとった呼び名
Web3.0を実現する技術「ブロックチェーン」
Web3.0が“分散と共有”を目指した概念であることは上で説明した通りです。ではそれを実現するにはどのような技術があるのでしょうか?
Web3.0の中核となる技術は「ブロックチェーン」と呼ばれています。これは簡単にいうと「インターネット上のやり取りの履歴を全員で分散して管理する仕組み」です。
この仕組みは以下の2つの技術から構成されます。
- 悪意のあるユーザーからのデータ改ざんは暗号技術によって防ぎます。ある履歴データをハッシュ値と呼ばれる不規則な文字列に変換して次の履歴データと一緒に記録します。これにより、特定の履歴データを改ざんすると前後の履歴データとの整合性が取れなくなるため、改ざんが検出できるという仕組みです。
- P2Pと呼ばれる技術により、特定の中央集権的な管理者を介在させずにユーザー同士のフラットなネットワークを作ります。そして履歴データはネットワークの参加者全員で保持するようにします。これにより一部の参加者が保有するデータが破壊されても別の参加者が保有するデータでリカバーができ、データの同一性が保持されます。
Web2.0では中央集権的な構造のインターネットでしたが、それはユーザー同士のやり取りやデータを特定の事業者(GAFAMなど)が管理していたからです。ブロックチェーン技術を使えば、特定の管理者が存在しない管理体制が構築できます。
Web3.0に関する日本政府の対応
政府・自民党はWeb3.0を将来の日本の成長戦略の柱と位置づけています。自民党のNFT政策検討PT(座長・平将明衆院議員)は「Web3.0時代を見据えた、新たなデジタル戦略に関する提言(案)」を取りまとめました。
Web3.0を前提とした社会基盤やルール作りを進めていくそうです。今後はWeb3.0の普及を推進する政策がどんどん出てくると思われます。
Web3.0でできること・具体事例
Web3.0でできること
NFT
NFTとは日本語では「非代替性トークン」と呼ばれます。非代替性とは「替えが効かない」という意味です。
普通のデジタルコンテンツはただの情報なので、容易にコピーできます。そしてコピーしたコンテンツとオリジナルのコンテンツは全く同一であり、どちらがオリジナルか区別はつきません。
一方で、NFTの場合は異なります。NFTはブロックチェーン技術を用いて、オリジナルのコンテンツがどれかを証明します。よって、世界で1つしかないデジタルコンテンツが実現できるのです。
ただし、ここでいう所有者とはあくまでもトークンの所有者であり、トークンに紐付けられたコンテンツの所有権や著作権を証明するものではない点に注意が必要です。また、NFTはあくまでもコンテンツに紐付けられたトークンによって所有者を識別できる技術であって、コンテンツのコピー自体は可能です。さらに日本の法律ではデータの所有権や売買はまだ法的に規定されていない点にも留意する必要があります。
NFTを利用すれば以下のようなメリットがあります。
- デジタルコンテンツの希少性を担保する
- テジタルコンテンツの所有者を証明する
- デジタルコンテンツが売買できる
メタバース
メタバースはVRやAR技術を用いてインターネット上に作られた3Dのバーチャル空間です。
3Dのバーチャル空間は2000年代初頭から主にゲームの分野で実現されていたので、それらとメタバースの何が異なるのかいまいちよくわからない方も多いのではないでしょうか。
実はメタバースもバズワードに近い言葉であり、厳密な定義があるわけではありません。その定義は識者や論者によって微妙に異なっています。
しかし、メタバースとゲームは主に以下の点において異なるようです。
- アバターが自分自身である(架空のキャラクターではない)
- 現実の経済と同期されている
- ユーザーがコンテンツを作成可能である
2番目の要素はECの例で考えるとわかりやすいかもしれません。例えば、メタバース空間内にデパートがあり、そこで購入した服が後日「現実の自宅」に届く、といったビジネスモデルが考えられます。つまりメタバースは架空の異世界ではなく、あくまでも現実の拡張なのです。
【こちらの記事も】本社機能をVR化してみた結果…【ロゼッタ・五石順一さんインタビュー】
Web3.0の具体事例
REV WORLDS(レヴ ワールズ)
上記のECのビジネスモデルを実現しているのが、伊勢丹の『REV WORLDS』です。これはスマホで利用できるメタバースで、バーチャルな新宿伊勢丹を再現したサービスです。陳列されている商品は現実の商品であり、選択すると伊勢丹のECサイトに遷移し、そのまま購入もできます。
メタバースをECに利用すれば、従来のECでは弱かった体験価値を補えるのではないかと注目されています。
NFT鳴門美術館

出典: 一般財団法人NFT鳴門美術館
一般財団法人鳴門ガレの森美術館は、2021年8月に「一般財団法人NFT鳴門美術館」と改名しました。その後は美術品のNFT化と流通を推進しています。
NFTはコンテンツの希少性を担保したままデジタル化できるため、デジタルアート作品の資産価値を守れます。NFTアートの発行、流通に特化した美術館は日本で初だそうです。
まとめ:Web3.0の時代はもう始まっている!
Web3.0はインターネットの普及、スマートフォンの普及と同じぐらいの社会的インパクトを与えるかもしれません。少なくとも今あるインターネットの体制は少しずつ変わっていき、新しいWebの概念が発展していくでしょう。その過程でたくさんのビジネスチャンスも生まれます。今後のWeb3.0の動向に要注目です。
【参考】
日本初のNFT美術館「NFT鳴門美術館」がスタート/一般財団法人NFT鳴門美術館
デジタル事業 -オンラインサービスの紹介-/三越伊勢丹ホールディングス
「Web3.0」をわが国の成長戦略の柱に NFT政策検討PTが提言(案)を取りまとめ/自由民主党
*タカハシ、barks、enjoysphoto / PIXTA(ピクスタ)