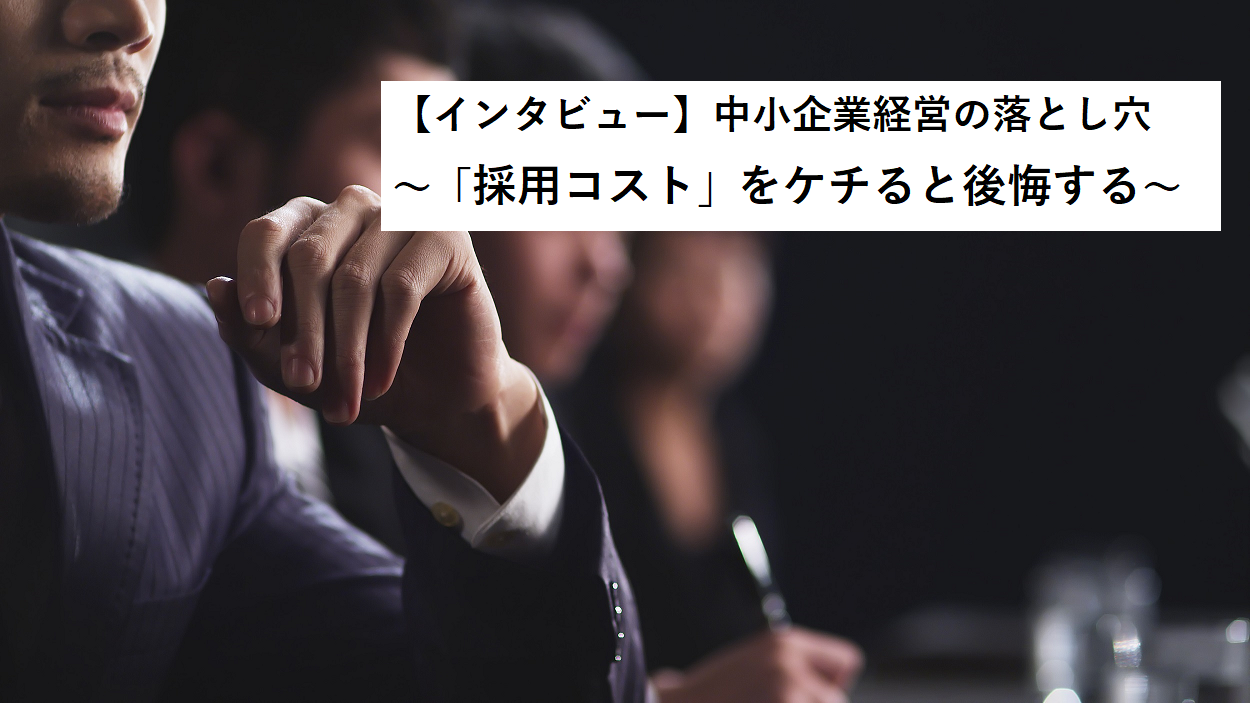中小企業の経営者は応募者のここを見るべし!中途採用で「即戦力人材」を見抜く方法
~老舗メーカーのとあるオーナー社長のつぶやき~
「社長。最近中途入社したAさん、プログラムのバグが直せないって言うんですよ。」
社長はAさんの職歴書で、大手IT企業でエンジニアをしていた経歴を見て採用を決めた。
うちの会社の軽微なバグくらいすぐに直せるようなことを面接で言っていたはずだが……。別の社員が困った表情でまた社長に声をかける。
「社長、Aさんがうちのやり方が古いって言って、そっぽを向いちゃったんですけど。」
社長は“即戦力人材”としてAさんを採用したつもりだ。
すぐに第一線で戦力になるはずだったのに、いったい採用で何を見逃してしまったのだろう?と社長は首をかしげる。
中途採用を実施する中小企業の多くは、即戦力を期待する傾向があります。ところが、たとえ前職での実績やスキルが十分であるようにみえても、新しい職場環境ですぐに活躍できないケースがあるのです。
今回は即戦力となる人材を見抜く、中途採用のポイントについてご紹介します。
中途採用で即戦力が求められる理由
中小企業ではほとんどの人材充足を中途採用で行っています。
厚生労働省の調べによると、従業員数30名以下の企業では中途採用比率が90%程度で、30~99人の規模でも約85%と大多数を占めています。
しかし2019年下半期に中途採用で「必要な人員を確保できなかった」企業は約41%にも上り、採用の難しさを物語っています。
従業員数が少ない企業ほど、一人の採用にかかる重要度は高まります。
少数精鋭で組織運営をしている中小企業においては、新しい戦力は事業成長にとってパワフルなエンジンとなります。
しかし見方を変えると、資金や体力が潤沢でない中小企業が採用ミスをしてしまう負のパワーも大きいといえるのです。
人材アセスメントの世界では「積極的誤り」と「消極的誤り」という概念があります。
積極的誤りとは、本来自社にマッチしない人材を採用してしまう誤りで、コストやパワーを無駄にしてしまいます。一方消極的誤りとは、本来採用すべき人材を見過ごす誤りで、享受できたはずの事業成果などを逃してしまいます。
いずれの採用の誤りも中小企業にとっては致命的となるため、いかに採用段階で「本当に即戦力になるのか?」を見極める重要性が求められるのです。
どのような人材が「即戦力」になるのか?
ひとことで“即戦力人材”といっても、厳密には各社の状況に応じて人材要件を言語化することが必要です。
しかし、中途採用にパワーやコストが注げない状況も考慮し、今回は“一般的に”即戦力になりやすい人材の特徴に絞ってお伝えします。
コダワリを捨てられる人材
言い換えれば“適応力が高い“柔軟性が高い”ような人材です。
中途採用者は前職での経験があるため、仕事の進め方から周囲とのコミュニケーションの取り方に至るまで、自社と異なる企業文化を“当たり前”としている人物です。
転職者が往々にして最初にハードルになるのが、カルチャーギャップです。
いくらスキルが高い人材でも、仕事を進めるカルチャーの違いに戸惑い、力を発揮する以前にやる気を失うケースもあります。
前職のやり方に固執せず、新しいやり方を受け入れる思考がある人は、すぐに会社に馴染むでしょう。
もちろん適応力が高い人材を求めたいところですが、そこまで柔軟でしなやかさがある人材はなかなか稀有です。
まずは「前のやり方とは違うけど、こういう方法もあるんだ」と、コダワリを捨てられそうな人に着目すると、候補人材が増えると思います。
例えば、面接でその人が仕事において譲れないポイントをいくつか聞いてみるといいでしょう。それが自社とマッチしていない場合、どこまで譲歩できるのか、などを話してみるといいと思います。
ミッション・ビジョンに共感する人材
即戦力採用というと、ついついスキルマッチングを重要視しがちです。
しかし少人数で事業運営を行う中小企業に定着するためには、スキル以前にミッション・ビジョンへの共感は不可欠といえるでしょう。
中小企業の現場では、業務プロセスがきっちりと固まっていない場合が多いです。また事業のトライ&エラーを繰り返すことが多いため、環境変化も多くなりがちです。
このような環境で何らかの問題やトラブルが発生したとしても、企業ミッション・ビジョンに共感していれば「自分が何とか現状を切り拓こう」という踏ん張りがききやすくなります。
ミッション・ビジョンへの共有がない場合、トラブル処理を上層部に委ねるなど、自分事として捉えにくくなります。
最悪の場合、「こんなはずじゃなかった」と早期離職されてしまうリスクがあります。
一人遊びができる人材
中小企業にはそれほど頻繁に入社者がいるわけではありません。
入社後にOJTの教育担当をつけ、丁寧なマニュアルで立ち上げ教育ができればいいのでしょうが、リソースが限られている中小企業ではそれが難しいのが現実です。
ともすれば、入社者が来ても「とりあえずこの資料読んでおいて」とだけ伝え、いわば“放置状態”になるケースもあるでしょう。
そんな時、放置された状況を悲観したり焦燥を覚えたりすることなく、自分でできることからやれるような“一人遊び上手”人材は、思いのほか定着がしやすいです。
自ら手を動かす志向が強いため、指示がなかったとしても動きを通じて仕事を覚えることもできます。
即戦力人材を見極めるための3つの選考ポイント
経験やスキルは職務経歴書でチェックすることを前提に、ここでは面接の場でぜひとも確認したい即戦力人材を見極める3つのポイントを紹介します。
仕事の修羅場エピソードを聞く
中途採用の場合、前職の仕事のエピソードは必ず確認する項目でしょう。
しかし今はSNSなどの情報発達の影響で、他人のエピソードでも職務経歴書に“盛り気味”で記述することもできてしまいます。
本当に応募者自身の経験なのかを確認するには、面接でエピソードを深掘りするしかありません。
「〇〇のプロジェクトリーダー」という記述に対して、リーダーの責任範囲、メンバーのアサイン方法、予算消化の管理方法など、事細かくヒアリングをするようにしてください。
その際、トラブルなどのいわば“修羅場”経験を聞くことが有効です。
トラブルが起こった際に、応募者がどのような課題解決思考を持っているか、どれほど自分の意思で解決を捉えているか、など有事の際の胆力が見極めることができます。
トラブルに強い人材は、転職後の壁を自らの力で打破し、戦力化しやすいでしょう。
転職理由を深掘りする
転職理由を確認する際は“現状否定型転職”なのか、“未来肯定型転職”なのかの見極めが大事です。
多くの応募者は現状にネガティブな意見を言わないかと思いますが、「現状は何が得られていなくて」「転職先では何を得たいのか」の接続がしっかりしているかは必ず確認したいポイントです。
その際、「現状で足りないことを埋める」だけではなく、転職先で挑戦してみたい仕事が明確にある応募者は即戦力化しやすいでしょう。
前述のように中小企業の現場では中途入社者はしばらく放置状態になる可能性もあるため、本人の中で「やりたいこと」という意思がある人の方が自家発電をしやすいからです。
なお転職理由を深掘りすると委縮する応募者は多いです。
「〇〇さんの希望が自社で叶うかどうか心配なので、質問しています」などの枕詞をつけると、応募者もリラックスして回答できるでしょう。
リアリティがある情報提供を行う
応募者に根掘り葉掘り聞くぶん、自社側も正直に情報提供を行ってください。特にミッション・ビジョンを伝える際には、単なる言葉だけではなくそのミッションがよく表れているエピソードなど、リアルな情報提供を心がけてください。
ミッション・ビジョンに共感があり見込みのある応募者の場合は、さらに現場の問題点などの実情もなるべく詳らかに情報提供をしてください。
自社課題を開示するのは抵抗があるかもしれませんが、即戦力になってもらうためには、入社後に「そんなこと聞いていない」と思われるのは最大の障害となります。
まとめ
即戦力人材はどこの企業でも引く手あまたです。
ただし中途採用において注意しておきたいのは、”即戦力=実際に力を発揮する状態”になるためには、まずは会社に馴染むことが前提になる点です。
どんな腕の立つ人であっても職場で委縮していたり、不満を抱えていたりする状態では、本来の力は発揮しにくいでしょう。
スキルマッチングだけで即戦力人材の判子を押し現場で不適応を起こすことがないよう、会社に定着するかどうかも採用の際には確認をするようにしてください。
* xiangtao / PIXTA(ピクスタ)