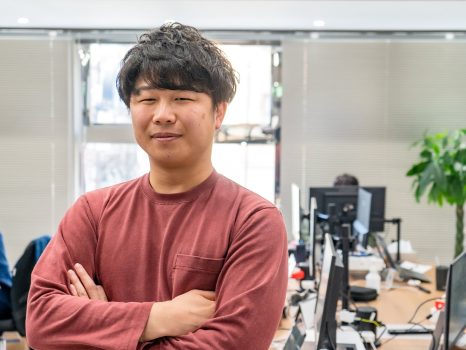成長するベンチャー経営者に共通するマインドとは?キャピタリストが語る
ウナギの稚魚を水槽にいれて運ぶと、水槽が揺れるストレスのせいで、その多くが死んでしまいます。しかし、天敵であるナマズを入れておくと、輸送時の揺れよりももっと強いストレスである生命に対する危機感が勝り、生存率が上がるそうです。人間も、適度なプレッシャーやストレスは生命力を育み、通常以上の成果を生み出すことがあります。
実際に生きている社会は多様性に満ちており、天敵も多く存在し、温室育ちが環境変化に弱いのは当然のことになります。生き残りをかける、という意味では企業経営も自然に学ぶところは数多くあります。
300社以上の企業を見てきたベンチャーキャピタリストである筆者が、成長するベンチャー企業経営者の共通点だと感じた“経営者マインド”をご紹介します。
目次
「居心地のよさ≠持続可能性」
組織の中にも異見する人がいてこそ、議論が活性化し、ユニークな結論が出ることがよくあります。同質な人ばかりだと、凡庸な結論が繰り返されます。環境変化が少ない世界では違和感がないことが心理的安定性を生み出しますが、新しい価値の創造にはつながりません。必ず起きる環境変化に対応していくには、多様性を受け入れてこそ、持続可能性は高まります。居心地のよさと持続可能性は、ある意味で二律背反なことかも知れません。
この二律背反を制してこそ、企業を成長させることができるのではないでしょうか。そのためにマインド・思考についてお話します。
成長を目指す上で必要な経営者マインドとは
1)危機こそ“生き延びるチャンス”ととらえる
心にゆとりの持てる職場環境は理想ですが、経営基盤が脆弱なベンチャー企業に危機は必ず訪れます。絶望的と思える状況を掻い潜り、生き延びた企業はとても逞しくなります。大きな危機を経験することで、鈍感力を身につけ、高い目標に向かって邁進することができるようになります。
ベンチャー企業が成長の機会を得るには、果敢な挑戦が欠かせません。果敢な挑戦は失敗に終わることが多いのですが、その学習効果を生かして、挑戦なしには得られないノウハウや精神力が身につきます。
2)居心地の悪さを受け入れる
成長を目指す企業は、あえて居心地の悪さを求めていく必要があります。達成できそうな目標ではなく、(知恵を絞らないと)到底達成できない目標を掲げることで、他社にはない収益モデルを思いつくことができるようになります。
また、価値観の共有が出来ているサポーターからの苦言は、建設的に捉え成長の糧としていく必要があるでしょう。叱咤激励、今ではあまり使われなくなりましたが、よき理解者からの苦言は英気を養うことに必ずつながります。
3)無茶ぶりや苦言に感謝する
お客さまからの意見は、期待の大きさの表れであり、大きな期待に応えてこそ、さらに大きな信頼を獲得することができます。無茶ぶりや短い締め切りは喜んで受け入れていきましょう。
会社に関する問題点を指摘する社員は、忠誠心の高い社員です。給料だけ貰えればいいと思っている社員はイエスマンを貫き、波風を立てません。本当に会社のことを考えている人がどこにいるのかを知っていれば、経営者は正確で明解な意思決定が行えます。
4)必ず会社を成長させる意志を持つ
成長途上にある会社の経営者は、耳の痛い話こそ大切にする必要があります。赤字の状態で心地よさを求めていては、資金は減っていくばかりです。居心地の悪さと決別したければ、早期に黒字を達成し会社を成長軌道に乗せていくことです。苦しい時期をしっかりと乗り越えていけば、旺盛な生命力が育まれ、長続きする安定した経営が可能になります。居心地の悪さは、成長へのプロセスとして楽しみましょう。
成長に指定席はなく、自由席車両でいかに生きていくかが成否を分けることになります。
【こちらもおすすめ】組織成長の秘訣は“人がたまれる場所”?急成長ベンチャー企業primeNumber代表取締役CEO・田邊 雄樹氏にインタビュー
悩んだときの対処法とは
悩んだときには、経営者の仲間や、頼りにしているコンサルタントなどの相談先など、信頼できる人に話を聞いてもらいましょう。気持ちを落ち着け、運を引き寄せるために神社仏閣に行くことや、初心に戻り、親と話すことも有効です。相談する際は、答えをもらおうとするのではなく、「自ら気づくこと」が重要です。対話から学び取り、気づきを行動へ移しましょう。
まとめ
ドラッカーも「意思決定における第一の原則は、意見の対立を見ない時には決定を行わないことである」といっています。誰も反対しないような意見は、会社を好転させるようなものではないのです。柔よく剛を制す世の中で勝ち残り、成功するためにも、厳しい時期を乗り越えた先に“本当の進化”があることを認識し、日々邁進していきましょう。
【こちらもおすすめ】ワンマン社長は中小企業に必要?ワンマン経営が導く組織崩壊の末路と成功
*EKAKI, rbhavana, metamorworks, Lukas / PIXTA(ピクスタ)