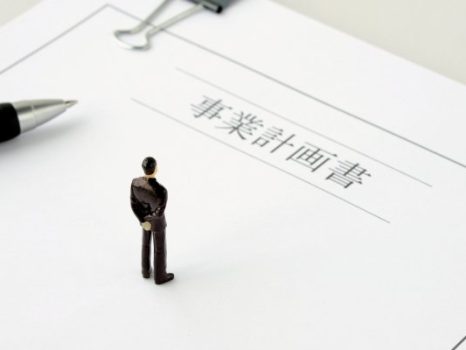事業再生ノウハウである「財務リストラ」とは?コンサルタントが解説
「リストラ」という言葉には、ネガティブな印象を感じられる方が多いのではないでしょうか?
しかしながら、本来は「リストラクチャリング」「再構築」という意味であり、企業活動において前向きな意味合いを持つ言葉です。
リストラを大別すると3種類になります。詳しくは前回執筆した記事もご参照ください。
1.業務リストラ
売上の向上、売上原価の圧縮、販売管理費の見直しといったものが挙げられます。つまり、本業の中での利益確保へ向けた自助努力というイメージです。2.事業リストラ
主だったものは、不採算事業からの撤退があります。先行投資がかさんでいる場合は損切が難しいですが、赤字事業からの撤退であれば効果はてきめんです。3.財務リストラ
今回のテーマです。
今回の記事を読み終えた後に、読者の方のリストラに対する印象が少しでもよくなり、実際の経営判断に役立つヒントを解説していきます。
3つの財務リストラとは
財務リストラとは以下の3つに大別できます。一つずつ、簡単に説明します。
①資産リストラ
②負債リストラ
③資本リストラ
①資産リストラ
資産リストラは車両、機械設備、不動産、有価証券などで「余っている資産の売却」です。「そんなの資金繰りが悪くなったらいわれなくてもやるよ!」という経営者が大半でしょうから、深くは触れません。
②負債リストラ
負債リストラは、年商10億円規模までの中小零細企業にとって大抵は喫緊の課題です。しっかりと取り組んで行けば、資金繰りの改善は必ず見えてきます。債務カット(有利子負債の圧縮)は難易度が高いですが、借入の再編でも工夫次第で現預金量を回復させることができます。詳細は後述します。
③資本リストラ
DES(デットエクイティスワップ、負債と資本の交換)はあり得ると思います。というのも、役員が役員報酬で受け取ったものの、事業の資金が乏しくなったり銀行借入が面倒であったりして、長きにわたり役員借入金が残っていることが頻繁(ひんぱん)にあります。さらに、減資も繰越欠損金をなくす代わりに資本金を減少させ、結果的に利益配当を出しやすくするケースですが、もともと資本金自体が少ないなか小規模・零細企業が対応することは稀です。
【こちらもおすすめ】倒産の兆候を見逃さない!今さら聞けない「財務分析」のやり方【経営の基礎】
中小企業が優先的にやるべき財務リストラとは
前段で書いた、②負債リストラを深堀りしていきます。
現預金が枯渇すれば、当然それは企業にとって「死」を意味します。そして、現預金は企業にとって血液であり、企業活動の体力の源泉です。
体力は「儲けるチカラ」といいかえることができます。具体的にいいますと、積極戦略に基づく施策に投下するための元手となる資金が、どうしてもV字回復には必要であるという原理原則です。虎の子の資金を投下した施策を成功させることで、税引き後の当期純利益を出し、債務超過という異常事態から資産超過という健康体に持っていくことが本筋の事業再生です。ちなみに、5年以内で債務超過を解消する計画を描かなければ、取引金融機関は前向きな支援姿勢を示してくれることはないでしょう。
販管費の削減や原価の低減は、財務リストラではなく業務リストラの領域であり、次の段階の施策といえます。工夫さえすればできる、業績回復のための一丁目一番地は“財務リストラ”であると考えます。その手法である2点をかみ砕いて説明します。
短期継続融資導入の効能
まず、経常運転資金という考え方を思い浮かべてください。経常運転資金とは、簡単にいえば「支払いと回収のズレ」であり、「企業活動を回していく上で最低限もっておかなければならない金額」といえます。
〈計算式〉
売上債権+在庫-仕入債務
≒
売掛金+棚卸資産-買掛金
となります。
たとえば、年商15億円で上記の経常運転資金が2億円、銀行借入残高が5億円の企業があったとします。
(借入内訳)
①A銀行(第一地銀)・・・残高2億円 期間7年 信用保証協会付
→毎月元金返済額 238万円
②B銀行(第二地銀)・・・残高2億円 期間10年 信用保証協会付コロナ融資
→毎月元金返済額 167万円
③B銀行(第二地銀)・・・残高1億円 期間5年 プロパー融資(不動産担保・根抵当権設定)
→毎月元金返済額 167万円
毎月の元金返済額合計は572万円となり年間の元金返済額は12カ月分ですので、6,864万円となります。
ここで、根抵当権を設定しているシェア的にメインバンクであるB銀行へ、毎月の元金返済がなく、期日一括返済となる当座貸越枠の設定、手形貸付への切り替えを打診します。そして、経常運転資金額のとおり、2億円の貸越枠もしくは極度2億円の手形貸付が無事に認可となった場合、銀行借入は以下のように再編可能になります。
※往々にして、メインバンクが不動産担保設定をしている場合、担保価値内での融資と競合の銀行より優先的に保証協会の枠を使い、メインバンクとしての責任ともいえるリスクテイクをまったく取っていないというケースが散見されるので、定期的に意識して複数の人間に銀行取引が適正なのか見極めてもらう必要があります。
①残高1億円(新規実行2億円のうち1億円を使って繰上げ返済)
→毎月元金返済額 119万円
②そのまま。残高2億円
→毎月元金返済額 167万円
③当座貸越枠もしくは手形貸付にて2億円、1年更新、期日一括返済(2億円のうち1億円を使い、プロパー融資1億円を返済)
→毎月元金返済額 0円(金利のみの支払い)
融資残高は変わらないものの、この再編で得られたメリットを整理すれば下記の2点です。
- 返済分の保証協会付融資の空き枠が1億円分増加
- 毎月元金返済が572万円から286万円になり、1年で(572万円-286万円)×12か月=3,432万円の現金支出の減少
長期一本化がもたらすメリット
同様のケースで、上記の再編にさらに長期一本化も組み合わせると、さらなる資金的メリットを得られます。
①と②を2023年1月から開始された、コロナ融資の借換保証制度で一本化し融資期間10年で組み直す
→毎月元金返済が286万円から250万円に減少。36万円×12か月で年間432万円の現金支出が減ります。
つまり、前段の3,432万円に432万円を加えて、年間で3,864万円の現金支出を減らすことができます。そして、保証協会付の空き枠を利用すれば、1億円の資金量を増やすことも可能になります。
【こちらもおすすめ】事業再生の進め方とは?経営者が常時から持つべき視点
財務リストラ成功のカギとは
財務リストラ成功に向けて重要になるのは、“経営者の実行力”です。つまり、真摯に取り組む気合と根性です。現代風にいうなら「レジリエンス」ということになります。結局は、現金支出を減らしたり新規で調達したりしながら資金量を増やす行為は、それなりにエネルギーが必要な交渉となります。自社の現状を正しく理解してあるべき未来を描き、いつまでにいくら稼ぎ、どんな財務状況にするのかという「経営計画」を、誰が見ても分かる形で策定しなければなりません。
正直なところ、これは骨が折れる作業です。しかしながら、この「経営計画」を策定する行為こそが、自社の進んでいくべき道を描くわけですから、経営者にとって最優先事項であるべきでしょう。業績改善に近道はありません。多くの企業がよりよい未来に進んでいくことを願います。
【こちらもおすすめ】優秀な経営者の強みは意思決定?よい意思決定を行うためのプロセスとは
まとめ
- 財務リストラには、資産リストラ、負債リストラ、資本リストラの3種類があり、違いを理解する。
- 業績が堅調な企業であってもそうでなくても、借入の再編で現金支出を減らし、積極的な攻めの施策に投下できる資金効率を上げることができる。
- 「経営計画」の策定は業績向上に必須である。進むべき道を示すものがなければ、ただ場当たり的な案件の積上げになってしまうからである。
*Jirapong Manustrong,Billion Photos, metamorworks / shutterstock
【まずはここから】オフィス移転・改装・レイアウトお問い合わせはこちら