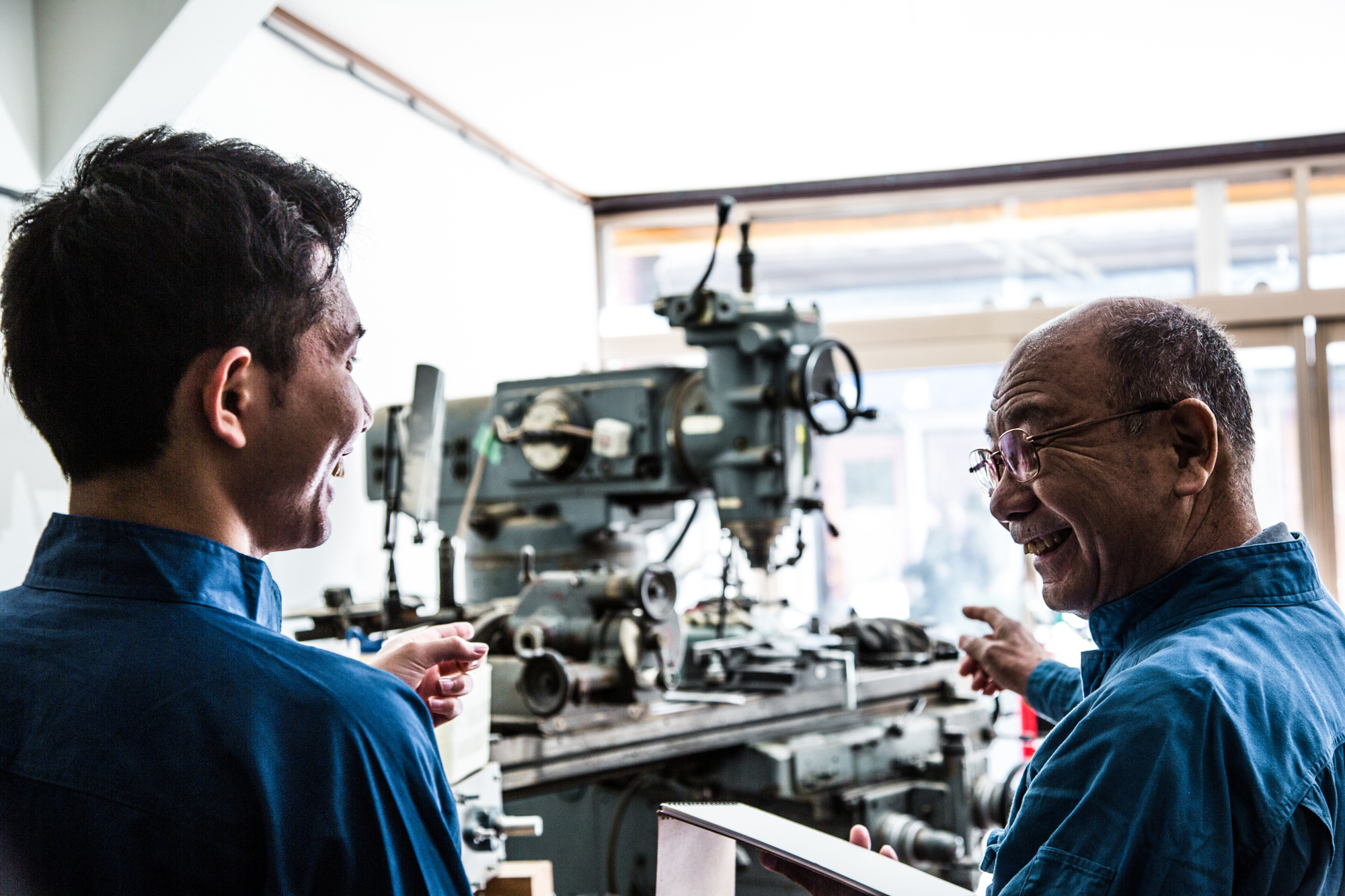「D&I」「DE&I」とは?中小企業が取り組むべきポイントを解説
以前ご紹介した記事では、ダイバーシティ経営についておよび、目指す意義や方法について解説しました。
昨今では、ダイバーシティ経営をより具体的に噛み砕いた概念として、「D&I(ダイバーシティー&インクルージョン)」や「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」の必要性や意義が、強く唱えられ始めています。
今回は、中小企業における「D&I」「DE&I」への向き合い方について解説していきます。
目次
ダイバーシティ経営と「D&I」「DE&I」の違い
「ダイバーシティ経営」「D&I(ダイバーシティー&インクルージョン)」「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」は、いずれも企業文化や組織運営に多様性を取り入れることの重要性を強調していますが、その焦点やアプローチに違いがあります。
まず、ダイバーシティ経営は、性別・年齢・国籍・障害の有無など、さまざまな背景を持つ人材を組織に取り入れることを重視しています。
一方で、「D&I」は多様な人材が組織内で受け入れられ、価値を発揮できる環境をつくることを意味します。単に多様な人材を採用するだけでなく、それぞれが自身の能力を最大限に活かせるような職場環境を整備することを重要とする考え方になります。
そして「DE&I」は、ダイバーシティとインクルージョンに加えて、エクイティ(公平性)の概念を取り入れています。エクイティとは、個々人が持つ独自の状況やニーズを考慮し、すべての従業員が公平な機会を享受できることを意味します。これには、昇進や研修の機会、給与の公平性など、職場での平等な扱いを保証する取り組みが含まれます。
職場の人材の多様性だけでなく、働く環境を整え成果を上げるための支援を行い、評価やキャリアステップの向上を組織的なゴールとして重要視しています。
なぜいま「D&I」「DE&I」が重要視されているのか
「ダイバーシティ経営を実践している」と標榜している企業でも、その成果を経営成績まで享受できていないケースが多く見られます。単純にダイバーシティ実践の前後で、財務諸表および経営管理レベルでの数値が変化していなければ、享受できてないと判断できるでしょう。
では、なぜ結果に表れないのでしょうか。それは潜在的にある多様な人材に対する「主戦力にならない・しない」というバイアス(思い込み)が、多様な人材の本質的な活用を抑止していることに起因すると考えられます。このバイアスのために、人材の活用や配置が旧来の範囲にとどまってしまい、当事者たちの活用範囲が限定的になるだけでなく、経営指標へのインパクトが表面化してこないことにつながるのでしょう。
このような背景が、多くの企業で成功への障壁となっていたとさまざまな調査からわかってきたために、もう一歩具体的成果に至るためのガイドラインとして「D&I」「DE&I」という考え方が広まってきました。
経済産業省におけるダイバーシティ経営推進の取り組みの中でも、アンコンシャス・バイアスの状況調査および今後の対策を述べた部分がありますので、興味がある方はぜひご参照ください。
【参考】令和4年度 産業経済研究委託事業(ダイバーシティ経営推進に向けたアンコンシャス・バイアス研修のあり方と効果測定指標等に関する調査)/東京大学
表面的に多様な人材を組織に取り入れただけで「ダイバーシティ経営の実践ができている」と満足してしまうのではなく、多様な人材が組織内で活躍し、公平な機会を享受できる環境を構築しなければ、本質的な目的を叶えられません。
実際に今の日本における就業環境を見ると、女性やその他多様な文化的・社会的背景を持つ人材が活躍している状況が一般的であるとは言い難いでしょう。その事実を証左する文献・データを探すといくらでも出てくる、というのが実態です。
日本国内でダイバーシティが実現されている職場を考えたときに、言語的な環境が大きな壁になることは否定できません。最初の環境整備として、ジェンダーギャップ解消の取り組みから始めて徐々に多様性の幅を広げていくことが、現実的な取り組み方の一つになるのではと筆者は考えます。
【参考】女性就業率上位でも男女格差「120位」に沈む日本のなぜ/日経ビジネス電子版
多様な人材が実際に活躍するためには、組織内の頭数を多様にするだけではなく、活躍するための環境や文化が公平に整備されている必要があるということです。前段として、そもそも人員のバランスもまだ多様性を実現できていない場合には、活躍するための環境が整っていないことが多いと推察できます。
つまり、「D&I」「DE&I」は多様な人材・多様な働き方を許容する就業環境実現を目指し、頭数だけではない中身を伴った変化を進めていくための、重要な考え方と捉えられます。
【こちらもおすすめ】中小企業向け!「人手不足を解消したいとき」に役立つ支援制度を一挙解説
「D&I」「DE&I」が企業にもたらす効果
冒頭で紹介した記事では、ダイバーシティ経営の必要性について「多様化するニーズへの対応」「柔軟な組織的対応能力の向上」「取引・投資先としての信頼性向上」の3点について説明しました。これらの取り組みは、昨今特に重要視されている経営課題まで影響を及ぼすことができるでしょう。
「D&I」「DE&I」がもたらす効果についても、ダイバーシティ経営の必要性に通ずるものがあります。また、以下のような効果も期待できるでしょう。
人材獲得力の強化
柔軟な組織対応力の向上が図られることで、他の企業と比べてより好条件な就業機会を得られることを、多様な人材に向けて企業自体の魅力としてアピールできます。
イノベーション創出
多様化するニーズへの対応という点においては、包含される概念ではあります。しかし、社内での働き方や社内制度の整え方などについて多面的な考え方や意見を取り入れることで、イノベーションの創出につながるでしょう。
生産性の向上
自然な帰結と言えますが、「D&I」「DE&I」を取り入れることで、柔軟な組織対応力を得るために社内での人材と業務の流動性が高まるはずです。そうすると、役割・組織をまたいだ業務理解が進みます。
また、多面的な人材配置と併せて、これまでには得られなかったアイデアや試みを積極的に取り入れて試行錯誤することで、生産性向上の余地が大きいでしょう。
これらの効果は、もちろん「D&I」「DE&I」の取り組みだけで得られるものではありません。しかし、具体的な取り組みが企業文化として育っているかどうかで、得られる効果の伸びしろが大きく変わってくることが最も重要な点であるといえます。
「D&I」「DE&I」を推進していくために
「D&I」「DE&I」を実現するためには、組織内での多様性を単なる数字としてではなく、すべての従業員が公平に活躍できる文化を根付かせるための具体的な対策が必要です。以下に、そのための主要なアプローチ例を紹介します。
実際は現場ごとの状況や個性に応じてより柔軟に考える必要がありますが、既製の多様性実現よりも、結果に対する深い意識付けが大切です。
経営層のコミットメント
経営層が「D&I」および「DE&I」の価値を理解し、積極的に推進する姿勢を示すことが重要です。経営陣からメッセージを発信することで、組織全体に方針を浸透させる基盤となるでしょう。
包括的な研修プログラムの実施
全従業員に対して、多様性や包摂性、公平性に関する研修を定期的に実施し、偏見やステレオタイプに対する理解を深めることが必要です。バイアスは自覚を伴わないものなので、教えるというよりも気づきを生み出すアプローチが重要でしょう。
また、インクルーシブなコミュニケーションやリーダーシップに関するスキルを強化する研修を提供することで、すべての従業員が互いを尊重し合う文化を育成し、気づきを日々の活動に反映させることができます。
インクルージョンを促進する制度の整備
リモートワークやフレックスタイムなど、多様な働き方を支援する制度は、従業員一人ひとりのライフスタイルやニーズに対応します。加えて、客観的かつ公平な評価基準を設け、パフォーマンスと成果に基づく評価と報酬の体系を構築するでしょう。
ここで肝心なのは、経営的な成果につながる活動を適切に評価できる考え方および評価者への指導です。伝統的な人間関係に基づく評価を否定する必要はありませんが、情実的な評価が仕事結果の評価よりも優先されるような事態は避けなければいけません。
また、評価者の評価もインクルージョンを考慮した体系に変えていく必要があります。
多様性を反映した意思決定構造
意思決定過程において、多様な背景を持つ従業員からの意見や提案を積極的に取り入れるようにします。これは意思決定プロセスや会議体の設計などに具体的に反映させる必要があります。
ダイバーシティ委員会などを設置し、多様性に焦点を当てた組織全体の取り組みを評価・推進するなど、あくまでもバイアスを改善していくための取り組みがより効果的な結果を生み出します。
多様性の監視と評価
「D&I」および「DE&I」に関する取り組みの進捗を計画化し、定期的に評価することで改善点を見つけ出します。同時に取り組みの成果や課題を組織内外に公開し、進捗状況についての透明性を保つことで、お題目に終わらない姿勢を維持できるでしょう。
コミュニティとの連携
多様性と包摂性に関する外部団体やイニシアティブと連携し、組織外の知見を取り入れることで、内部の取り組みを強化できます。ここではバイアス解消のためにも、表面的な関係性ではなく闊達な議論を積極的に行い、継続的に理解を深めるためのよい実践の場としましょう。
【こちらもおすすめ】“女性社員の活躍”に潜む無意識の思い込みを解消するための取り組みとは
実践の場は目の前に、まずは手を付けられるところから
今回の記事では、概念と取り組みのための考え方をご紹介しました。実際に取り組みを始めることで、人材の獲得や社内の業務円滑化に効果が出るでしょう。人材不足に悩む現代の日本の経営者にとっては、とにかく早く手を付けられるところから取り組むことが急務と考えます。
まずご自身の仕事のみならず、家庭での振る舞い方でもあえて「変容できるところ・すべきところがないか」といった観点を取り入れてみてはいかがでしょうか。実際に優秀な女性を人材として獲得することは、企業として大きな躍進につながるでしょう。
*metamorworks, keyphoto / PIXTA(ピクスタ)
*Jacob Lund / shutterstock
【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら