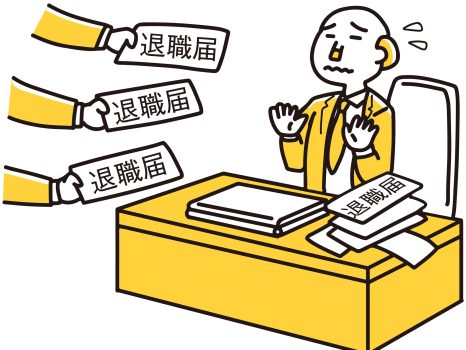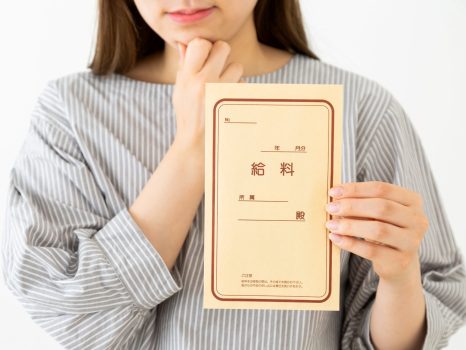「優秀な人が辞める会社」とは?職場を見直すうえで見落としがちなポイント
社内で活躍していた人から突然退職の申し出を受けたり、苦労して採用した人材が入社一年もたたないうちに辞めてしまったりすることがつづくと、事業継続や社内の雰囲気を良好に保つうえで悪い影響を及ぼす可能性があります。 “優秀な人”の退職がつづく場合、会社の制度やあり方に、なにかしら問題のある可能性があるかもしれません。
本記事では、優秀な人が辞める会社の特徴をまとめました。見落としがちなポイントを、改めて見直すきっかけになれば幸いです。
優秀な人が辞める会社の特徴とは
退職は個別性の高い事象なので、その理由を一概に決めつけることはできません。しかし、“よくあるケース”というのは存在します。自社が、“よくあるケース”にどれくらい当てはまるか見直してみることは、優秀な人の退職を減らすのに効果があるはずです。
ここからは、優秀な人の退職につながる“よくあるケース”を4つ紹介します。
【こちらもおすすめ】仕事を辞める前兆とは?社員の退職フラグを見逃さない対応策1:入社後サポートの偏り
新卒入社であれば、受け入れる現場としても「新卒だからしっかり育てなければ」という意識を持ちやすいです。
一方で中途入社というのは、中途入社者自身も受け入れ側も「即戦力」という鎧をまとってしまい、「こんなこと聞いたらできないやつと思われるかも」「まずはお手並み拝見」といったように、入社後のサポートが薄くなりがち。その結果、中途入社者が孤立してしまい、最悪の場合、短期間での離職ということにもなりかねません。
入社後サポートとして、“仕事を教える”ことはどの会社でも行っているでしょう。不足しがちなのは、“人を教える”サポートです。一般的に仕事を進めるときは、「この件は、まず◯◯さんに話を通しておこう」「△△について分からなければ□□さんに聞けば大丈夫」など、無意識のうちに“関わる人”をイメージします。中途入社者は、経験や能力を買われて入社したはずです。しかし“関わる人”については、会社を移ったことによってリセットされています。これでは、本来の力を発揮することもできません。
中途入社者に対して、“仕事を教える”サポートに加えて、関わる人を増やすような“人を教える”サポートは十分にできているか、改めて見直してみましょう。
【こちらもおすすめ】優秀な若手社員の採用・定着に向けて ~「入社後フォロー」での3つのポイント~2:評価への不満
“評価に不満がある”というのは、よくある退職理由の一つです。こういった声を受けて、「評価制度をつくろう・改定しよう」と考える経営者・人事の方も多いでしょう。しかし、評価制度の良し悪しに目を向ける前に、考えてほしい点があります。それが、評価というのは“制度”と“運用”から形成されているということです。
“制度”というのは、評価基準や等級などのように、明文化されているものを指します。一般に、“評価”といったときにイメージされるのは“制度”ではないでしょうか。“制度”は、会社(経営者・人事)が前もって決めておくものであり、一度決めたらそう簡単には変えません。
一方、評価を実際に行ううえでは、“運用”が重要です。“運用”とは、明文化された“制度”を、実際に社員に適用することを指します。具体的には、評価基準(制度)に従い、評価結果を“決める・伝える”という行為です。評価結果を“決める・伝える”ときに、評価者が制度の趣旨から外れた決め方・伝え方をすれば、制度はその時点で骨抜きになってしまいます。
「評価に不満がある」という声をよくよく聞いてみると、その対象は“制度”というよりは、“運用”である場合がほとんどです。そして、社員の目に映る“運用”というのはすなわち、“評価者”です。“評価への不満”というのは、「なんであの人に評価されなきゃいけないんだ」という“評価「者」の不満”といえるでしょう。
普段の仕事ぶりをしっかり見ることができる人を、評価者として選んでいるでしょうか。また、評価者は目標設定やフィードバックを通して、普段から本人と「評価の納得感につながる」コミュニケーションが取れているでしょうか。「評価制度をつくろう・改定しよう」とする前に、“運用”≒ “評価者”の人選と、コミュニケーションを見直してみてください。
【こちらもおすすめ】「評価に納得できないので辞めます」どう防ぐ?評価制度改定を成功させる3つのアクション3:コミュニケーション不足
職場の問題のほとんどは、“コミュニケーション不足”に帰着するといってもよいでしょう。しかし、コミュニケーション不足と大括りに捉えてしまっては、解決の糸口が見えません。コミュニケーションの中身を、もう少し分解してみましょう。
働き方改革やコロナ禍を経た今、職場で不足しているコミュニケーションの一つが、お互いの人柄を知るためのコミュニケーションです。以前は出社が中心だったため、オフィスで毎日顔を合わせ、仕事が終わったあとも食事や飲み会に行くことがよくあったという人が多いでしょう。それらは、自然とお互いの人柄を知ることにつながっていました。その人の印象・価値観を知っていることは、無意識のうちにコミュニケーションの潤滑油になっていたはずです。
現在は、リモートワークを主流とするためにそれがスッポリと抜け落ち、業務上の指示や連絡だけのやり取りが蔓延している職場が少なくありません。業務上の指示・連絡はしているわけなので、短期的には仕事も回るし、なにも問題はないように見えます。しかし、潤滑油を欠いたコミュニケーションは、“言っている人の顔が見えない”ために、軋轢や不信感を生みやすいです。それが中長期にわたり蓄積すれば、「仕事は回っているけど居心地の悪い職場」となってしまいます。そういう職場から人が去っていくのは、想像に難くないでしょう。
お互いの人柄を知るためのコミュニケーションは十分でしょうか。業務の指示・連絡だけの、潤滑油を欠いたコミュニケーションにはなっていないでしょうか。
【こちらもおすすめ】ハイブリッドワークでも社員がつながる!組織内コミュニケーションを高めるオフィスのアイデア集4:組織風土の見えなさ
組織風土というと大げさに聞こえますが、要は「◯◯なときは普通△△するものだ」というような、仕事を進めるときの暗黙のルールのことです。
先述した入社後サポートの中で、仕事を進めるときには無意識に“関わる人”をイメージしている、ということを紹介しました。それと同様に、仕事を進めるときに“普通はこうする”と無意識に繰り返されるルーティンや共通認識が、その職場ごとにあるはずです。この暗黙のルールが積み重なったものを、組織風土と呼びます。
この説明を聞いて、自分の職場の暗黙のルールがすぐに思い浮かぶでしょうか。すぐにはパッと出てこない人が多いのではないでしょうか。“暗黙”のルールだからこそ、当の本人であってもなかなか気づきにくいのです。
退職理由として、組織風土という言葉が出てくることは稀でしょう。しかし、“暗黙のルール”と言い換えると、退職理由になりうることが分かります。仕事を進めるときに「うまくいかない」「邪魔される」「協力してくれない」と感じることが積み重なれば、それは退職の遠因になりますよね。これらネガティブな印象を持ってしまう理由の一つが、「暗黙のルールを知らないから」なのです。
暗黙のルールを知らないために、仕事を進めるときに周囲とうまくやり取りできない。そうすると、成果は出ないし、周囲からは「分かってないやつ」と思われてしまう。組織風土が退職の原因となりうる構図がここにあります。
仕事を進めるうえでの“暗黙のルール”を、できるだけ明文化するようにしていますか。中途入社や異動などで新しい人が職場に加わったときに、仕事を教える一環として“暗黙のルール”も教えているでしょうか。
まとめ
優秀な人の退職につながる、“よくあるケース”を紹介しました。本人も周囲も、仕事をうまく進めよう、仲良くやっていこうと日頃から意識しているはずです。しかし、目に見えないところを見落としているために、ポイントがズレてしまい、うまくいかないということが多いでしょう。
今回紹介した“よくあるケース”というのは、どれも目に見えないものです。一度そこに目を向けてみると、退職を減らすヒントが見えてくるかもしれません。
*shisu_ka / shutterstock