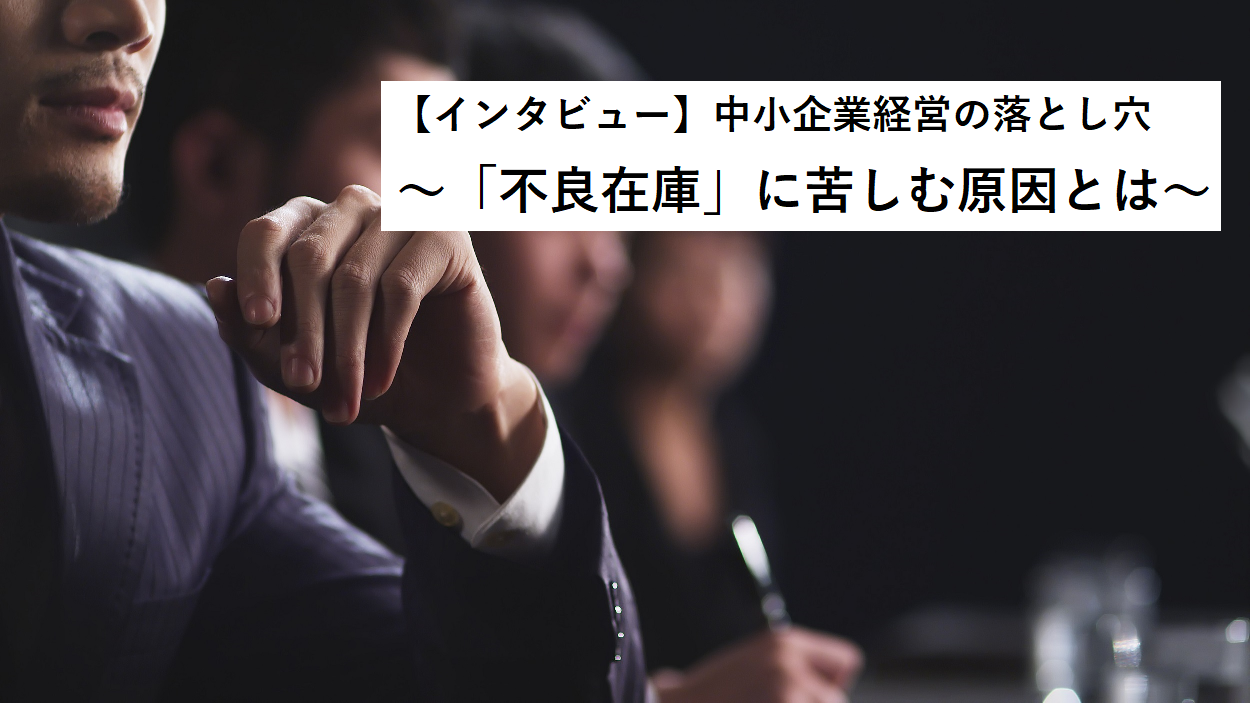“伝える”ことの難しさ、大切さ。伝統企業を継いだビジネスマンが見つけた経営のコツ(2)
企業経営においてキーとなる“伝える”ことの大切さを、大企業のサラリーマンから、家業の納豆メーカーを継いだ富士納豆製造所の星野玄喜さんに伺うインタビューの後半です。
サラリーマン時代とは異なり、ネイルサロンの経営や納豆メーカーでは、“相手の立場に立って”“工夫して伝える”ことの大切さを実感した星野さん。後半では、社外のさまざまな仕事相手に対しての“伝え方”の工夫について聞いていきます。
「伝えた」といっても「伝わった」とは限らない
明治屋やコカ・コーラにいたときは業界用語という共通言語があったため意志の疎通が早く、意識せずとも伝わるのが当然だと思っていたものの「“多くを説明せずとも理解できる相手”と仕事をしていたんだということに後から気づきました」。
自身も受け手として、「伝えられ方が違う」と感じたことも多々あったそう。
具体的に話すということは前提として、内部では共通言語を使って時間をかければ解決することも、外部に対しては相手の反応を見つつ確認しながら丁寧に進めていく必要がありました。
内部においては星野さんが説明したことを相手に反芻してもらい、理解度を確認するという方法をとっていたそうです。
サラリーマン時代のエピソードとして、星野さん自身が「伝えた」と思っていたことが実際には実行されていないことがありました。そのとき、上司に言われたのが「実行されてはじめて伝えたことになる」ということ。
メールや口頭で言っただけでは「伝えた」ことにはならない。自分はそれまでは単に「伝えたつもり」だったんだ、と教わったそうです。
ネイリスト相手に伝えたいことがあるときは、趣味の話など相手の興味がありそうなものを会話の中に入れることで、距離感が縮まり、距離感も縮まることも学びました。
失敗は大歓迎!前向きに失敗しよう
「失敗することは悪いことじゃありません」と星野さん。
「3回も4回も同じことで失敗するのは困りますが、前向きに失敗して、萎縮しないこと、失敗は大歓迎」と強く語る姿が印象的でした。
今はネイル事業から撤退したものの、納豆の現場に入ってからもネイルサロン経営での経験が活きています。
「人を大切にしなければいけないのはどこも同じです。工場で働いているのは職人というよりも近所のおばさんたち。あちらから見れば僕は息子のようなものなので、家族に世間話をするように伝えるのがいいと考えています」。
富士納豆を食べて育ってきた人が今度は作り手に回って働いているそうで、かしこまってしまうのはむしろよくない、目を見て話せば世代間ギャップも感じないといいます。

出典: 経営ノウハウの泉
効率的に販売ができない、今こそ通販に力を入れていきたい
コロナで試食販売ができないなか、全体的に売上が上がっている納豆業界。どうやら消費者の心理は、安価で健康的な食品に関心が向いているようです。加えて、製造工程もコロナ前と変わることがない業界なので影響を受けません。
富士納豆製造所が桃太郎納豆についてのプレスリリースを出し、まずは地元のテレビや新聞、雑誌に取り上げられた結果、徐々に民放キー局も興味を持ち始めています。
とはいえ、やはり売り上げは実店舗に頼るところが大きく、営業マンもいないため、販路を広げることにどうしても苦戦している様子です。
まずは通販で購入できることを周知していき、通販で購入したくなるモチベーションを高める必要があると語ります。
パッケージ制作でも伝え方を考えた
桃太郎納豆のプロジェクトチームに入ったアートディレクターの知人に、かつて賞を取ったイラストレーターがいました。
パッケージのオーダーは、「近代的でかっこよくイマっぽい桃太郎」でしたが、ここでも自分からイラストレーターに指示することはせず、その道のプロであるアートディレクターに希望を伝え、そのアートディレクターからイラストレーターに指示してもらう方法をとったそうです。
実際、はじめに上がってきたイラストはもっといかつく、怖そうな迫力のある見た目だった桃太郎でした。
納豆そのものは男女問わず食べられているものの、実際に買うときスーパーで手に取るのは女性が多いことを想定して、イラストの桃太郎は少しイケメンに変えてもらいました。
“イラストレーターが描きたい絵”と、“実際に商品が売れる絵”が必ずしも一致するわけではないのですが、そのことを直接イラストレーターに言うのではなく、意図を正しく伝えるためには、むしろ間に人を入れるべきという判断です。そのアートディレクターも絵を描く人なので、より適切に指示をしてもらえたようです。
パッケージイラストを女性向けに修正したのは、男性は保守的な考え方の人が多く、なにごとも冒険しない傾向があるようで、納豆の試食販売をしてもまず近寄ってきて来ないからだといいます。
女性の方が新しいものや珍しいものに興味を持ってくれるし、チャレンジしてくれる。だから、女性を意識したパッケージにしたそうです。
一方で、今まで富士納豆で築いてきた伝統的な良い部分は残すとはじめから決めていたので、「守っていくべきところ」である、納豆そのものの味は変えずにタレとパッケージだけを変えることにしました。実際、伝統の納豆の豆の味は好評のようです。

出典: 経営ノウハウの泉
納豆人気の高まるヨーロッパで勝負
最近、ヨーロッパでも納豆の需要が高まっているようです。そこで、星野さんは桃太郎納豆の輸出するチャレンジを計画中。
日本人も多く住み、日系スーパーも多いオランダのアムステルダム、ドイツのデュッセルドルフ、フランスのパリ、イギリスのロンドンの4都市でまずは2021年から納豆の販売にチャレンジするつもりだそう。
もともと日本食は健康的なことに加えて、2013年に和食がユネスコ無形文化遺産になったことでさらに注目を集め、豆腐はすでにヨーロッパに工場もあります。
納豆は匂いなどから多少ハードルは高いものの、まずは食に感度が高い人たちを狙い、認知を高めることに注力します。
ですが、ここで課題が発生。
2021年4月にEUの法律が改正されて、動物性原材料を使ったソース、たれ、ドレッシングのEU内への輸出が厳しく制限されます。現在国内で販売されている納豆に付属のタレの大半は鰹節の出汁を使っていて、この規制に抵触してしまいます。
鰹節はたれのコクを出すのに不可欠な材料で、代わりに昆布を使うとあっさりしすぎてしまう。しかし、これを克服する工夫を続けていて、「あと一息で完成しそう」ということでした。
パッケージに関しては、桃太郎納豆のアメコミ調のイラストが、このままでも海外でウケそうなので、アルファベットで商品名を記載する程度にとどめ、それが終わったらpop作りやSNS発信など周知に力を入れていくそうです。
「世界中どこで食べられても嬉しい納豆を目指して、伝え、伝えられ、アドバイスをもらいながらさらに工夫していきます」と語る星野さんでした。
常に相手の立場になって、伝えることの大切さ
星野さんは、大手メーカーのサラリーマンを経て、まったく畑違いのネイルサロンを経営し、さらにまた異なる家業の納豆メーカーを引き継ぎました。
その課程で、自分の想いや価値観を伝えることに難しさに何度も直面しました。
ネイリストに接客業の基本を身につけてもらうにしろ、新しいコンセプトの納豆製品を市場に出すにしろ、自分本意の発想だけでは駄目だと考えて行動を変えてきました。
ネイリストや、納豆を販売してもらう店舗の担当者や、実際にパッケージを手に取ってくれる顧客の立場に立ってみて「どうすれば伝わるか」ということを丁寧に積み重ねてきたのです。
これから、ヨーロッパでの納豆販売に挑戦するにおいても、きっとその「伝え方」が実を結んでいくことでしょう。
星野さんの今後にも期待です。