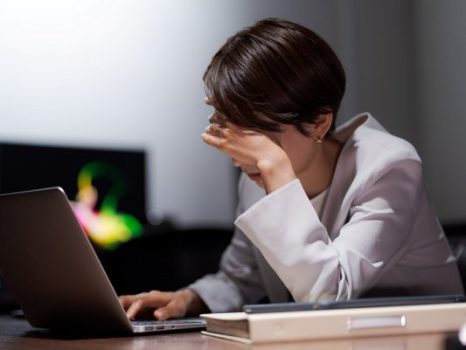社員のメンタル不調…見直すべき?社内制度策定のポイントを産業医が解説
産業医である筆者のもとに「メンタル不調者が増えてしまい、対応に迷っている……」という相談がよせられることがあります。メンタルでもフィジカルでも、病気やケガによる休職は誰にでも起こりうるものです。ただ、メンタル不調が要因の休職には特徴があり、それを踏まえたルールづくりをしておかないと困ったことが起きることがあります。“安心して休める・復帰できる”という風土をつくることは、働きやすい職場づくりの第一歩です。今回は、社員がメンタル不調になる前に最低限決めておいてほしい社内ルールと、ルールがない場合にどのような困りごとが起こるかについて解説していきましょう。
こういうケースありませんか?
ある従業員が「体調が悪いのでしばらく休みます。有給休暇が残っているので」と、休暇にはいりました。2週間の有給取得後に復帰しましたが、その後も体調が悪そうでパフォーマンスが低下しています。そのため周囲から心配の声もあがっています。
有給休暇は理由を問わず取得できるものです。しかし、上記のように“体調不良を理由とした休暇”に対して、何も手を打たないと、体調がさらに悪化・業務に支障がでるなどの困りごとが起こってしまうのです。業務外の疾病で業務につけない場合は、会社に休職制度があれば、その制度を利用するのが一般的でしょう。
休職に関しては、就業規則に記載があることがほとんどですが、診断書の提出や受診指示に関する細かい規定までは定めていない場合もあるでしょう。そのため以下のような規定をしておくことをおすすめします。
【社員のメンタル不調についてのウェビナー記事はこちら】遅刻や離席が多い社員…どうすれば?従業員の健康課題を整理する方法【産業医が解説】
休職に関する規定のポイント
まずは、以下のような休職復職に関する規定を定めましょう。
【参考】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き p.26~27 / 厚生労働省
1)休職をとるために必要な手続きの規定
「体調が悪いので休みます」と伝言を残して、出社されなくなる方がいらっしゃいます。診断書が提出されないと、体調不良の理由や休職の見込みの期間がわからないため、会社側の対応が後手になることがあります。そこで、“休職に際しては医師の診断書を提出すること”を必須としましょう。また、診断書には、以下の事項が記載されていることを確認しましょう。
・病名
・症状
・休業の見込み期間 など
有給休暇が多く残っている場合、病気の療養のために有給休暇を使用する方もいますが、“医学的な理由により5日以上休む場合は診断書の提出を求めることがある”というルールにしておくことが望ましいでしょう。
また、診断書を産業医がみれば「症状にあった医療機関に受診できているか」「休職の見込み期間が妥当かどうか」を確認できます。ぜひ相談してみてください。診断書を提出してもらい、必要に応じて産業医が確認することで「どのような体調不良で、会社側で対応が必要なのかどうかがわからない」「メンタル不調なのに内科から診断書が出ていて、適切な治療が受けられておらず不調が続いてしまう」という事態を防ぎやすくなります。
2)休職中のルールを決めておく
休職すると仕事から離れて療養することになります。治療の状況や復職の見込みなどについて、月1回程度、担当者を決めて連絡を取るようにしましょう。また、診断書は休職に入るときだけでなく、休職期間中にも提出してもらうようにしましょう。通常は1~2か月、長い療養が見込まれる場合は3か月分まとめての診断書が発行されることが多いようですが、会社のほうで“診断書は1か月ごとに出す”などのルールをつくってもよいでしょう。
休職期間を延長する場合、その都度診断書の提出をしてもらわないと、困りごとが起こることがあります。
たとえば、「初回の診断書の発行のときだけ受診して、その後通院していなかった」「定期的に通院していないため、傷病手当金の証明をしてくれる医師がいない」などの事態が起こりえます。このような事態を防ぐために、診断書の提出を義務付けることに加えて、産業医が休職中も面談をしておくと、体調の経過や治療方針が把握でき、復職時期や復職後の業務の調整が行いやすくなります。“休職中にも産業医面談を行う場合があること”について、規定に定めておきましょう。
また、復帰の時期がみえてくると、産業医面談などの復職準備を行うことになりますが、主治医に情報提供をお願いすることや、診療情報提供書を依頼することがある旨についても、規定に定めておくと説明しやすくなります。
3)受診や休職の指示ができるよう、就業規則に明記しておく
これまでの解説とは逆に、体調が悪そうなのに休職することを希望しない方がいます。業務内容の配慮などにより、体調が悪くても働き続けながら治療をする“両立支援”の場合もありますが、働き続けることで体調が悪化した場合、会社が“安全配慮義務”を問われることがあります。
とくにメンタル不調の場合、心療内科・精神科への受診が一般的になってきたとはいえ、「メンタルクリニックにはかかりたくない」「精神科の薬はのみたくない」と受診を躊躇(ちゅうちょ)することがあります。ただ、体調不良をそのままにして働き続ける場合のリスクを鑑みると、必要に応じて、産業医面談や受診、診断書の提出を会社から指示するほうがよいでしょう。これらは、就業規則に定めておくと、必要な場合に理解が得られやすくなります。また、ただ指示するだけでなく、受診先の選び方・診察の際の相談内容などのサポートがあるとよいでしょう。
【産業医がいない会社の対応策はこちら】メンタル不調で休職…産業医がいない企業で実施すべきメンタルヘルス対策とは
まとめ
従業員のメンタル不調に対しては、安心して休職し、体調が回復したら会社復帰できるよう制度を整えることが大事です。同僚や先輩の「病気で休職したが、復職してやりたい仕事に就けている」「休職したことがキャリアにとって不利益にならない」という実例が、一人一人の安心感につながります。
就業規則は、弁護士や社会保険労務士と相談しながら改訂することが多いですが、制度を作成・運用する際は産業医の意見も聞いてみてください。経験のある産業医であれば、休職復職の際に困りごとが起こりやすいポイントを把握しています。どのようなルールを設ければよいのか・どのタイミングで産業医が関わるのがよいのかについて意見をもらえるでしょう。休職のルールが整っており、原因の疾病やケガの種類によらず公正に対応してもらえるという環境は、従業員にとって安心できるものです。現場の声や、これまでの対応実績をもとに貴社にあったルールづくりを行いましょう。
【こちらもおすすめ】あなたの会社の休職制度は大丈夫? 休職トラブルを防止する4つのコツ
*Luce, kouta, nonpii / PIXTA(ピクスタ)
【まずはここから】はじめてのフリーアドレス導入ガイド