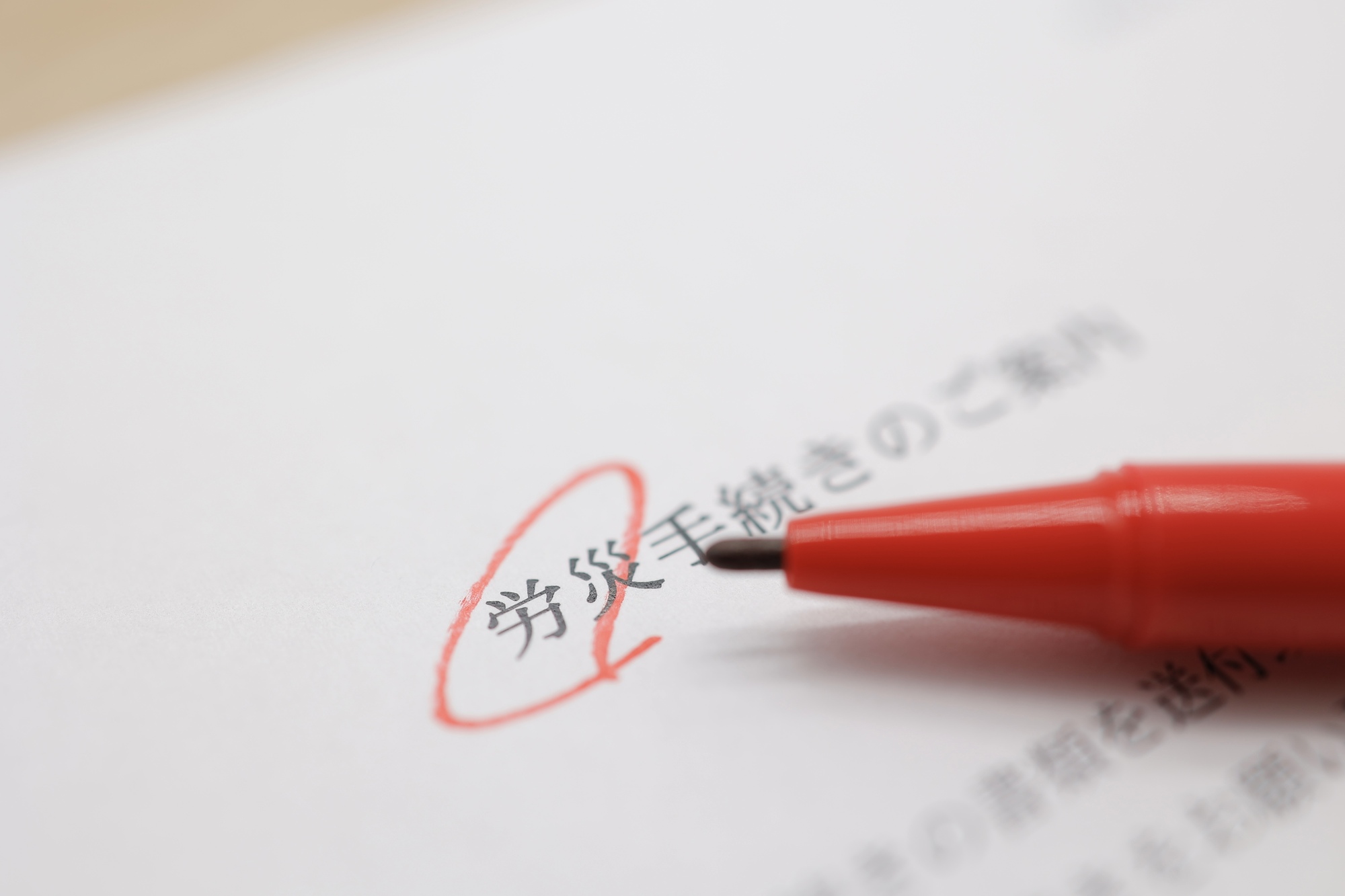メンタル不調で休職…産業医がいない企業で実施すべきメンタルヘルス対策とは
産業医/労働衛生コンサルタントの筆者は人事担当者の方から「メンタルヘルス不調を防ぐために、何か方法はありませんか?」「身体の病気の対応で困ることは少ないが、メンタルヘルス不調の対応には自信がない」というご相談をよく受けます。具体的な相談内容としては、以下のような内容です。
・ハラスメントの訴えがあった
・メンタル不調で休職者が出たが、どのように対応すればよいかわからない
・メンタル不調からの復職者が、たびたび体調不良を訴えるので困っている
メンタルヘルスの不調というのは、企業の規模に関わらず、どの組織でも起こり得るものです。そして、産業医がいない*中小企業でも社会資源を利用してメンタルヘルス対策を行うことは、決して難しくはありません。
まずは、『労働者の心の健康の保持増進のための指針』(厚生労働省)を参考にできるところから取り組んでみましょう。特に”ハラスメント対策”と”メンタルヘルス不調者を想定した休職や復職の規定”については、対応が必要になることが多いですから、社内規定や対応フローを整えておくことをおすすめします。
(1)ハラスメントへの対応
“仕事(取引)や成果に関すること以外での不平等さ”がハラスメントとなる場合が多いとされています。まずは、ハラスメント予防のため、組織のトップからメッセージを発信しましょう。そのうえで従業員アンケートなどで実態を把握し、就業規則などに規定を設けてください。教育研修も効果的です。
もしハラスメントの訴えがあったら、関係者に配慮しながら聞き取り調査を行い、会社としての対応を検討します。具体的には、事実関係の確認、被害者・行為者双方に対する適切な措置、再発防止措置の実施です。具体的な取り組み例、社内規定、文書のひな形などについては、「あかるい職場応援団」という厚生労働省のホームページに資料がありますので、活用しましょう。
【参考】ハラスメント関係資料ダウンロード / 明るい職場応援団(厚生労働省)
ハラスメントの調査のときに留意するポイントは、元々メンタルクリニックに通院中であるなど、ハラスメント以外に体調不良の原因がある場合も想定することです。ご病気の影響(疾病性)があり、対応に迷う場合は、これからでご紹介する社会資源の利用をおすすめします。
ハラスメントの訴えが起こる職場では、メンタル不調者が続出する、退職者が増える、など、会社にとっては大打撃です。 安心して働ける職場は、働く人が能力を発揮するために欠かせません。また、次に解説する精神障害の労災に関しても、ハラスメントは大きく関わってきます。
【もっと詳しく】中小企業のハラスメント対策、具体的に何をすればいい?
(2)精神障害の労災認定
もし、職場のハラスメントなど、業務により精神障害を発症した(もしくは悪化させた)ということになれば、企業が責任を問われる可能性があります。具体的には、労災申請や損害賠償請求、などです。精神障害の労災認定は年々増加しており、他人ごとではありません。ハラスメントがあった、半年間を平均して月80時間以上の残業があった、明らかな業務の負荷があった(トラブル対応があった等)があてはまると「業務が理由で健康障害が起こった=労働災害ではないか」と言われるリスクがあります。この点について詳しくお知りになりたい場合は、精神障害の労災認定(厚生労働省)をご参照ください。
精神障害の労災を防ぐためには、(1)でご説明したハラスメント対策の他に、長時間労働の是正、中程度以上の業務の負荷がかからないようなマネジメントなど、包括的な取り組みが重要です。
【参考】令和2年度「過労死等の労災補償状況」を公表します / 厚生労働省
(3)休職・復職の規定
「業務上の理由でのメンタルヘルス不調ではなさそうだ」という場合、もし仕事を休むのであれば、”私傷病による休職、あるいは欠勤”となります。休職か欠勤かは、就業規則の取り決めによります。
就業規則の休職に関する項目はどうなっていますでしょうか? 以下のような事項が就業規則や休復職の規定に定められておらず、場当たり的に対応するのは、トラブルの元です。
・どのような場合に休職になるのか?
・休職中の取り決めは?
・復職までの流れのルールがあるか?
また、休復職に関するよくあるご相談としては、次のようなものがあります。
・体調が悪くパフォーマンスが落ちており、会社としては休んで回復してほしいが本人は休みたがらない
・休職中に連絡が取れなくなる(診断書が提出されなくなる)
・復職した後に、体調不良での休みを繰り返す
このような状況に陥ることを防ぐには、以下の3つが重要です。就業規則や、休職・復職の社内規定で明文化しておきましょう。
①有給休暇で休む場合でも、〇日を超える場合は診断書を提出すること
②復職時、あるいは会社が指定した場合に産業医面談を受けてもらうこと
③復職後に体調不良が起きた時のルールを決めておくこと
【もっと詳しく】曖昧な休職ルールはNG。メンタルヘルス不調者に対応する就業規則のポイント
会社に産業医がいない*場合、特に復職時は地域産業保健センターを活用し必ず産業医資格を持つ医師による面談を設定し、報告を受けるようにしましょう。必要に応じて、就業配慮に関する主治医意見を取得することも有用です。地域産業保健センターや産業保健総合支援センターでは、産業医のいない*小規模事業者や労働者に対して、産業保健に関するサービスを無料で提供しています。このように、産業保健のスタッフを活用することで、メンタル不調にまつわる困りごとを予防・解決しやすくなります。
【参考】地域窓口(地域産業保健センター) / 労働者健康安全機構、産業保健総合支援センター(さんぽセンター) / 労働者健康安全機構
まとめ
産業医がいない*企業のために、様々な社会資源が用意されています。より手厚いサポートが必要な場合は、有料となりますが、民間の従業員支援プログラム(EAP)や産業保健スタッフのスポット契約のサービスを提供している企業もあります。上手に活用して、自信を持って、メンタルヘルス対応ができるようになりましょう。
*常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任することが義務付けられています
【こちらの記事も】【よくある間違いも】就業規則の変更が必要となるケースと進め方チェックリスト
【参考】
『労働者の心の健康の保持増進のための指針』/ 厚生労働省
『産業医はじめの一歩:「働く人・企業」のニーズをつかむ!基本実務の考え方と現場で困らない対応』川島恵美・山田洋太著/羊土社
『明るい職場応援団』/ 厚生労働省
『精神障害の労災認定』 / 厚生労働省
『地域窓口(地域産業保健センター)』 / 労働者健康安全機構
『産業保健総合支援センター(さんぽセンター)』 / 労働者健康安全機構
*maruco、Mills、umaruchan4678、Luce、SoutaBank / PIXTA(ピクスタ)