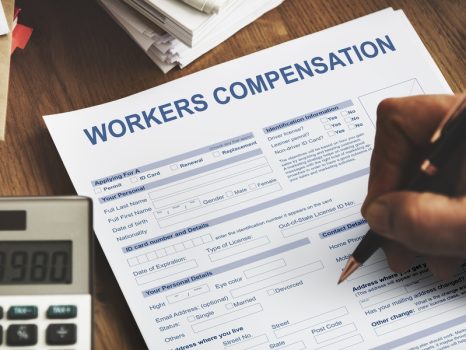2024年10月から従業員数51名以上の企業も対象に!社会保険の適用拡大によるメリット・デメリットや注意すべき点を解説
2020年の年金法の改正により、社会保険の適用範囲拡大が始まりました。この拡大は2022年10月から段階的に進められており、2024年10月には従業員数51名以上の企業にも適用されます。これにより、多くの企業が新たに適用対象となる可能性が高いため、あらかじめ内容の把握と対応について検討しておく必要があるでしょう。そこで本記事では、2024年10月からの社会保険の適用拡大について解説していきます。
目次
2024年10月からの社会保険適用範囲
2020年の年金法改正による社会保険の適用拡大は、すでに2022年10月より従業員数が101人以上の企業において、第一弾が実施されています。
今回の改正では、従業員数が51人の企業が対象です。従業員数とは「フルタイムの従業員数」と「パート・アルバイトを含む、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員」を指し、現在の厚生年金保険の適用対象者に該当します。今回の適用拡大によって対象となる従業員や、70歳以上で健康保険にのみ加入している従業員は含みません。
【こちらもおすすめ】【弁護士に聞く!】社労士はどう選べばいい?自社に合った社会保険労務士の選び方のポイント
適用拡大による新たな加入対象者
今回の適用拡大によって加入の対象となるのは、以下のすべてに該当する従業員です。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金が月額8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
①の所定労働時間については、就業規則・雇用契約書などにより、その従業員が通常の週に勤務すべき時間を指します。③については、最初の雇用契約の期間が2か月以内であったとしても、就業規則・雇用契約書・その他の書面において、雇用契約が更新される、または更新される場合があると明示されている場合も含みます。また、同一の事業所において同様の雇用契約に基づいた雇用者が、契約更新などをされた実績があり、その期間が2か月を超える場合にも当てはまります。
【参考】社会保険適用拡大ガイドブック/厚生労働省
従業員の社会保険加入における、企業側のメリット・デメリット
メリット
メリットは、社会保険の適用により法定の福利厚生が向上するので、仕事へのモチベーションがアップするでしょう。また、社会保険の適用対象となった短時間労働者にとっても、安心して働くことができる魅力的な職場に映ります。その結果、従業員の採用率が向上し、離職率の低下が期待できるはずです。
デメリット
一方でデメリットとして、健康保険料を従業員と折半することになるために企業側に負担が増える点が挙げられます。また、社会保険の手続きや管理には、一定の事務作業が伴うため、管理業務も増加します。さらに、扶養内で働きたい従業員にとっては保険料が負担となり、離職の申し出がある可能性もあります。
社内準備のステップ
厚生労働省では、社会保険適用拡大にあたり次のようなステップを推奨しています。
STEP1:加入対象者の把握
今回の適用拡大の要件である従業員数が51人以上に該当するかを確認します。該当する場合には、上記で述べた4つの要件と照らし合わせて、加入対象者がいるかどうかを確認しましょう。
STEP2:社内周知
加入対象者に該当する従業員に対して、周知を行います。
STEP3:従業員とのコミュニケーション
加入対象者に該当する従業員に対して、個別に面談を実施します。この面談では、社会保険・厚生年金への加入により保険料が控除され、手取りが減少するというデメリットを伝えることが大切です。それだけでなく、健康保険として傷病手当金・出産手当金の支給を受けられるなどのメリットも伝えましょう。メリット・デメリットを踏まえて、今後加入対象者となる従業員がどのような働き方を希望するのか確認します。
STEP4:書類の作成・届出
2023年10月から2024年7月までの間に、6か月以上従業員が50人を超えたことが確認できた企業・事業所には、日本年金機構から9月上旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。加えて、10月上旬には「特定適用事業所該当通知書」が送付されるので、確認してください。該当する短時間労働者がいる場合には、「被保険者資格取得届出」を作成して10月7日までに届け出ましょう。
【参考】年金Q&A/日本年金機構
【こちらもおすすめ】【社会保険手続きも】もう役所に行かなくてOK!「gBizID」でできる電子申請を徹底解説
経営層が注意すべき点
企業負担の保険料を試算する
経営者が注意すべき点としては、まず企業負担分の保険料の増加が挙げられます。企業にとっては単純なコスト増であるため、早めに試算しておきましょう。厚生労働省の社会保険適用拡大の特設サイトでは、簡単なシミュレーションができるので、参考にするとよいでしょう。
対象となる従業員の意向を尊重する
社会保険の適用には従業員にメリットがありますが、手取り金額が減少するため、「社会保険の適用を受けたくない」という従業員もいるでしょう。加入対象にならないような働き方への変更希望があるにもかかわらず社会保険への加入を進めると、かえって当該従業員の退職を招く可能性がありますので、従業員の希望を尊重することが重要です。
まとめ
今回の社会保険の適用拡大は予定されていたものではありますが、かなり多くの企業が対応に迫られることになります。社会保険の適用は従業員の家計にも影響することなので、早めに対応の要否を検討し、従業員としっかりコミュニケーションを取りましょう。
*Monster Ztudio, Indypendenz, Andrey_Popov, chaponta, metamorworks / shutterstock
【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら