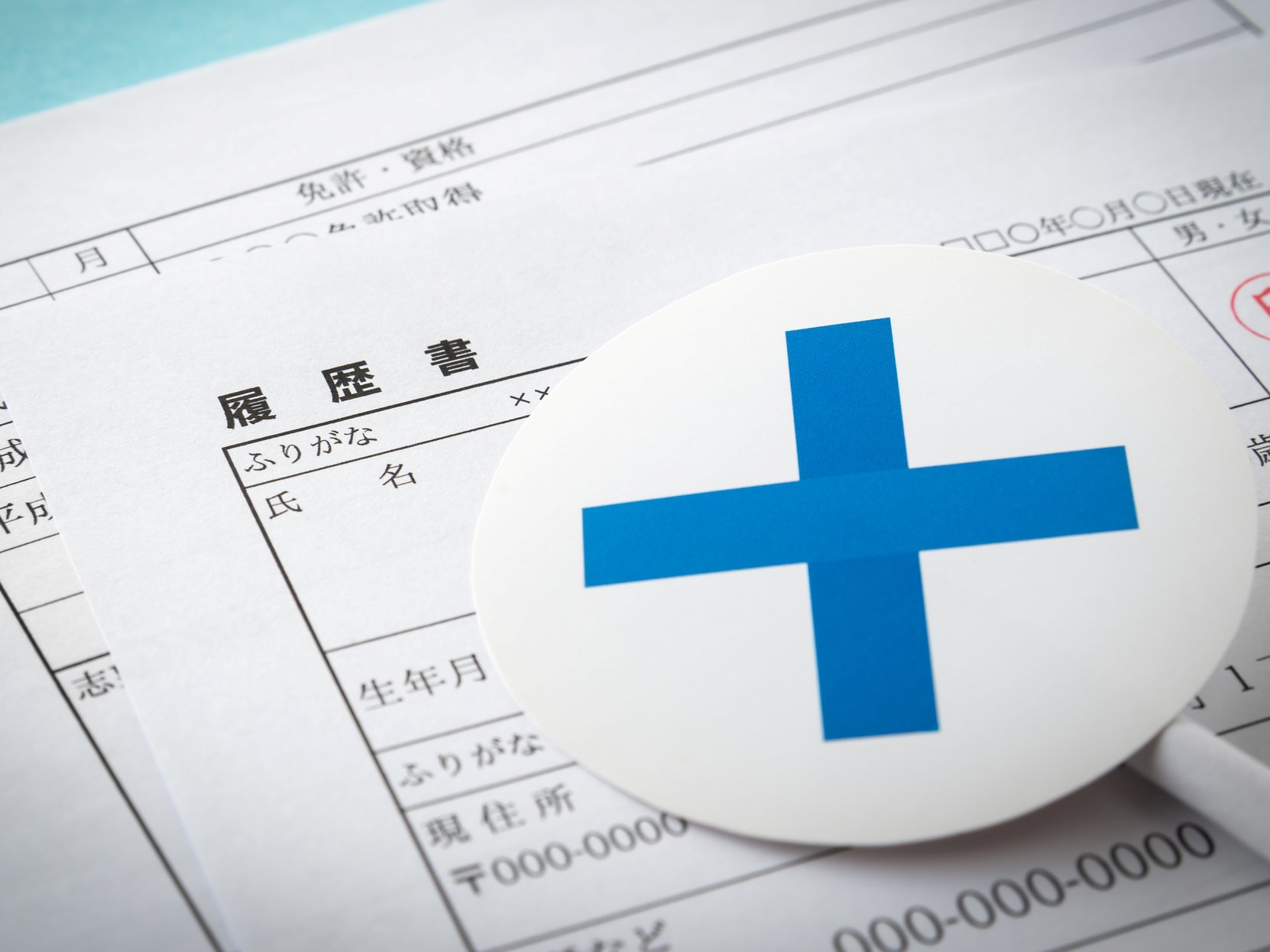
面接と話が違う…経歴詐称の社員は解雇できるのか?未然に防ぐ対策を解説
多くの企業が4月入社を実施している関係で、毎年5~6月頃になると、「前職の経歴から能力を期待して採用したが、期待外れだった。職歴詐称で解雇できないか」といった相談が多く寄せられます。実際に求職者が意図して職歴詐称を行っていなくても、企業側と能力的なミスマッチが起こることで「詐称したのでは」と感じることもあります。そこで、今回は社員の職歴詐称に対する解雇について解説していきます。
目次
職歴詐称とは
「職歴詐称」とは、法律上の定義はありませんが、求職にあたりこれまでの就職経歴や役職、担当していた業務内容などについて、虚偽の事実を申告することを指します。
ライトアーム株式会社が2021年6月に公表した「採用におけるリファレンスチェック」の実態調査結果によれば、本人が申告した経歴と実際の経歴が詐称されていたという経験の有無について、13.9%の経営者が「非常にある」と回答しており、32.2%の「少しある」と35.6%の「あまりない」を含めると、職歴詐称を経験している企業は8割以上になります。
職歴詐称はどのような罪になるのか
職歴詐称を行ったとしても、それ自体で刑事罰の対象にはないでしょう。対象にならないとしても、企業側からは以下のような措置が行える可能性があります。
・内定の取消
・本採用拒否
・懲戒解雇などによる解雇
・その他懲戒処分等の不利益な措置
職歴詐称が発覚した際、解雇できるのか
職歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇などを行える可能性はありますが、いかなる場合でも解雇できるわけではありません。
裁判例上、労働者の資質、能力の評価はもともと企業側の責任とリスクを負うべきものであるとされ、経歴詐称があっただけではなく、これにより「その資質、能力に対する適正な評価、判断を誤らせ、そのために、企業の賃金その他労働条件の体系を乱しあるいは適正な労務配置を阻害するなど企業秩序を現実に侵害した場合でなければならない」とされています(日本農薬事件・佐賀地裁昭和51年9月17日)。
したがって、「職歴詐称があった」ということにより信頼関係が失われるという点のみではなく、それにより企業秩序にどのような影響があったかがポイントとなります。職歴詐称という会社を欺く行為があったとしても、問題なく仕事を行っているのであれば、解雇をするのは相当ではないということです。
懲戒解雇できた例:グラバス事件
職歴詐称を理由とした解雇に関する裁判例はいくつかあります。そのひとつに、職歴詐称があり期待される能力を有していなかったことの懲戒解雇を要件とした事例として、グラバス事件(東京地裁平成16年12月17日)を紹介します。
この裁判例では、開発に必要なJava言語のプログラマーとして採用された者が、プログラミング能力がほとんどなかったにもかかわらず、経歴書にはJava言語のプログラミング経験があるかのような記載をしていました。また、採用時の面接においても同趣旨の説明をしたということで、懲戒解雇を有効としています。
【参考】
日本農薬事件/全国労働基準関係団体連合会
グラバス事件/労働新聞社
【こちらもおすすめ】違法にならず解雇できる?今すぐにでも辞めてほしい「モンスター社員への対応」【所要期間や注意点も】
採用段階でそのような社員の採用を防ぐためにできること3つ
一度採用した人を解雇することはなかなか容易ではありません。採用するか否かを判断する段階においては、企業にも「採用の自由」が認められているため、ある人を不採用とすることは、差別などでない限りは広く認められています。
したがって、基本的な対応策は、採用の前段階でとっていく必要があります。
①面接でしっかりと確認する
まず考えられるのは、面接で能力、資質を見抜くということです。これが基本的な対応となるでしょう。面接で職歴に関する質問をし、円滑に受け答えができているかを確認することです。
とくに、”職歴詐称”というためには、虚偽の事実をエントリーシート等に記載していたり、面接での質問で虚偽の事実を述べていたりと、求職者側から虚偽の事実を積極的に述べていることが必要になります。反対に、いうべきである不利益な事実を述べなかったということだけでは、「職歴詐称」として解雇や懲戒処分などを行うことは難しいといえます。したがって、面接をする側のスキルも重要になります。
②卒業証書、退職証明書、その他資格を証する書類を求める
面接でしっかり確認することが基本的な対応策ですが、それだけでは見抜くことは難しいといえます。
学歴や職歴、資格に関しては、大学や大学院などの教育機関の卒業証書や、前職での退職証明書、その他特定の資格を有していることを示す証明書類の提出を求めることも重要です。また、場合によっては、採用前に試験を実施し、資格審査も一つの手段です。たとえば、エンジニア職での採用の場合、採用フロー上で、業務で使用する言語が書けるかをテストし、レベルを把握すると齟齬が起きにくいでしょう。
③前の職場へのヒアリング
書類の確認によって、形式的に一定の資格を有していることは確認できますが、実際の職務経験まで見抜くのは難しいでしょう。職務経験のチェックで最も有効なのは、前の職場に問い合わせすることです。しかし、実際には個人情報保護法の観点から、回答が得られないことが多いといえます。
【こちらもおすすめ】中小企業の経営者は応募者のここを見るべし!中途採用で「即戦力人材」を見抜く方法
試用期間中の対応がポイント
実際に、職務経験や求めていた能力を有しているかを見抜くことは容易ではありません。日本農薬事件のように、労働者の能力、資質の判断の責任とリスクは本来企業側が負うべきものであり、人を採用する以上、求めている能力と求職者が「有している」と述べている能力とが完全に一致することは稀で、多少の乖離があることは否めないでしょう。
企業側は、そのようなリスクがあるものと理解したうえで、試用期間中に求めているスキルを有しているか否かを見極めることが重要です。試用期間であるからといって容易に本採用拒否が可能なわけではありませんが、企業にとっての機会損失を考えると、早めに対応をしておくことが望ましいといえます。
*kai,タカス,maroke,ilixe48, CORA / PIXTA(ピクスタ)









