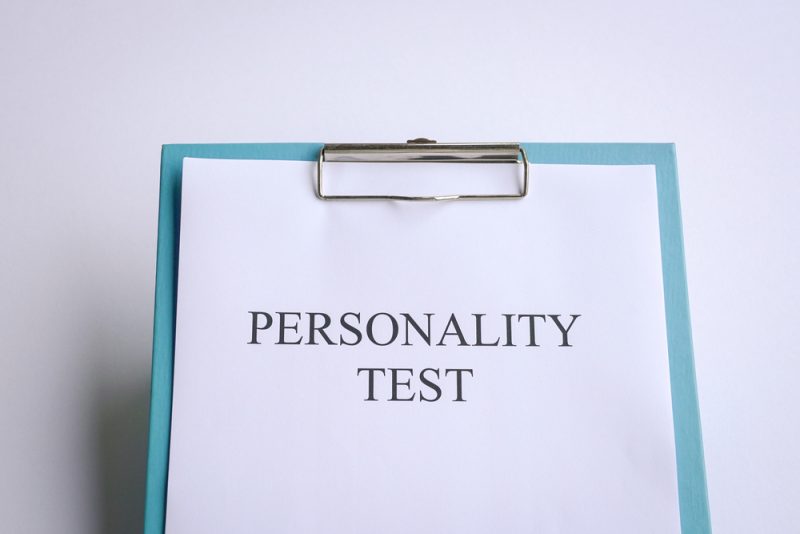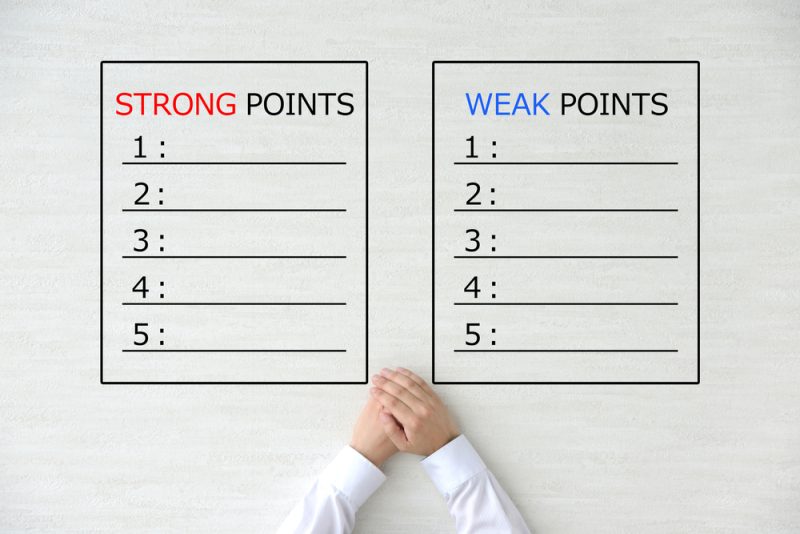
人材育成やマネジメントに活用!おすすめ性格診断ツールとその活用方法を紹介
今、企業の人材育成で注目されている性格診断やスキル診断。診断ツールや関連書籍を見る機会も増えたのではないでしょうか。
客観的な診断ツールを使うことで上司や本人の主観や感情的な視点からの脱却を促し、円滑なコミュニケーションやチーム構成の一助になると注目されています。また、それぞれの個性を尊重しながら、今までなかなか受け入れられなかった相手の言動を理解しやすくなるなど、人間関係にも効果を発揮しています。
今回は、性格診断でわかることやおすすめの性格診断ツール、性格診断の適切な活用方法を解説します。
目次
性格診断で何がわかるのか
性格診断やスキル診断では当人の強みや弱み、思考や判断の傾向がわかります。たとえば、慎重派でコツコツ積み上げていくことが得意な人もいれば、アイデア出しやクリエイティブな仕事に向いている人もいます。リーダーシップの高い人もいれば、ナンバー2のようにリーダーを支えることで強みを生かせるといった人もいます。
挙げればきりがありませんが、みんなそれぞれの傾向があるので、何がよくて何が悪いかよりも個々のよいところや強みを組織でどう生かせるかを客観的に知るきっかけになるといえるでしょう。
また、当人が気づいていない傾向を知るきっかけになるというメリットもあります。「自分では饒舌で人とのコミュニケーションは得意」だと思っている人でも、実際には「きっと周りにそのような“自分”を期待されているだろう」という潜在的な意識のなかで行動していて、そこにストレスを感じていることも性格診断から導かれることがあります。
当人も客観的に自分の傾向を知ることで「いわれてみたら、子供の頃からそういう部分があったかもしれない」「そういわれると、学生時代の頃にこんな出来事があったな」などのように、気づきと思考を深堀りするきっかけになることも多々あります。人材育成だけではなく、自分自身を知るきっかけとして就職活動や採用時にも活用するメリットは高いのです。
【こちらもおすすめ】人材が育たない?課題解決の本質は「課題把握」にあり
性格診断おすすめのツール
たくさんあるツールのなかで「抵抗感なく」「コミュニケーションの一助」として利用できるという点でおすすめのひとつが『16personalities』です。簡単な質問に答えるもので、16パターンの診断結果を得ることができます。また診断でパターンが決まったら、それをさらにエネルギー・意識・気質・戦術・アイデンティティなどの項目で細かく分析してくれます。
たとえば、「エネルギー」だと外向性100~内向性100という幅があり、「気質」だと思考100~感情100という幅で診断がでます。タイプは16パターンですが、それぞれのなかにさらに項目があり、100~100の幅でそれぞれの「傾向」が出ます。「あなたはこれ」と決め打ちされるというよりも、タイプは決まってもそのなかに「この部分についてはこの傾向が強く出ている」という傾向に重きを置いた診断結果がでるため、思考するきっかけとしての効果が望めると思います。
「あなたはこのタイプ」という決定で診断が終わってしまうと、人は「いや、これはちょっと当てはまらないな」や、「所詮、診断だから」というように、どこかで反発したり斜めに見てしまう部分は一定あるかと思います。しかし、本診断ツールはあくまでも「傾向」を知るという要素が強いので、「たしかに私にはそういう一面があるかも……」と考えるきっかけになり、それをテーマにしたコミュニケーションが確立しやすいでしょう。
【こちらもおすすめ】コーチングとは?社員と会社のエンゲージメントも高めるためには
診断ツールで終わらない、活用方法3つのポイント
人材育成を効果的に行うために「性格診断ツール」をご紹介しましたが、ただの診断で終わらせない「育成につなげる」ポイントが3つあります。それが以下です。
・診断結果の性格で確定ではなく、変わるきっかけと考える
・性格診断で褒めポイントを見つける
・何よりも本人の思考を深めることに重点を置く
診断結果は「変わるきっかけ」にすぎない
性格というものは、幹はあっても枝葉の部分や価値観については人生とともに変化するものです。学生時代から新卒で入社した会社での経験や職種、また役職が上がるなどの経験によって価値観は常にアップデートしていきます。その人の本来の性格、たとえばプライベートは変わらないとして、「仕事に向かう自分」は変化していく。そうすると、診断ツールはあくまでも「変わるきっかけ」にすぎないということです。
会社や管理職者の立場からしたら、診断をして社員や部下の傾向が分かれば育成しやすい、ある意味安心するかもしれません。しかし、ここをゴールにしてしまっては逆に窮屈で成長を妨げる危険性もあります。たとえば傾向が出たところで、社内の人間関係について言及していきましょう。質問例として、「自分の傾向に似ているなって思う人いる?」や、逆に「思考の傾向が強いって出ているけど、逆に感情傾向が強いなって感じる人いる?」と聞いてみてもいいかもしれません。ちょっとした会話のなかで本人が潜在的に抱えている人間関係の課題が見つかることがあります。
また、チームのメンバーとゲーム感覚で試してみてもよいでしょう。それぞれのパターンを開示し、項目一つずつを出し合ってみるのも「お互いを知る」きっかけになります。相手を認めることによって、よりよいチームづくりの一助になるでしょう。ただ、複数人で行った場合にはどうしても発言の多い人、少ない人、主張する人、相手に合わせる人など、そもそもの傾向が先行してしまうリスクがあります。こうなってしまったら、発展性がありません。誰に発言させ、議論として深めていき、どこに着地させるか。これはファシリテーターの力量が非常に求められる部分です。
まずは、個人ごとに行い、そこからチームに発展させるのがよいでしょう。
性格診断で褒めポイントを見つける
さらに、上司から部下への面談や育成の場では「褒めポイント」を探すツールとして使ってほしいと思います。「ほら、こういう部分あるよね~」と部下を指導しようとするのではなく「ああ、だからあのときこういうナイスフォローしてくれたんだね」とか「この傾向って仕事でもこういうところでチームに役立っていると思うよ」というプラス評価部分を活用することで、「上司が自分を理解してくれている」と感じ、今後の指導もより効果的になっていきます。ツールをツールで終わらせないためには、上司の資質が問われていることを忘れてはいけません。
本人の思考を深めることに重点を置く
何よりも本人の思考を深めることに重点を置いてください。会社や上司が理解した気になってはいけません。性格診断は、あくまでも自己分析の思考を深めるためのツールです。本人が自分自身を見つめ直したり、気づかない自分のよさに気づいたりすることが重要です。社員本人と行う面談を徹底的なサポートの場と捉え、「聞く・問いかける・共感する」ことが、本人の変化や成長につながります。会社や上司は本人を変えることはできません。仕事に向き合う姿勢を変えられるのは本人自身であるという意識が最も大事なのです。
ぜひ、貴社でも活用してみてください。
*BongkarnGraphic, takasu, Sinseeho, chaponta / shutterstock
【まずはここから】無料オフィスレイアウト相談はこちら(移転・リニューアル・働き方改革)