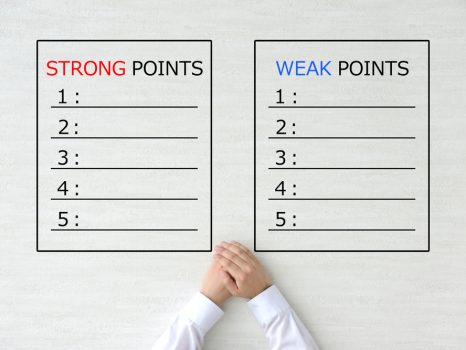形骸化したストレスチェック…産業医が有効な活用方法を解説します
2014年の労働安全衛生法改正により、常時50人以上の従業員を抱える事業者でストレスチェックが義務化されました。しかし、「年に1回実施するだけで、活用の仕方がわからない」「メンタル不調を減らすためには役に立っていない」という声がよく聞かれます。
しかし、一見役に立っていないようなストレスチェックもうまく活用することで、従業員が一人ひとりのセルフケア能力を高めることや、職場としてメンタル不調のアラートを感知し予防することに役に立てることができます。
今回は健康経営や人材資本経営の一歩として、ストレスチェックを効果的に活用する方法や、ハイリスク者への対応方法を解説します。
【参考】2014年の労働安全衛生法改正/厚生労働省
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェックは、“心理的な負担の程度を把握するための検査”とも呼ばれ、主な目的は、①労働者自身のストレスへの気付きを促進すること、と、②ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることです。
「職業性簡易ストレス調査票」が用いられることが多く、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポート(ストレスを緩衝する要因)の3つの要素に関する質問が含まれます。
【参考】
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針/厚生労働省
職業性ストレス簡易調査票(57 項目)/厚生労働省
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等 /厚生労働省
【こちらもおすすめ】従業員数が50人になると変わる義務は?障害者法定雇用率・ストレスチェック・定期健康診断
ストレスチェックは現場の声を集められているのか
従業員の方からは、「ストレスチェックは面倒なので、適当に答えている」「悪い結果が知られると、人事に影響するのが心配」という声を聞くことがあります。数十問の質問とはいえ、忙しい中で回答するのは負担であるため、どのように活用されているかわからなければ、回答するモチベーションが下がるのは理解できます。ただ、回答率が悪いと、集団分析の結果の妥当性が下がったり、ハイリスク者に気づきにくくなったりと、せっかく実施した意味が薄れてしまいます。
それでは、どのようにすれば、ストレスチェックの回答率を上げ、率直な回答を得られるのでしょうか。まずは、ストレスチェックの目的を知ってもらい、「職場の環境改善のために協力しよう」と思ってもらえることが重要です。
また、情報の共有範囲を気にされる方が多いため、実施者と実施事務従事者という限られた人間しか結果を見ることができず、人事や評価に関わることがないということも周知して、安心して受けてもらえるようにしましょう。
たとえば、個人の結果を見ることができる人は人事権がなく守秘義務を負うことを周知することや、人数が少ない部署については集団分析をしないなど、個人が特定されないようにする配慮は必ず必要です。
ストレスチェックを活用する方法
①高ストレス者は面談を希望しないこともある
ストレスチェックでは、高ストレス者に面談の勧奨を行い、希望者には医師による面談を実施することになっています。ただ、高ストレスに該当した中で面談を希望する人の割合は高いとはいえず、必要な人に届いているとはいえません。
通常、高ストレス者の面談ではストレスの要因の聞き取りだけでなく、ストレス対処や睡眠に関するアドバイス、医学的なアセスメントに基づいて受診が必要な際の情報提供などを行います。早めに高ストレス者に対応することで、休職や退職が発生するのを防げる場合もありますので、面談を申し出やすい工夫をしましょう。
たとえば、「ストレスチェックの結果からすると面談をするほうがよさそうだが、本人が希望しない」という場合には、長時間労働者の面談や健康診断の事後措置の一環として、まずは医療職に相談できる機会を設けることも一つの方法です。
また、面談でハラスメントや過重労働の事実が語られる場合もあります。そして、「自分が話したと知られたくない」という方は多いものです。現場に還元することは大事ではありますが、本人の同意が得られない場合は、誰が発言したかは知られないようにして、産業医から人事担当者や経営層に情報提供をする場合もあります。
ハラスメントについては、ストレスチェックとは別のルートでも相談窓口を設け、不利益にならない形で相談しやすい体制を整えておくことが重要です。
②集団分析の結果の活用が肝心
「集団分析結果をどのように活用していくか」がストレスチェックの肝といっても過言ではありません。よくない例としては、実情と照らし合わせて「この部署が高ストレスなのは仕方ないよね」という感想で留まるような部署別の“成績表”のように使われてしまう場合です。
部署のリーダーの職場環境改善へのモチベーションを保つためにも、部署別の結果は個別にフィードバックするなどの配慮が必要でしょう。
集団分析結果の分析の一つに、「総合健康リスク」があります。“量 ‐ コントロール”と“職場のサポート”から判定され、100を平均として、数字が大きくなるほどストレスの高い職場であることを意味します。数字で出るため、比較がしやすいのですが、数字だけでなく、どうしてそういう結果になっているのか、実情と合っているか、そして、どのような変化が起これば数値が改善するか、という効果測定のためにうまく利用するのが大切です。
人を増やして過重労働が緩和される、あるいは、管理職研修などによりサポート機能を強化するという取り組みが数字に反映されると、会社全体のモチベーションも上がるでしょう。
また、集団分析結果として、高ストレス者の割合や、休職者の発生件数、離職率などが併せて考察されやすいですが、個人要因に偏り過ぎず職場の状況を把握する指標としては、総合健康リスクは使いやすいものです。
【参考】これからはじめる職場環境改善/厚生労働省
③職場環境改善の機会を設ける
次に、集団分析結果の活用法の一つに、職場環境改善があります。「職場のここを変えたらいいのに」「仕事の手順でこう工夫すればもっと楽になるのに」というアイデアを持っている方はたくさんいらっしゃいます。その声をうまく拾い上げ、優先順位をつけて環境改善するためのツールです。厚生労働省からは、職場環境改善のワークショップを実施するためのツールが無料で公開されています。
実際に、職場の環境の改善について意見を出し合うだけでも、「自分の意見を伝えられる場所がある」「ほかの人が何を考えているか知ることができる」とメンタルヘルスの向上に役立ちます。もちろん、すべての職場環境改善アイデアがすぐに実現できるわけではありませんが、コミュニケーションの活性化につながります。
職場環境改善とは、メンタルヘルスに関わる部分だけでなく、作業環境や作業手順などの仕事の進め方も含まれます。作業をより効率的にすること、物理的な環境も含めて快適な職場をつくることも、メンタルヘルスに寄与します。
【参考】職場環境改善ツール/厚生労働省
【こちらもおすすめ】働きやすいオフィスは「社員全員」でつくる!オフィスカイゼン活動の進め方とは
最後に
今回は、ストレスチェックの意義と、結果の活用法について解説しました。特に中小企業では、実施するだけで精いっぱいで、結果の活用まで手が回らないという実情があるかもしれません。
ただ、従業員のストレスについて、職場環境について、たくさんの情報が得られるツールですから、活用しないのはもったいないことです。ストレスチェックは毎年実施することから、効果検証もしやすくなっています。ぜひ「やりっぱなし」「受けっぱなし」のストレスチェックにせず、取り組みやすいところから、活用してみてください。
【こちらもおすすめ】実は経営者も知らない?従業員の健康管理に必要な「産業医」ができること3つとは
*KY, タカス, metamorworks / PIXTA(ピクスタ)
【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら