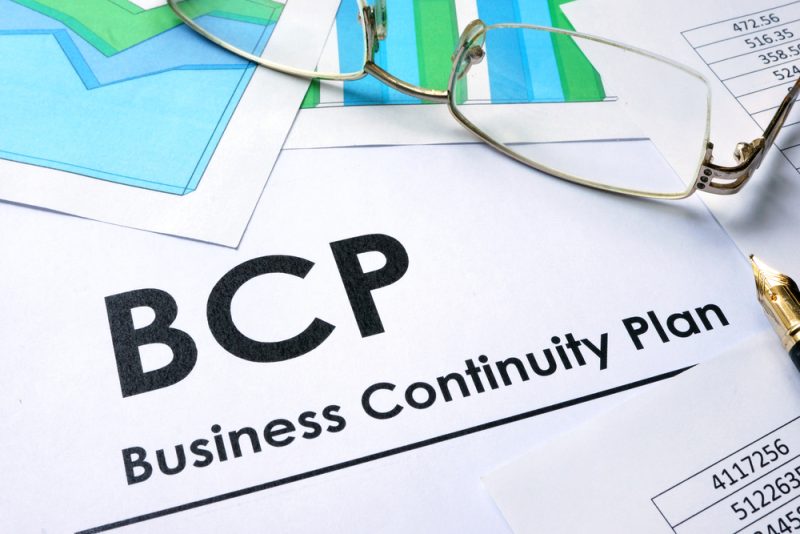あなたの会社は大丈夫?社員の命と企業を守るために防災マニュアルを作成しよう
2024年1月1日に発生した能登半島地震。最大で震度7の揺れを観測しました。石川県では、2024年2月28日の時点で、死者数は241人、住宅へ被害は7万4,792棟となっています。
企業にとっては、社員や資産を守り、災害に備えることは重要です。また、災害の影響を最小限に抑えるためには防災マニュアルの整備が不可欠です。本記事では、命と企業を守るために防災マニュアルを作成する重要性と具体的な手順について解説します。
【参考】令和6年能登半島地震による被害等の状況について(危機管理監室) / 石川県 危機対策課
目次
安全配慮義務、防災マニュアル、BCPそれぞれの関係とは
防災マニュアルの作成に移る前に、まずは安全配慮義務、防災マニュアル、BCPそれぞれの関係について解説していきます。
一度大きな災害が発生すると、社員の出勤困難や交通の寸断、水、電気などライフラインへの影響、そして企業の生産や消費者の消費活動にも影響が出ることが考えられます。
企業には「社員の安全配慮義務」があるほか、経営者にとって災害が発生しても事業を継続するためのBCP(事業継続計画)の作成は重要となります。まずは、社員の命を守るための安全配慮義務と防災マニュアルが確保された後、重要な事業を継続していくための事業継続計画(BCP)を策定されるべきです。
このあと解説していきますが、BCPは、事業継続性を確保し、災害や緊急事態が発生した際に事業活動を継続するための計画であり、安全性が確保された環境での事業活動の継続を支援するものであります。
こうしたことから、BCPは安全配慮義務と防災マニュアルが整備されたあとに着手しましょう。
おさらいとして、企業の安全配慮義務とBCPについて具体的に解説していきます。
おさらい:そもそもBCP(事業継続計画)とは
防災マニュアルについて説明する前に、BCPについて解説していきます。
BCP(Business Continuity Plan)とは事業継続計画のことをいいます。
近年、南海トラフ巨大地震や首都直下地震といった大規模地震の発生が予想されていたり、台風や豪雨災害の発生、感染症のまん延など、企業の存続を脅かすようなリスクが多様化しています。このため各企業において、災害時に重要な業務を継続するため、BCPの策定・運用が求められています。
大地震などの自然災害、感染症のまん延、テロなどの事件、大事故、サプライチェーンの途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順などに加え、被害やその影響を小さくする事前対策などを達成するための計画です。
事業継続を脅かす問題にはさまざまありますが、そのなかでも災害時に企業に求められる対応が「社員の安全確保」、「二次被害の防止」、「事業の継続」などです。
災害発生後、スムーズに事業を継続させていくためには、やはり災害前から防災マニュアルを作成しておき、スムーズに対応することが求められます。
【こちらもおすすめ】企業が被災したら!? 『BCP(事業継続計画)』で重要となる「安否確認」の必要条件とは
企業の安全配慮義務
企業には社員の安全を守る義務があります。それが「安全配慮義務」です。
労働契約法第5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。法律で定められている以上「安全配慮義務」は、経営者として看過できない重要な義務になっています。
災害時も例外ではありません。勤務中や、通勤中、出張中に災害に巻き込まれる可能性もあります。
過去の例をみると、東日本大震災の津波で犠牲になった自動車教習所の教習生らの遺族が、教習所側に損害賠償を求めた訴訟で、安全配慮義務に違反したとして、19億円を超える賠償を命じたこともあります(控訴審により、解決金と陳謝を条件に和解が成立)。
このように、企業が安全配慮義務を怠ることは訴訟問題にも関わってくるといえます。災害時に適切な行動をとるためにも、防災マニュアルをはじめとしたBCPの策定の重要性がうかがえます。
【参考】労働契約法第5条 / 厚生労働省
【参考】宮城の津波26人死亡、教習所に19億円賠償命令 仙台地裁 / 日本経済新聞
防災マニュアルの必要性
皆さんの会社では「防災マニュアル」は用意されていますか? そもそも本当に防災マニュアルが必要かどうかわからないと悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
内閣府の「令和3年度の企業の事業継続及び防災の取り組みに関する実態調査」によると、企業のBCP策定状況は、大企業で70.8%、中堅企業で40.2%となっています。つまり、大企業を中心に災害時に備えたBCPの策定は比較的進んできている一方で、中堅企業に関しては半数に満たない状況となっており、まだまだ災害発生時の対応策が立てられていないといえます。
BCPを策定したきっかけとしては、「リスクマネジメントの一環として」「親会社・グループ会社の要請」「企業の社会的責任の観点から」という項目が上位3つとなっています。
災害時に社員の命を守ることはもちろんですが、事業を継続させることも経営者に求められていますので、防災マニュアルをはじめとした計画の策定は、待ったなしの責務といえます。
では、実際にはどのようなポイントに注意して防災マニュアルを作成したらよいのでしょうか。
【参考】令和3年度 企業の事業継続及び防災の取り組みに関する実態調査の概要①② / 内閣府
防災マニュアル作成のポイント
それでは、実際に災害が起こった際に、自社や社員を守るための「防災マニュアル」の作成について一緒に考えていきましょう。
一番に大切なのは、社員の命と安全を守ること、そして事業を継続していくことです。作成のポイントを以下にまとめました。
①社員の命を守る防災を整備する
生命の安全確保を最優先に
全員が命を守る行動をとる、安否確認ができるように部署ごとにマニュアルを整えておきましょう。また、災害発生に備えて、避難経路の確保や耐震補強、什器の耐震対策の実施も進めておくべきです。
備蓄の確認
ライフラインの停止や帰宅困難者の発生に備えて、社員の人数分の水や、食料、簡易トイレなど生活用品の備蓄を整備しておきましょう。
目安として最低一人3日分の備蓄を用意することをおすすめします。備蓄倉庫などに余裕がある場合は1週間分の備蓄を用意するのが望ましいといわれています。
災害発生時の対応をまとめておく
地震などの災害時に、どのように行動すればよいのか対策本部を設置して対応するほか、対策本部は、明確に指示が出せるようにそれぞれの部署の責任者が担当の中心となるとよいでしょう。
また、あらかじめ災害を想定した訓練をしてきましょう。地震を想定した訓練を行うときには「リーダー、情報担当、消火担当、救出担当、避難誘導担当」などと部署ごとに分けて行ってください。担当を決めておくと、いざというときにとるべき行動が見えてきます。
事業所近郊で地震が発生したことを想定して、実際に訓練してみることが社員の命を守ることにつながります。
②BCPを策定する
重要業務を特定する
災害発生後は社員や施設、インフラなどが被害を受け、機能するものが限られることを認識したうえで、最優先に取り組むべき業務を決めておきましょう。
目標復旧時間・目標復旧レベルを定める
いつまでに業務を復旧すれば「顧客との取引を維持できるか」、「会社が破綻しないか」などの視点で設定しておきましょう。
取引先とあらかじめ協議しておく
いつまでに、どこまでの製品やサービスを提供できるかについて取引先と共通認識をもちましょう。
電話やメールなど普段の連絡手段が使えない場合も想定し、連絡方法を決めておくことをおすすめします。
事前対策や代替案を用意しておく
重要業務にかかる資材などについて、災害時でも利用できるよう事前に対策を打つほか、代替策を用意しましょう。
社員とBCPの方針や内容について共通認識を持つ
緊急時に経営者はどう行動するか、社員にどう行動してほしいかを事前に話し合い、決めておきましょう。
緊急時の行動計画を社内へ浸透させるには、経営者自らが災害へのリスクを理解し、社員に繰り返し伝えることが第一歩です。
部下に任せておくだけでなく、自ら防災の意識を高めていくことが社員の命、また会社を守ることにつながります。
防災マニュアルがすぐに整備できない場合
いざ防災マニュアルやBCPを策定しようと思っても、仕事に追われて後回しにしてしまい本格的なマニュアルをつくる時間がないということもあるかもしれません。
その場合、社内で共有しておきたいのは災害が発生した際に社員全員が安全に避難できるような対策です。社内の避難経路の確保や避難場所といった最低限の情報は明確にしておきましょう。
計画は一日にしてならず
防災マニュアルやBCPの策定については、経営層の理解なしにすすめることはできません。まずは経営層から声をあげ、社員の命と企業を守るために考えてみましょう。
また、防災マニュアルをはじめとした計画の作成は誰に任せたらよいのか迷われるかもしれません。筆者が以前働いていた会社では総務課が作成をしていましたが、理想としては一度社内で話し合って決めることをおすすめします。
マニュアルや計画は策定して終わりでは意味がありません。策定したあとに、担当者や組織全体で定着させるために、訓練、演習を計画し、継続的に実施することが重要です。
【こちらもおすすめ】社員と会社を守る「企業防災」とは?まず取り組むべきファーストステップ
防災マニュアル作成のための参考資料
今すぐ作成をはじめられる防災マニュアル作成例として、東京都港区が紹介している「事業者向け作成マニュアル」を紹介します。
このマニュアルは、中小企業がはじめてBCPを策定することを想定して作成してあるので、ポイントがわかりやすくまとめられています。テンプレート方式で入力ができるので、どこからはじめたらよいかわからないという経営者の方におすすめのマニュアルです。
災害発生時に向けた第一歩、ここから踏み出してみませんか?
【参考】港区事業所向け防災マニュアル / 港区ホームページ
*Vitalii Vodolazskyi, MMD Creative, metamorworks, THICHA SATAPITANON, CrizzyStudio / shutterstock
【まずはここから】オフィス移転・改装・レイアウトお問い合わせはこちら