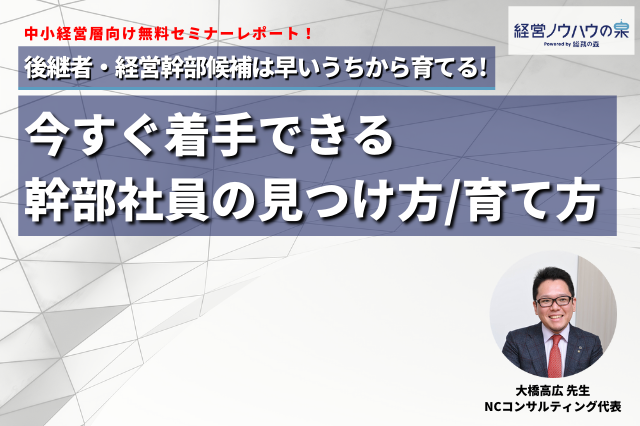【新規事業】成功の秘訣ここにあり。アサインから兼務マネジメントまでを徹底解説
筆者の経営コンサル業としての得意領域であります、地方創生活動において積極的に身の丈にあったDX化を皆さまにオススメ・お手伝いをする機会はどんどん増えております。この活動では単にお客様企業の成果にとどまらず、その経験を地域全体に“お隣様事例”として地域のロールモデルにし、地域全体の経営効率を上げていくということを常に目標に掲げています。
その先に地域の複数の企業で効率化が進むことで、ヒト・モノ・カネの余力が現状よりも少しずつ見え、企業単体から地域全体が徐々に変化していくはずという仮説に基づいています。さらに、その先の狙いとして、その余力を地域で包括的にまとめ、協業による新商品/新商流開発や、新規事業の立ち上げにつなげたいと考えています。
ここで、新規事業の企画立案や、具体的な立ち上げをお手伝いすることが少なからずあります。これまでに、うまくいったものもありますし、うまくいかなかったものもありました。その内、うまくいかなかった典型パターンの一つに“人材の配置”における失敗が多く見られました。よくある相談として、「社内で優秀な人間を配置して新規事業立ち上げを任せたはずなのに、この優秀な人材が機能しなかった。何がよくなかったのか?」という相談です。本日はこの点について最近多くのお問い合わせをいただいておりますので、リスクにはまらないポイントを紹介しようと思います。
新規事業立ち上げの課題
まさに今回のテーマにピッタリの調査結果があります。NTTデータグループのコンサルティングファームである株式会社クニエが発表したレポートです。こちらの調査において、“体制面の影響”について色濃く言及されています。
【参考】新規事業の実態調査レポート ~新規事業の成功確率を高めるには~/株式会社クニエ
1)リーダーの関与度合い
まず大きく影響するのが「リーダーの関与度」です。リーダーの関与度が高いほど成功度合いが高いとの調査結果が出ています。新規事業では、状況把握および判断のスピードにダイレクトに影響するため、想定できない事態が連続して常に発生します。リーダーの判断がリアルタイムで求められる場面が多く、時間調整や判断確認のリードタイムに時間がかかってしまい、事業推進が停滞してしまうのです。そのため、リーダーの関与度は非常に大切でしょう。
調査結果からもリーダーが専任なのか、兼務なのか、それだけで2倍以上の成功度の違いが出てくるとされています。
2)チームの当事者意識
次に、リーダーの関与度と密接に関係が考えられる項目として「チームの当事者意識」が挙げられています。
クニエ社の調査では「顧客理解調査が従前に行われているか」という点と、「社内調整がしっかり行われているか」という点でチームの当事者意識が変わってくると説明されています。ここで言及されている“社内調整”とは「各部門から得られる協力のこと」として述べられています。
もう一歩踏み込んで、兼務で新規事業に参加しているメンバーについて考察すると、元の所属部署での納得が十分に得られていないことが原因で、兼務の状況にあるスタッフに対して元所属部署からの要請が強く残ってしまうため、なかなか新事業に集中する時間を取ることができないという事態をしばしば目にします。これも前項同様、関与度の問題となって新事業に十分な推進力が得られない原因となってしまいます。
一方、別の項目では、メンバーの中に専門家や経験者がいることについては、意外にも「成功度合いにプラスに貢献しないこと」が報告されています。
ここまで整理して考えると、やはり専門性や経験よりも新事業に集中して取り組むことができる体制や、社内の協力が最も欠かせない要素であることが推察されます。
【こちらもおすすめ】組織力をあげる「心理的安全性の高い職場」のつくり方とは?
新規事業の人材選びに重要なポイント
では、ここで重要となるポイントですが、専門性や経験が任用する人材としての重要な項目でないとしたら、どのような人材に担ってもらうのが正しいのでしょうか。
著名な経営コンサルタントであるジェフリー・ムーア氏は自身の著作で、まさに新規事業開発を継続する重要性を説いているのですが、そこで人材の兼務において留意すべきマネジメントスキルについての考え方を提唱しています。
ムーア氏によると、企業のマネジメントは4つのゾーンに分類され、それぞれ必要な能力が異なり、下記のように整理されるそうです。
①インキュベーションゾーン(新規事業の芽を探し出す能力)
②トランスフォーメーションゾーン(新規事業を育成し形作る能力 → パフォーマンスゾーンへの橋渡し)
③パフォーマンスゾーン(屋台骨となる既存事業で成果を出し続ける能力)
④プロダクティビティゾーン(生産性を向上させる能力)
【参考】ゾーンマネジメント 破壊的変化の中で生き残る策と手順/日経BP
とくに、兼務が発生するケースとして多いのは、パフォーマンスゾーンの有能な人材を“期間限定”として、トランスフォーメーションゾーンに兼務で配置する場合をよく見ます。デキる人だからあちらでもこちらでも力を発揮してもらいたいという思いから、そうなってしまうことが多いのでしょう。
しかし、ここで重要なのはパフォーマンスゾーンにいる優秀な人材がまったく新しいことに取り組む場合であっても、先述の通り、新規事業の立ち上げ業務を、既存事業の定常業務とリソースを奪い合いながら対応し続けることは、大きすぎる負担となってしまいかねません。同じマネジメントスキルの中で新しいラインを立ち上げるという話とはレベルが違う議論になってしまいます。
リーダーは専任にする
クニエ社の調査にもあったように、新規事業の担当リーダーは専任として配置することが何よりも重要と考えます。または最低でも既存事業と兼務にする場合は、しっかりとした代行を既存業務に残して副務扱いにするべきでしょう。
新規事業に向いている人材
そして、元々備えている能力として日々の業務をしっかりこなすことに長けている人材よりは、想定外・未知の事象に対して、仮説を設定し検証しながら適切な道のりを定めていくことに長けている人材を任命しましょう。よりトランスフォーメーションゾーンに適した人材を配置することが重要なのです。
経営者のやってしまいがちなミスとして、既存の業務でより成果を発揮している人物を“デキる人材”としてなんでもやらせてしまう傾向があります。クニエ社の調査でも専門性や経験は成功に強く貢献しないことが報告されています。ここはそれぞれのマネジメント層に必要な適性を強くもった人材を見極める眼力を発揮してもらなければなりません。
新規事業の人材選びの注意点
もう一点、気にしておいていただきたい点があります。それは「マルチタスクをこなす能力」は、「単一業務を遂行できる能力」とは、まったく別物であるということです。
我々経営コンサルタントの世界でも、プロジェクトの兼務は相当の経験を積んだ人材でなければ担当させられません。自分の得意な専門領域の検討であっても、複数の事業を同時に進めるのは、非常に難しいものです。兼務業務を任命する際は、最初から難易度が高そうな業務を担わせるのではなく、徐々にマルチタスク能力を育成・確認できるような段階を設定するようにしてください。
複数の業務に同時に目配せできてバランスもうまくとれることが確認できるようになってから、徐々に難易度の高いタスクを兼業できるようになっていくようなケアが必ず必要です。いきなり難易度の高いマルチタスク環境に放り込まれてしまい、なかなかパフォーマンスが出せずに有能な人材が悩んでしまったり、体を壊してしまったりというケースをコンサルティングの現場で数え切れないほど見てきた筆者としては、有為な人材を毀損しないようなマネジメントをお願いしたいと強く思っています。
*EKAKI, studio-sonic, Luce, shimi / PIXTA(ピクスタ)
【こちらもおすすめ】「IT人材がいない、採用も難しい」中小企業が低コストでDXを進めるためには