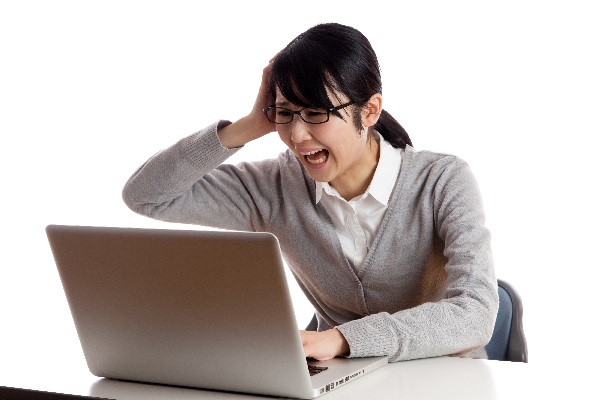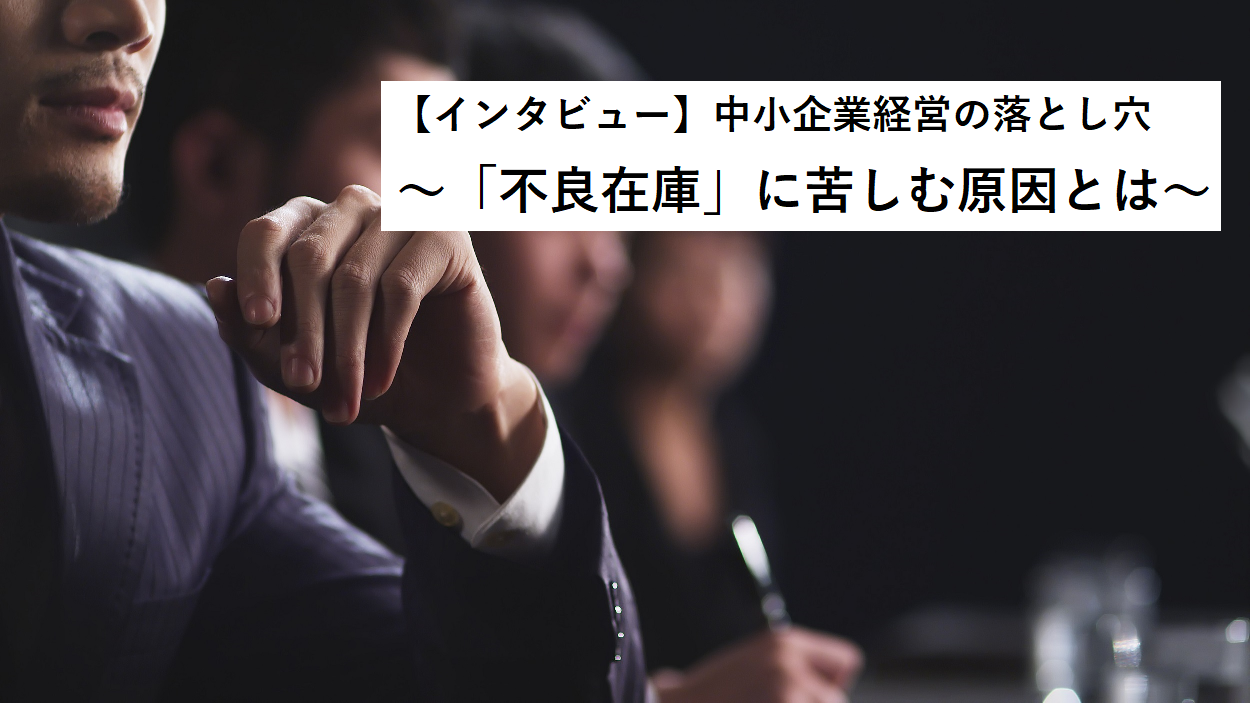営業にノルマは時代遅れ?適切な設定と評価方法を考えてみる
あなたの会社では“ノルマ”という言葉を日常的に使っていますか?営業ノルマ(以下、ノルマ)は営業スタッフにとって頭を悩ませる課題であり、時には厳しいプレッシャーとなります。
とくに最近、ノルマという目標設定の考え方は合わなくなりつつあります。数値目標設定がKGI(重要目標達成指標、企業の目指す最終的な定量目標)として浸透しつつある現代において、「ノルマ=KGI」として捉える方がフィットし、KGIを達成する重要業績評価指標であるKPI、それを支える重要成功要因のKSFを明確にする方が重要なのではないでしょうか。そこで、今回は現代における営業スタッフの適切な目標の設定方法について解説します。
目次
営業がつらい理由「ノルマ」が36.3%
日本労働調査組合が2021年6月に発表した「営業職の退職動機に関するアンケート」調査結果によると「営業職をしていて辛かったこと」という質問に「ノルマ」と回答した営業職が最も多く、実に36.3%の営業職がノルマをつらく感じていることがわかりました。これは2位の「お客様の理不尽さ」「クレーム対応」の8.8%を大幅に引き離して圧倒的な1位であり、営業職の間でノルマがどれだけ負担になっているかが明確に表れています。
【参考】【日労公式】「営業辞めたい」6割弱という結果に。営業職500名へのアンケート調査/日本労働調査組合
そもそも「ノルマ」の定義とは
現代において、営業スタッフの目標を“ノルマ”という言葉で表現することに違和感を持つ方も多いかもしれません。Oxford Languages監修のGoogle日本語辞書によると、“個人や工場に割り当てられた,一定時間内・期間内になすべき生産責任量。第二次大戦後,シベリア抑留者が日本に伝えた語。転じて,各自に課せられた仕事などの量”とされています。
つまり、ノルマとは“義務”であり、それによって評価されるものではないという考え方が根本のようです。変数の多い現在では古典的なノルマ設定が難しいこと、トップダウンだけではない目標設定や成果に基づく評価制度を採用している企業が増えていることなどが、違和感の正体ではないでしょうか。現代において、営業スタッフの目標は、ノルマではない別の指標で考えていくべきなのです。
適切な目標設定・運用法とは
では、どのような営業スタッフの目標を設定すればよいのでしょうか。以下、3つのステップから考えてみましょう。
1)目標達成のためのKGI・KPIを設定する
目標を設定する際には、まずは最終的に達成するべきKGIを設定しましょう。そのうえで、達成のための段階的な指標、すなわちKPI(Key Performance Indicator)を設定することが重要です。営業の場合、目標として「達成すべき成約数」が設定されることが多いでしょう。しかし、成約に至るまでの各段階においてもそれぞれのフェーズに応じた指標が存在するはずです。
たとえば、メール開封数、架電数、リード獲得数、商談数、商談化率などです。いずれも成約の前段階として必要なものであり、KPIとして設定できます。これらのKPIを設定することで、スタッフはどの活動に重点を置くべきかが明確になり、目標達成に向けた具体的な行動を取ることが容易になるのです。
「テレアポ→商談→成約」という営業プロセスの場合、商談から成約に至る割合が算出できれば、成約数の目標達成に必要な商談数がわかります。さらに、テレアポから商談化する割合が算出すると、目標とする商談数に必要な架電数がわかります。成約数を伸ばしたいならば、商談化率を保ったまま、架電数を増やしていく方法が有効です。
このように、各KPIをモニタリングしながら最終的な目標に向かうことで適切な目標の運用が可能となります。
2)本来の能力よりやや高めに設定する
適切なレベルで設定しなければスタッフの負担が大きくなりすぎますが、適切なレベルとは「本人が確実に達成できるレベル」ではありません。最初から確実にできるとわかっているレベルだと、がんばりや創意工夫の余地が少なすぎて成長が促進されないからです。本人のキャパシティよりもやや高め、少しがんばらなければ達成できないレベルに設定しましょう。
3)市場環境が変化したら目標の見直しも検討する
市場環境は絶えず変化するため、新たな競合の出現や経済状況が変動したりすると、営業の現場での状況も大きく変わります。そのような場合、目標を含めて戦略を見直すことも重要です。また、当初の想定通りに達成状況が進んでいない場合には、原因の検証し、見直しが必要になることもあるでしょう。
いたずらに目標を下げると、スタッフのモチベーションも下げてしまいかねません。何が何でも目標を絶対視することも避けつつ、慎重な検討が必要になります。
営業スタッフの評価方法とは
営業スタッフの評価は、単純に業績だけでなく、行動や姿勢を含めた多面的な視点から行うべきです。日本の人事考課では一般的に、業績、能力、姿勢の3つの視点が重要視されます。
1)業績評価
業績評価では、目標達成度など具体的な数字が評価の対象となります。評価期間中に上げた営業業績を数値化し、あらかじめ設定されている目標に対して達成率を元に評価します。
2)能力評価
能力評価では、業績を上げるための個々の行動様式や潜在的な能力が評価対象となります。営業スタッフが持つスキルや知識、職務を通じて新たに身につけた能力、想定外の事態への対応力などが評価されます。数値化が難しいこれらの項目は、(評価者の)主観を排除した公平な評価を行うことが課題となります。
3)情意評価
仕事に対する取り組み方や姿勢を評価する項目も設けられることもあります。これは“情意評価”と呼ばれ、仕事への熱意や意欲的な姿勢、勤怠や勤務態度、積極的な業務改善姿勢などが評価対象となります。営業業績が伸び悩んだり、能力の向上が見られなかったりしても、仕事への向き合い方や姿勢への評価を通じて公平に評価し、モチベーション維持につなげることが可能です。
【こちらもおすすめ】業績の向上にどうつながる?中小企業の「人事評価制度」メリットとデメリットを解説
目標を達成できない営業スタッフへの個別の対応
ときには、目標達成に苦戦するスタッフもいるでしょう。そうしたスタッフへの個別対応は、組織の健全性と長期的な業績に大いに影響します。
対応策として、目標達成できない原因を考え、今後の改善策を練ることや、トップセールスなどのノウハウ共有を行うことが有効的でしょう。また、目標達成できない状態が続くと、自己評価が低下し、モチベーションが低下することがあります。定期的な1on1ミーティングを行うなど、心身のサポートをできる体制にしておきましょう。
また、最も重要なポイントとしては、目標達成が難しいスタッフに対して、数値の達成だけでなく、行動や努力を評価する公正な評価体系を整備することです。行動考課や情意評価を導入し、スタッフの努力を適切に評価しましょう。
まとめ
「目標必達」の意味を込めて使うアップデート版“ノルマ”は重要な指標ですが、過度な“ノルマ”は強引な営業やプレッシャーによるメンタル不調などを招きやすいため、適切な設定と運用が必要です。現代にフィットするように、KGI・KPIといった指標を用い、現場のスタッフと十分にコミュニケーションをとったうえで決定しましょう。目標達成困難な社員には適切なサポート体制や公正な評価体系をつくりましょう。
* kabu,OnO,マツ,りびっつ,チキタカ(tiquitaca),Turn.around.around, kabu / PIXTA(ピクスタ)
【こちらもおすすめ】営業効率を劇的改善!4ステップでつくる「やることリスト」の効果があなどれない