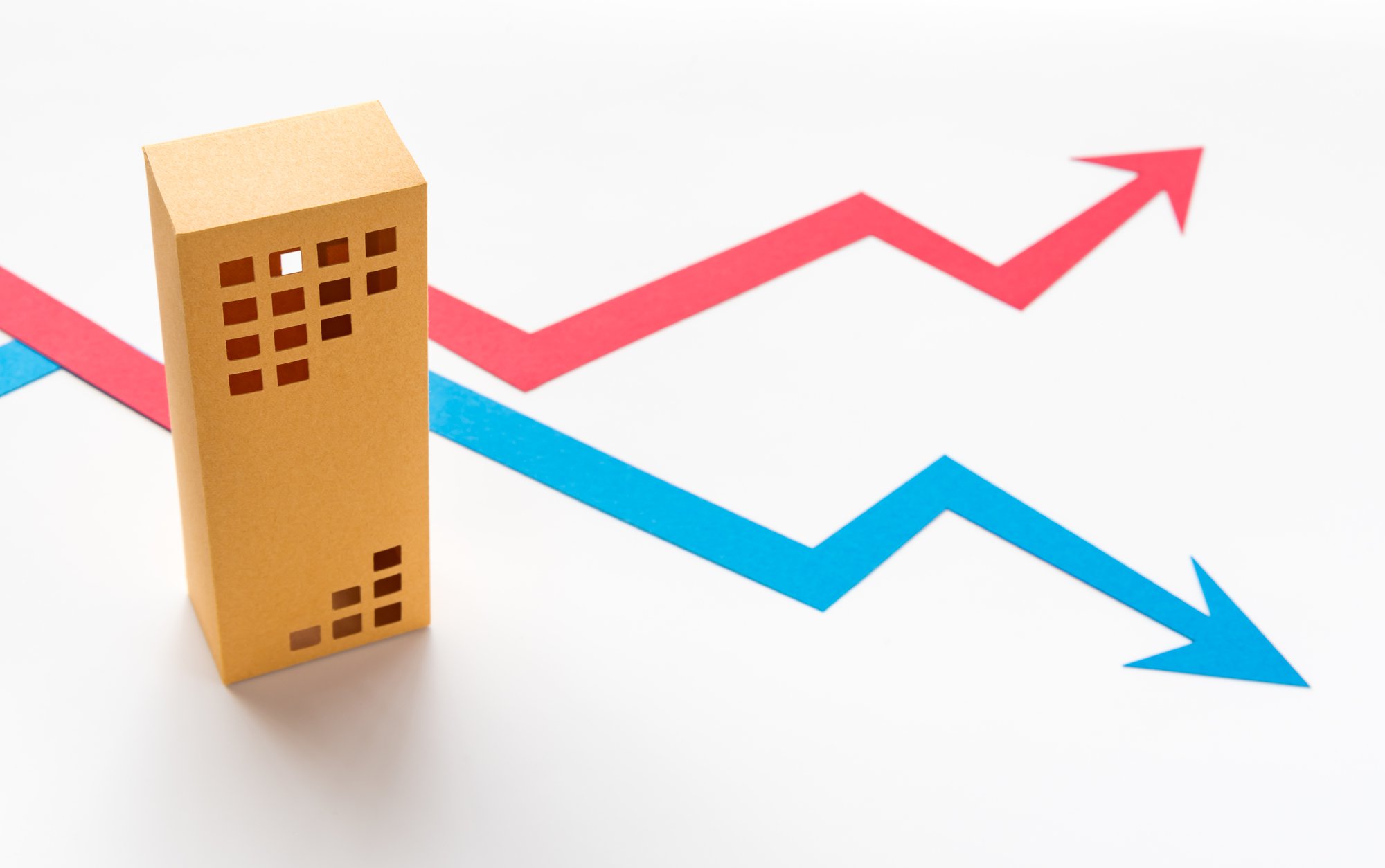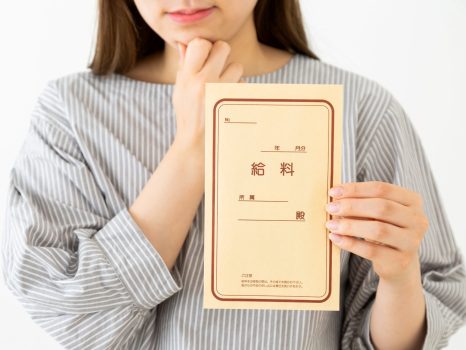黒字倒産の危険も…資金繰りが苦しい原因の改善方法とは
会社を安定して運営するには“資金繰り”が重要です。一見、安定して見える企業も資金繰りに失敗し、倒産してしまうなんてこともありえるのです。今回は、経営コンサルタントとして数多の企業を見てきた筆者が、資金繰りが悪化する理由と改善方法を解説します。今一度、自社の収支管理を見直す機会としてください。
目次
資金繰りとは
まず、資金繰りとは「資金の収支管理」といえます。資金の流れを理解し、管理する行為をひとまとめに“資金繰り”という言葉で表現します。最もシンプルにいえば、“資金管理”と表現できます。
黒字倒産とは
そもそも倒産の明確な定義はありませんが、シンプルにいえば、「現金が枯渇し、事業が停止すること」という理解が一般的です。
また、聞いたことがある方も多いとは思いますが、“黒字倒産”という言葉があります。この意味は、帳簿上利益は出ているものの、現金が尽きてしまい給与や取引先への支払いが滞り、事業停止状態となってしまうことを指します。つまり売上はあるものの、支出が多く、売掛金を回収する前に現金がゼロになってしまうというケースです。
結局のところ、利益よりも、「現金があるかどうか?」ということの方が大切です。経営者は経理の方に任せっぱなしではいけません。“資金繰り=資金管理”であり、現金の推移は注意深く、常にチェックできる体制を構築しなければなりません。
資金繰りが悪化する原因とは
そもそも、売上が少なく、売上総利益が僅かしかないことや、販売額が原価割れして赤字である、ということは資金繰りが悪化する最大の理由ではあります。しかし、よくある「利益はあるはずなのに、なぜか現預金の減り幅が大きくて資金が苦しい……」という悩みはよくあると思います。そのようなときは、以下の3つのポイントをチェックしてみてください。
原因1:固定費の支出額が多過ぎる
そもそもの売上の増減に関わらず、毎月固定で現金が出て行ってしまう項目の見直しをおすすめします。固定費の代表格は地代家賃、人件費、リース料、広告宣伝費等、販売の増減に関係なく一定額支出があるものです。
原因2:支払い条件と回収条件のバランス
当たり前ですが、原則として支払いは遅く、回収は早い方が資金繰りは楽になります。得てして、この逆のケースが資金繰りを苦しめています。業態によりさまざまなケースがあるとは思いますが、可能な限り大口の支払いを遅く、大口の回収を早くできるように交渉してみましょう。
原因3:融資条件が悪い
頻繁にあるケースですが、意外と盲点になっていることがあります。決して忘れてはならない支出が“元金返済額”です。金利は経費として認識していることがありますが、元金返済は経費にはならない単純な現金の減少です。融資期間が短く、元金返済が異常に多い場合は資金繰りを圧迫します。
業態によっては、常に支払いと回収のタイムラグから発生する、“経常運転資金”が発生します。この場合は、言い換えるなら「事業を回していく上で、必要な資金」となります。この計算式は「売掛金+棚卸資産-買掛金」です。
この金額を短期継続融資(当座貸越・手形貸付)といった期限一括返済の形をとり、継続し続けることで不要な元金返済部分の現金支出を減らすことができます。さらに、複数ある借入を金融機関と交渉し、まとめて一本化し、長期間の返済に変えてもらうことも有効です。
資金繰りの悪化をさせないためにやるべきこと
1. 資金繰り予定表による実績の振り返り
これが王道です。予算と実績の振り返りを毎月遅くとも15日までには実施しましょう。実は資金繰り予定表を作成して、実績との照らし合わせを複数人の目で行っている企業は中小企業の全体の5%未満というのが、今までの経験のなかでの実感です。
言い換えるならば、この資金繰り予定表を作成していくプロセスそのもので、支出の実態を把握でき、問題点に気づくので、作成プロセスから資金繰り改善への工夫が自然に始まっていくという効果も期待できます。
【無料ダウンロードはこちらから】資金繰り表を作成する
2. 貸借対照表と損益計算書の試算表を毎月作成する
こちらも、経営状態の正確な把握のために、毎月遅くとも15日までには作成しましょう。目標値をクリアできているのか確認し、目標とのギャップが発生しているのならその原因を毎月、考えていくことは経営者としての基本動作であり大切なことです。月末で締めて、翌月15日までに作成できないのであれば社内の経理体制もしくは提携している会計事務所に問題点があるといえます。早急に経理体制の再構築を検討すべきでしょう。
【無料ダウンロードはこちらから】
貸借対照表を作成する
損益計算書を作成する
3. 根拠ある経営計画書を作成する
根本的な経営改善を行うには、根拠が明確に示された経営計画書が必須となってきます。経営計画書の作成率も中小企業全体では10%未満と考えられます。中小企業の資金繰りのカギを握り、社外においてないがしろにできない存在は銀行、信用金庫などの金融機関です。金融機関の職員は融資のプロであって、読者のあなたが経営する企業の業界のプロではありません。
何をお伝えしたいのかといいますと、「業界の素人が見ても、“戦略”と“戦術”が分かる根拠の明確な経営計画書が必要」ということです。この経営計画書の効能は計り知れません。「どうせ絵に描いた餅でしょ?」という思い込みは捨て、まずは稚拙であっても、経営学のフレームワークの代表であるクロスSWOT分析を土台に、行動計画にまで落とし込んだ計画書の作成を強く求めます。
【こちらもおすすめ】M&Aの相談がわが社に!どう判断する?経験豊富な元CFO・現COOが解説
まとめ
いろいろとお伝えして参りましたが、シンプルに結論をいえば以下の通りです。
- 資金繰り予定表を作成し、予算と実績の振り返りを毎月行う
- 借入の一本化、長期化や、短期継続融資を導入し、借入の最適化を行う
- 原価の低減はいうまでもないが、固定費を中心に支出の見直しを実施
これら3つに真摯に全力で取り組めば、かなり高い確率で資金繰りは改善します。ただ、ここで忘れてはならないことは、資金繰りを改善させることは経営改善の一部であって、本当に大切なことは、資金の余裕をつくったのならその資金を戦略的に「何にいくら使って、いくらの効果を狙っていくか?」ということの方が圧倒的に重要です。この点はきちんと経営計画であらかじめ示しておかねばならないでしょう。
資金繰りの改善は戦術、手段の一部であって、経営の目的ではありません。「言うは易く行うは難し」の項目が多いとは思いますが、資金繰りの改善に近道はないのです。思いどおりの企業成長を遂げるために、地道な資金繰り改善の一歩を踏み出してみましょう。
*Luce, Rawpixel, takeuchi masato, CORA, shimi, beauty-box / PIXTA(ピクスタ)