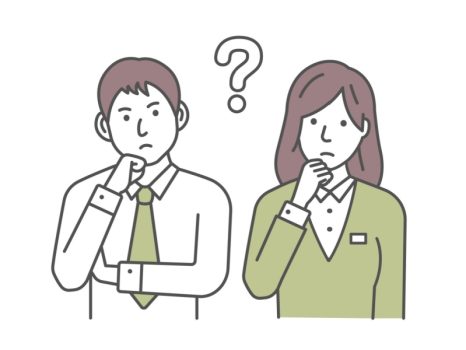中小企業必見の「賃上げ促進税制」とは?令和6年度税制改正大綱を踏まえて詳しく解説
この春、組合の賃上げ要求に対する満額回答が相次ぎました。背景には、物価高と人手不足が影響しているといわれています。投資拡大・消費拡大を実現するには、国民所得の伸びが物価上昇を上回る必要があるでしょう。
デフレ脱却のチャンスとばかりに、今年度の税制改正では、所得税・個人住民税の定額減税とあわせて、企業の賃上げを強力にプッシュするための「賃上げ促進税制」が強化されました。
しかし、物価上昇に苦しんでいるのは、大企業に勤める人々だけではありません。日本の雇用の7割を担う中小企業が賃上げできなければ、政府が目標にかかげる「賃上げと成長の好循環」の実現は難しいでしょう。
本コラムでは、中小企業にしぼって賃上げ促進税制の改正点をお伝えしていきます。
目次
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、つまり税額を控除できる制度です。控除額は、下記の算式で計算します。
| (今年度の全雇用者に対する給与等支給額―前年度の全雇用者に対する給与等支給額)×控除率=税額控除額 |
原則的な控除割合は15%ですが、一定の要件を満たした上で給与の上昇率が高い場合、最大で45%の税額控除が受けられます。
中小企業のうち6割を占めるといわれる赤字法人にとって、これまでの制度では何もメリットを感じられないことが課題でした。どれだけ控除率が高くても、もともと払っていない税額に対しての控除にうまみを感じないからです。
そこで今回の改正では、賃上げ促進税制が中小企業の賃上げのインセンティブとなるよう、新たに「繰越税額控除制度」が設けられました。何がなんでも、国民全体の賃上げを実現したいという政府の本気度が感じられます。
【こちらもおすすめ】昇給の種類とは?中小企業が実施すべき「給与制度」の作り方
令和6年度の改正点
今回の改正点は、次の4つです。
| 1. 適用期限の延長 2. 繰越税額控除制度の新設 3. 上乗せ措置(教育訓練費)の適用要件変更 4. 上乗せ措置(くるみん認定・えるぼし認定)の新設 |
1. 適用期限の延長
適用期限が3年間延長され、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
2. 繰越税額控除制度の新設
赤字の法人でも、限度超過額が5年間、繰り越せることになりました。税額控除できる金額には上限があり、これまでは法人税額の2割を超える部分は切り捨てだったため、赤字の法人や少しだけ黒字という程度の法人にとっては、絵に描いた餅状態だったのです。
改正により、今後はその期に控除できなかった分を、翌期以降利益の出た年度で使えることになりました。中小企業にとっても、節税効果の高い魅力的な税制になったといえるのではないでしょうか。
ただし、繰越税額控除制度を使うためには持続的な賃上げをしていることが要件であり、適用できるのは前年よりも全雇用者の給与等支給額が増えている場合に限られます。また、未控除額が発生した年度の申告で、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の提出が必要です。
3. 上乗せ措置(教育訓練費)の適用要件変更
教育訓練費を増加させた場合には税額控除率が上乗せになりますが、その要件が変更になりました。具体的には、下記2つの要件を満たせば控除率が10%上乗せされます。これまでは10%以上の増加が条件でしたが、教育訓練費の増加割合が低く変更されたことで、上乗せできる法人が増えるのではないでしょうか。
| 要件1 | 教育訓練費の額が、前年に比べて5%以上増加していること |
| 要件2 | 教育訓練費の額が、全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上であること |
4. 上乗せ措置(くるみん認定・えるぼし認定)の新設
子育てと仕事の両立支援や女性の活躍推進に積極的な企業には、さらに控除率を上乗せしようという制度です。厚生労働省による認定制度「くるみん」以上または「えるぼし」の2段階目以上の認定を受けていれば、5%が加算されます。
| 要件 | 「くるみん(以上)」、または「えるぼし(2段階目以上)」の認定を受けた事業年度であること |
【こちらもおすすめ】今、中小企業にも女性活躍推進が求められている!進め方から助成金まで解説
制度の適用要件
以上の改正を踏まえると、令和6年4月1日から中小企業者等に適用される「賃上げ促進税制」は、以下のとおりです。
中小企業者等とは
青色申告書を提出する下記のいずれかの法人(個人)を指します。
| 1. 次のいずれかの法人(前3事業年度の平均所得金額が15億円以下に限る) ○資本金(または出資金)が1億円以下の法人(下記は除く) ・同一の大規模法人から1/2以上の出資を受けている法人 ・2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受けている法人 ○資本(または出資)を有しない法人で、常時使用する従業員数が1,000人以下 |
| 2. 協同組合等 |
| 3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 |
税額控除率とは
適用対象ごとの控除率は、以下のとおりです。
| 適用対象 | 税額控除率 | |
| 通常(ベース) | 全雇用者の給与等支給額が、前年度比1.5%以上増加 | 15% |
| 上乗せ(給与上昇) | 全雇用者の給与等支給額が、前年度比2.5%以上増加 | +15% |
| 上乗せ(教育訓練費) | 教育訓練費の額が、前年比5%以上増加、かつ、全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上 | +10% |
| 上乗せ(新設) | くるみん(以上)認定、または、えるぼし(2段階目以上)認定 | +5% |
ただし、控除税額は当期の法人税額の20%が上限です。また、その期に控除できなかった部分については、5年間繰り越すことができます。
全雇用者の給与支給額等とは
国内雇用者に対する給与等をいいます。賞与は含みますが、退職金など給与所得とならないものは、原則として該当しません。給与等に充てるための助成金等がある場合には、その額を控除します。
国内雇用者とは
国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。パート・アルバイト・日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員および役員や個人事業主と特殊な関係がある者は除きます。
教育訓練費とは
国内雇用者の職務に必要な技術・知識を習得させる、または向上させるために支出する費用のうち、一定のものをいいます。
たとえば、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等・外部施設使用料等)、外部に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、外部の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などがこれにあたります。
くるみん認定とは
男性の育児休業等取得率や雇用環境の整備に関する行動計画の策定など10の基準を満たした企業を、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定する制度のことをいいます。くるみん認定を受けた企業は、自社の商品や求人広告などに、くるみんマークをつけることができます。くるみんには、赤ちゃんをつつむ「おくるみ」と「企業ぐるみ」で子育てをサポートするという意味が込められています。
なお、労働者数が300人以下の一般事業主の場合は特例がありますので、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
【参考】くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正/厚生労働省
えるぼし認定とは
男女の平均継続勤務年数や管理職比率など、5つの基準のうち1つまたは2つ以上の基準を満たした企業を、女性の活躍推進に積極的に取り組む企業として厚生労働大臣が認定する制度のことをいいます。えるぼし認定を受けた企業は、自社の商品や求人広告などにえるぼしマークをつけることができます。えるぼしの「える」は、Lady ・Lead・LaudableなどのLを意味しています。
賃上げ促進税制の上乗せ控除率が適用されるためには、5つの基準のうち、3つまたは4つの基準を満たし、かつその実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表する必要があります。
まとめ
2024年度改正の中小企業向け「賃上げ促進税制」について、解説しました。本来、企業が支払う賃金は全額が損金算入できるわけですが、それに加えて賃上げ分の最大45%が税額控除できるという、これまでに類を見ない破格の大盤振る舞いです。
今回の賃上げ促進税制は、中小企業にとってもおさえておきたい節税対策といえるのではないでしょうか。ぜひ、参考にしてください。
*genzoh / PIXTA(ピクスタ)
*Kmpzzz, AlvaroMP, lovelyday12 / shutterstock
【まずはここから】はじめてのフリーアドレス導入ガイド