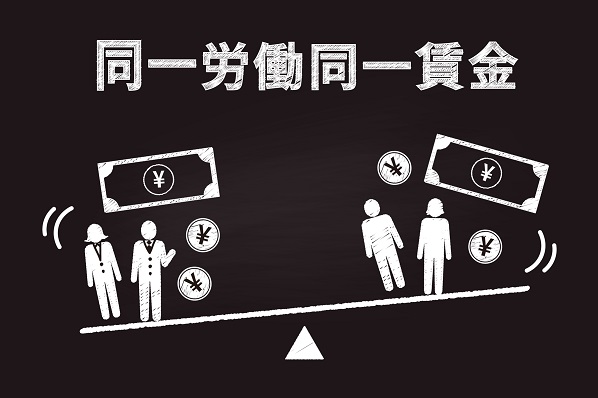昇給の種類とは?中小企業が実施すべき「給与制度」の作り方
社員の昇給を経営者の裁量等で実施してはいませんか? 「令和3年度中小企業の賃金事情(令和3年版)」/ 東京都産業労働局(※従業員が10人~299人の都内中小企業を対象とした賃金についての調査)において、「過去一年間に定期昇給を実施した」と回答した企業のうち「定期昇給の規定はないが慣行により実施した」と回答した企業は約4割となっています。
必ずしも定期昇給の規定がないことが経営に悪影響を及ぼすというわけではありませんが、何らかのきっかけ、例えば「代表者変更や経営者の交代を機にわかりやすいルールを構築したい」「明確なルールがないことに社員が不満を抱いていた」というようなことから、昇給ルールを含めた給与制度構築の検討をするという場合もあるでしょう。
そこで今回は、昇給ルール設計の方法を解説していきます。昇給した際の実務チェックシートも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
昇給にはどういう種類があるの?
そもそも昇給とは?
昇給とは、“年齢や勤続年数、また評価結果等の要素の変化により行う基本給の引き上げ”のことを指します。どの要素を採用するか、また各要素をどの程度加味するかは会社により様々です。例えば、昇給決定の基準を「年齢と勤続年数のみとしている」「評価結果のみとしている」「年齢・勤続年数・評価結果すべてとしている」等、いろいろなケースがあるでしょう。
このような基準に加え、昇給を実施するタイミング等、昇給にはいくつか種類があります。
普通昇給と特別昇給
前述のように“年齢”や“勤続年数”、また“評価結果”等、対象者が共通の要素で昇給することを“普通昇給”といいます。一方の“特別昇給”とは、例えば「著しい業績や成果を上げた」「特別な功労があった」というように“特別な理由にもとづいて昇給すること”を指します。
定期昇給と臨時昇給
毎年時期を定めて行われる昇給のことを“定期昇給”といいます。例えば、前年度の取り組み結果から新年度開始時に行う場合が最も一般的といえるでしょう。一方、“臨時昇給”とは時期を特に定めないで実施する昇給のことを指します。
ベースアップ(ベア)と昇給の違い
次に昇給と混同しやすい“ベースアップ”について説明します。前述のように昇給を決める要素は様々ありますが、社員個別の昇給額には差がつくことが多いといえるでしょう。例えば、「若年層ほど昇給額を大きくする」「勤続年数が多くなるほど昇給額を大きくする」「評価結果が良いほど昇給額を大きくする」というように様々な考え方があります。このような考え方にもとづいて決定された各人の昇給額には差がついていきます。
一方“ベースアップ(ベア)”とは、社員全員の賃金を一律の比率で昇給させる仕組みです。例えば、2%のベースアップが実施されると、基本給20万円の場合は20万4,000円になり、同じく25万円の場合は25万5,000円になるわけです。「労働組合と使用者側が交渉する“春闘”によりベア〇〇円を妥結した」というようなニュースを聞いたことがあるかもしれません。これがまさにベースアップのことを指します。
【こちらの記事も】社員のモチベーションアップには欠かせない!キャリアアップや昇給に関連する相談まとめ
どのように昇給ルールを決めればいいの?
それではどのように昇給ルールを決めればよいのでしょうか。一般的に昇給ルールは給与制度を構成する一つの要素であり、例えば等級制度、諸手当、基本給表等を検討した上で決定するものです。昇給ルールを決定することは、ダイレクトに人件費の変動につながるものであり非常に重要であるといえます。
以下に昇給ルールを決定するまでの参考手順を記載します。
その1:等級制度を作成する
基準を定め、社内評価の段階を作っていきます。一般的に段階が上がるほど基本給が増加していくことになります。この基準のことを“等級制度”といい、例えば能力や期待役割等の基準があります。「新入社員が入社した後、段々とレベルアップしてより難しい業務を担当し、将来的にはチームをまとめ部下育成を担っていく」というような段階をイメージするとわかりやすいでしょう。
その2:モデル賃金を作成する
次に“モデル賃金”を作成します。これは「ある社員が新卒で入社し定年まで勤めると仮定して、その間の基本給や手当、また賞与の見込みを計算していきどのくらいの賃金を得ることができるか」という想定パターンを複数作成し、自社の賃金水準を検討していくためのものです。“優秀な結果を出し続ける場合”や“標準的な結果を出し続ける場合”というように複数のモデルを検討し、その地域の生計費や業界平均等のデータを参考にしながら賃金水準を決定します。
その3:諸手当を決定する
役職手当、資格手当、家族手当、精勤手当等の“諸手当”を決定していきます。例えば、「過去設けた手当で、現在ではすでに形骸化している手当は廃止する」「現在の業務状況や社会情勢を踏まえて必要な手当を新設する」等を検討していきます。また、同じ手当でも金額や対象を変更する場合もあるでしょう。例えば「共働き家庭が多いので、配偶者を対象とした家族手当を減額する一方で、子どもに対する手当を新設する」ということも考えられるでしょう。
【こちらの記事も】手当、助成金は?男性の取得は?産休・育休に関する相談まとめ
その4:賃金テーブルを作成する
モデル賃金で自社の賃金水準を明らかにし手当を決定すれば、あるべき基本給の水準がみえてきます。その水準を踏まえて、各等級に対する基本給の下限額と上限額を設定し“賃金テーブル”を作成します。等級に対して明確に基本給の幅を設定することで、社内の段階と賃金を連動させることができます。
その5:昇給表を作成する
自社の基本給水準が明らかになれば、入社から定年まで毎年どの程度の昇給を設定すればその水準に近づくことができるかが分かります。その昇給水準を“昇給表”に落とし込みます。この際、等級や評価によって格差をつけていくことが一般的です。そうすることで、例えば社内でより大きな役割を担っている、より大きな成果を創出した、という社員を適切に処遇することにつながります。
昇給を決定した後はどのような手続きが必要になるの?
それでは、上記のようなルールにしたがって昇給を決定した後、実務ではどのような手続きが必要になるのでしょうか。昇給すると給与額が変更になるわけですが、その際に保険料や税金の再計算や届出が必要になってきます。
『経営ノウハウの泉』では、昇給を実施した後の手続き実務チェックシートを無料でご提供しています。下記リンクよりダウンロードしてお役立てください。
>>>「“従業員の給与を昇給する”実務チェックシート」を無料ダウンロード!
今回は、昇給ルールの設計方法をご紹介しました。昇給ルールを作成する際に、ぜひ参考にしていただきたいです。
【参考】『令和3年度中小企業の賃金事情(令和3年版)』/ 東京都産業労働局
*Gugu / PIXTA(ピクスタ)