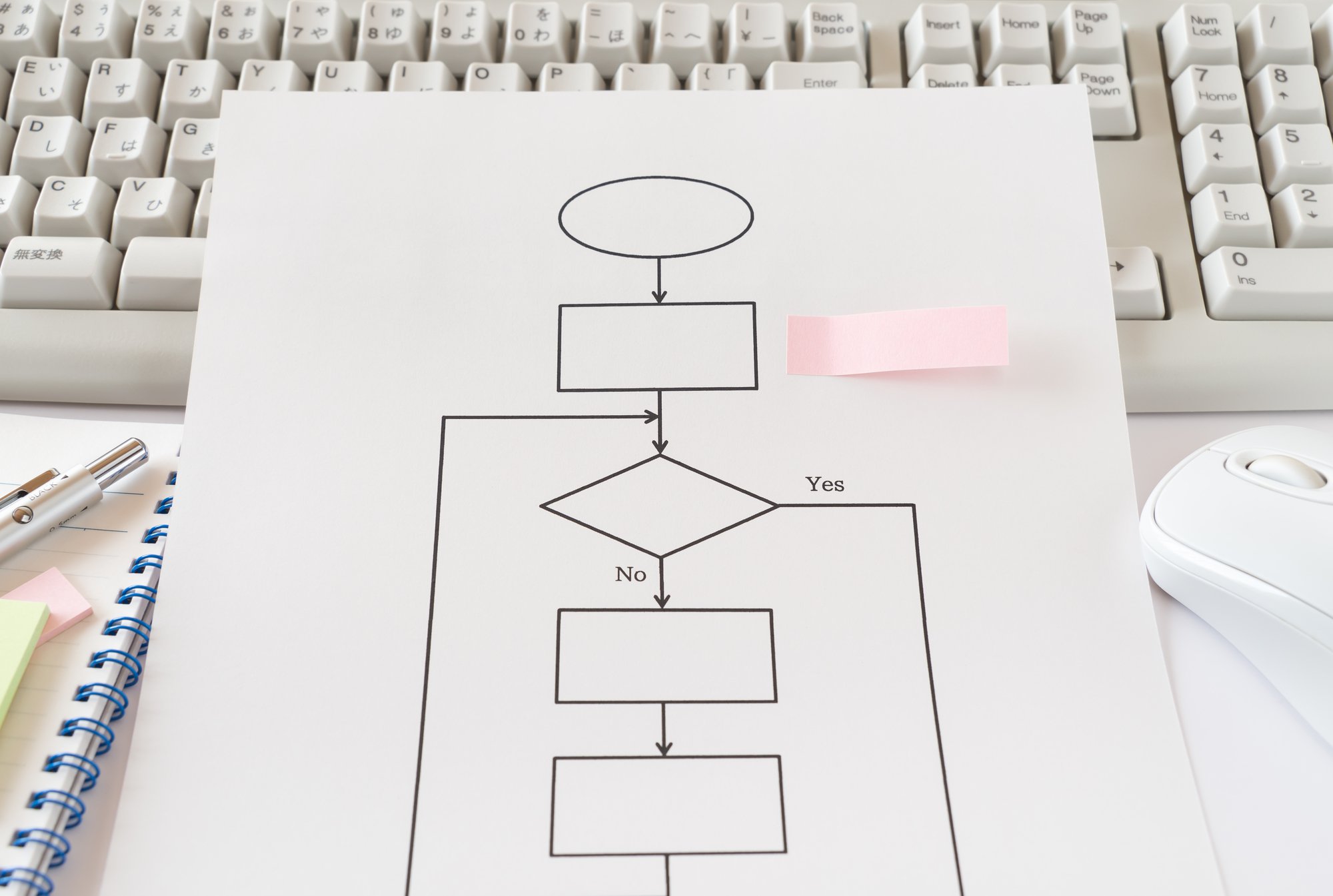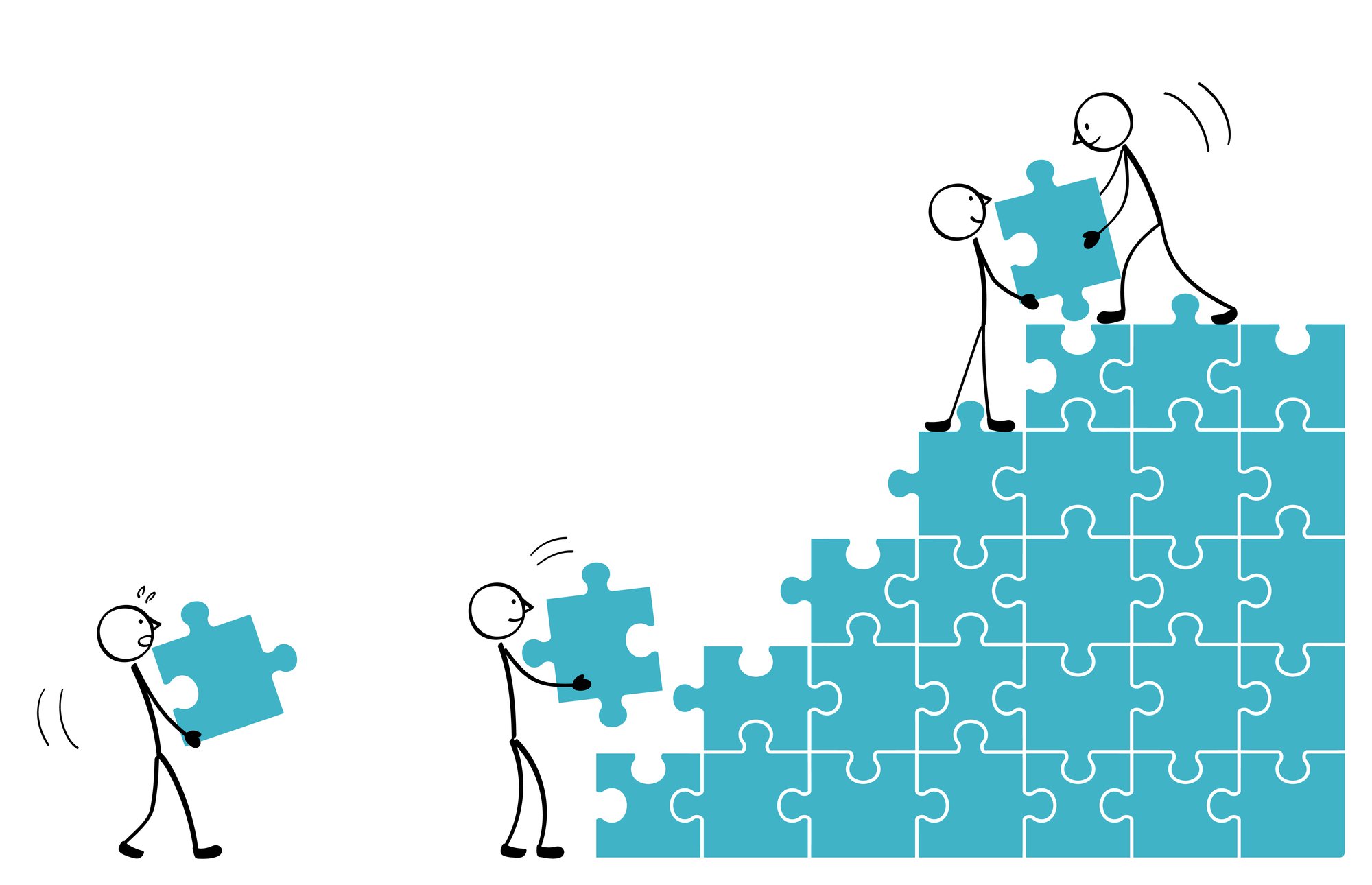「マニュアル化」するべき本当の目的とは?進め方の4ステップも紹介
企業がスタートアップから徐々に成長していくときに、必ず出てくる課題が「いつ業務をマニュアル化するのか?」です。実際のところ、経営の現場にいると、営業やその他の締切がある業務に追い立てられ、なかなか手がつかないものです。しかし、さまざまな場面で業務をマニュアル化しておくとよいことしかありません。また、事業を発展させていく中で、仕事に関わる人を増やすことが前提にある場合、一人事業主のステージからでもマニュアル化は進めておくべきです。これは筆者自身も経験上、確信していることです。そして、周りの経営者の方も、しっかりした方は必ず何かしらの形で自身の業務を文書化しています。日々、業務を進めていく中でマニュアル化は必ず役に立つのです。今回の記事を契機にぜひ検討していただければと思います。
目次
マニュアル化の効果とは
マニュアル化についてその効果について考えると、社内業務・品質基準の統一化、教育コストの削減、業務改善準備のための棚卸しなどが期待されます。やはり最初はそこが目指すべき効果でしょう。業務自体をどう実施するかというノウハウがしっかり明文化されていることで、新しいスタッフが加わったときの研修や引き継ぎにかかる負担を減らすことができますし、現在の担当者がいないと業務が進まないといった属人化問題も回避することができます。
また、現在の業務がどのように行われているかが正確に把握されていないと、業務がブラックボックス化してしまい、組織として変更・改善がやりにくいという点も属人化の問題点も併せて議論されています。
マニュアル作成「本当の目的」とは
書店にある指南書や、ネット上のガイドにも解説されているマニュアル作成を推奨している本には、業務の標準化、品質の底上げ、人材育成、属人化の解消、業務効率化のための棚卸しなどを目的に掲げています。これらすべて大切な事柄ですが、最も大切なことは “組織内の業務・組織を常にアップデートしていくため” です。
経営者本人も、業務のマニュアル化自体がリスク回避という理由だけでは着手するモチベーションが充分に得られないのではないでしょうか。いざということがなければ、そのままで済ますこともできてしまうのが実際だったりします。そのため、以下の3点を理解しておくことが大切です。
1)ビジネスモデルを更新し続けるために
以前の記事にも紹介した通りビジネスモデルは常に更新し続ける必要があります。その必要性については是非、以下の記事をご覧ください。
10年前と変わっていないのは危険!? 「ビジネスモデルの変革」はどんな企業に必要か
事業と同時に従業員も育っていくことを前提に考えると、従業員も常に同じ業務を担当していては事業に成長はありえませんし、スタッフの所得向上を図ることも難しくなります。
2)自動化の土台づくり
繰り返し発生する作業は順にマニュアル化を進めていくことで、新しく加わったスタッフに担当移譲、外部の企業に委託することができます。もしくは以下の記事でも紹介したように、機械による自動化を実現し、部分または全体を無人化できる可能性もあります。
リモートワークの弊害をどう乗り越える?コロナ禍で露呈した中小企業の経営課題(人材と機械の役割再配置について)
3)事業発展の基盤を築く
さらに、目線を事業全体として考えれば、事業承継に悩む企業とのM&A案件の相談が多く寄せられています。これは地域で育った事業を守り、育てるための大切な取り組みです。しかし、参入するにもやはり業務のマニュアル化が行われていないと、業務統合自体が検討できなくなってしまいます。マニュアル化はリスク低減や業務負荷低減の話にとどまる話ではなく、事業発展のために欠かせない敷石となる基礎準備と捉えましょう。
【M&Aについてもっと詳しく】未経験だから踏み出せない…「中小企業のM&A」種類とメリット、リスクをわかりやすく解説
事業承継問題の解決策として注目! 中小企業のM&Aメリット・デメリット【事例付き】
中小企業におけるマニュアル化の進め方
マニュアル化作業の着手タイミングですが、先にも書いたように一人事業主の段階からでも開始すべきです。以下でマニュアル作成のポイントを解説していきます。
①マニュアル化するべき作業を洗い出す
作業はすべてマニュアルにすべきかというとそうではなく、早期に手をつけるべき対象は以下の作業になります。
・常時行う作業ではなく、年度や月次などの定期作業
・一定の品質/基準を満たせば誰でも担当できる作業
・繰り返し実施してノウハウが蓄積している作業
②とにかく形として残す
これらをとにかく形は問わないので文字や図に落としておくことをおすすめします。筆者も経営者として、上記の基準を元に、とにかく形は問わずに思いついたところから記録しています。あとから気づいたことを追記したり、修正したりすることを前提にとにかく形にすることを進めましょう。
③一か所にまとめておく
一方でどこでもよいというわけではなく、記録する場所は一か所に定めておくようにしましょう。筆者自身も「どこにメモしたか……」と探すことに時間がかかってしまう本末転倒な事態を過去に何度もやらかしてしまいました。今はLINE WORKSを社内の共通ツールにし、筆者が記録する場所はLINE WORKSの掲示板に統一しています。
④体裁やフォーマットは問わない
スタッフの皆さんにも同じルールで記録をお願いしており、文書の体裁やフォーマットなどは一切問わないようにしています。一つだけ守る基準は、自分以外の人が読んでも理解できること、これのみです。そこで、新しいスタッフや外部委託の担当者に業務の話をするときに記録したものを参照しながら会話すればよいのです。その時点で記述に不足や修正が必要であれば、そのタイミングで実施するようにしています。
これを繰り返しているだけでも数年経てば意外と必要なマニュアルが揃ってきます。その上で、現在不足している作成が必要なマニュアルも、業務を進めている段階であぶり出されてきますので、追加で作成することになります。整えた“業務マニュアル”の冊子化などは、本当に必要になったときで間に合うのです。
まずはこれまで経験が積み重なった業務は新しいスタッフ、機械化または外部にどんどん任せられるようにマニュアルを活用し、事業をアップデートしていきましょう。
*freeangle, Graphs, CORA, hidekichi, PRISM, Kana Design Image / PIXTA(ピクスタ)
【こちらもおすすめ】キーマン社員は不要!?あの人しか知らない「属人化」解消のファーストステップを解説
【まずはここから】無料オフィスレイアウト相談はこちら(移転・リニューアル・働き方改革)