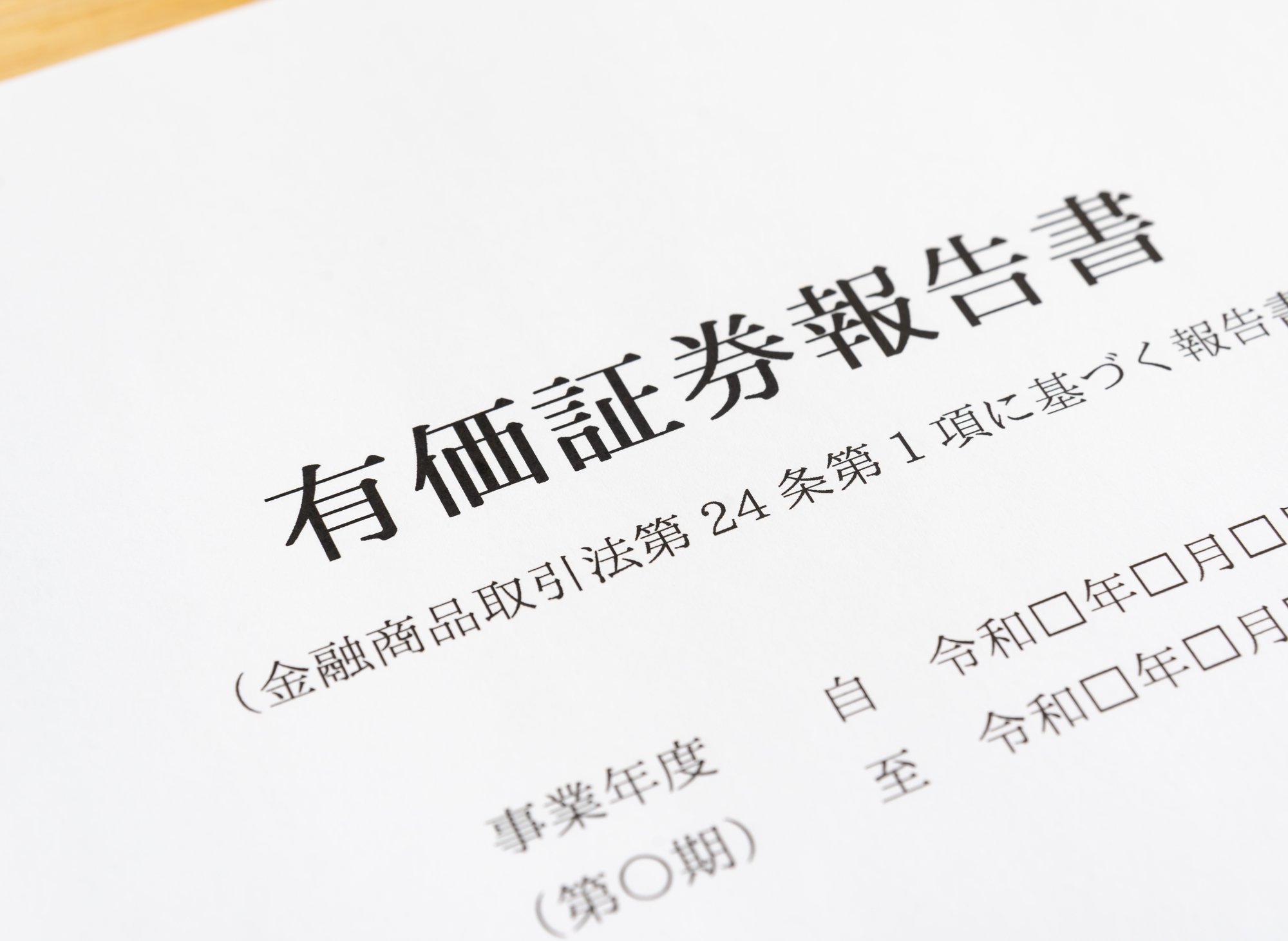上場が成功とは限らない?上場経験あり元CFOが語るIPOのメリットとデメリット
「会社を立ち上げたからにはいつかは上場したい!」どの経営者でも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。今回は上場を2度経験し、ベンチャー企業経営に今も携わる筆者が上場のメリット・デメリットについて考えてみました。
目次
上場の意義とメリットについて
まず、一般的にいわれる上場の意義を紹介します。何回も聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんので、ここは簡潔にいきましょう。
1)資金調達の自由度が上がる
自社の株式に価格がつくことにより、株式の発行がより柔軟にできるようになるため、資金調達の自由度が上がるといわれています。未上場の状態でも株式の発行はできますし、増資は当然可能です。しかし、企業価値算定が難しいことや、株式を取得した投資家のエグジット(投資家やベンチャーキャピタルが自身の投資を終了し、投資先企業からの資金や利益を回収すること)機会を提供しづらいことから、上場している場合の価値から若干のディスカウント(または、非流動性ディスカウント・・・特定の資産や投資の流動性が低いために、その価値が通常の市場価格よりも割安に評価されること)が発生することが多くあります。
2)あらゆる面で信用力が得られる
また、日本には今367万社以上の企業があるといわれていますが、上場企業はそのうち3,883社(2023年5月10日時点)だけです。「上場しているから優れた会社」というわけではないですが、上場をするためにガバナンスや企業の成長可能性、事業の継続性について網羅的な審査が行われることから、同じ規模の会社であれば、上場企業の方が信用力は高いとみなされることが多くあります。このことから、銀行から無担保で融資を受けられたり、オフィスを借りる際も経営者の個人保証がいらなくなったりなど、財務面でのメリットも多く存在します。
信用力については、社会的信用の観点でも同様にメリットがあります。たとえば、上場することで信頼度が増すことから、取引先との事業機会が増えたりすることもあるでしょう。企業の与信調査をする際に、上場企業、それ以外の企業で審査基準を分けている事例はまだ存在します。ベンチャー企業も増えていることから変化も見られていますが、これはまだ一般的な見方の一つといえます。また、会社の認知度や事業の継続性に対する安心感が増すことから、一部の採用領域においては、未上場企業よりも優位になる場合もあるでしょう。
【参考】21年の企業数は367万社、コロナを受け飲食・宿泊が減少/日本経済新聞
【資金調達についてもっと詳しく】中小企業の資金調達方法は?弁護士兼中小企業診断士が代表的な方法を解説
【金融融資面談についてこちらもおすすめ】意外と見られているポイントって?金融機関の融資面談マニュアル
上場はいいことばかりではない?デメリットとは
上場の意義とメリットについてご紹介いたしました。では上場はどんな企業に対してもよいことなのかというと、そうでもないかと筆者は考えています。3つほどデメリットについても考えてみましょう。
1)どの企業でも市場から評価されるわけではない
上場の際にはPER(株価収益率)という株価指標が多く用いられます。PERは「会社の純利益想定に対してどのくらいの時価総額が適切かを測る指標」であることから、市場からの成長期待値といい換えることもできます。成長期待値を数値化したものである特性上、どういった事業であっても一定のPERがつくわけではありません。実際に上場の事例を見てみても、公開価格(上場時の株価)ベースのPERが15倍という会社もあれば、50倍を超える会社もあったりします。具体的な数値に置き換えてみると、純利益が5億円の会社があったとして、上場時に時価総額が「75億円」と評価されることもあれば、「250億円」と評価されることもあるということです。
この評価の違いは事業の成長性に起因するものですが、その成長性の要素は市場のこれまでの経験上、成長を実現してきた企業の特性をトレース(記録、追尾)するケースが多く見られます。たとえば以下4つなどがポジティブに評価される軸となります。
・成長市場に事業ドメインを持つ会社かどうか
・事業展開が体系的になっていて、成功の再現性が担保されている
・エコシステム(ビジネス上での生態系)を構築できる事業で、自律的に事業が成長する環境をつくることができるかといった事業構造上の特性
・今トレンドの事業を持つ会社かどうか。2021年頃であればSaaS企業、今であればLLM(大規模言語モデル・・・膨大な量のテキストデータから学習される機械学習モデル)やAIプラットフォームなどがフィットしそうです
企業は上場する際に、これらの点を証券会社や投資家が査定し、株価が決まっていくことになります。その中で必ずしも企業の想いがすべて認められるわけではありません。場合によっては意思に沿わない株価算定をされる可能性もあります。その場合、自らが考えるより安い株価で株式を手放さなければならなくなる場合があるのです。
2)上場することで業績に対するプレッシャーが発生する
これは株式会社である以上、当たり前の話ではあります。その一方で未上場の企業の場合、ベンチャーキャピタルから出資を受けていない限り、株主は自分だけだったり、昔からよく知った親族・友人や、長く取引を続けている取引先であったりすることが一般的です。そうであれば、事業を再構築し業績を回復させるまで長く見守ってくれる株主は多いかと思いますが、上場企業となるとそうはいきません。決算の内容やリカバリー戦略に失望した株主は会社の株を売却することで、いつでもその会社に対する投資をやめることができます。
株式を手放したい人が多くなると、株式を買いたい人よりも売りたい人が多くなり、株式の需給が悪化することから株価が下落します。一時的な売りであれば株価はすぐに回復しますが、たとえば業績悪化が原因の場合、すぐに株価は回復しません。株価が低位で推移することで、資金調達したい場合であっても必要な金額が調達できないなど、副次的なデメリットが発生することもあります。
こういった事態を避けるために、上場企業の中には大胆なリストラクチャリング(不採算部門の事業縮小、撤退、統廃合などを行い、高収益事業へ経営資源を集中させること)を避ける会社もあります。また、リストラクチャリングを行う場合であっても、更なる失望を避けるために、大胆なピボット(路線変更や方向転換)に着手できないなど、打ち手が小粒になるケースも散見されます。このように、経営スタイルによっては、業績に対するプレッシャーにより十分な事業変革の打ち手に着手できなくなることも、実際に見られるデメリットの一つです。
3)資金調達が有利になるメリットがない場合もある
一般的な上場企業の資金調達手法として、証券会社に引受を委託して行う株式の発行(いわゆる公募増資)が考えられますが、獲得できる手数料が十分でないことから、証券会社は小規模の増資に対して消極的です。たとえば10億円程度など、小規模な水準では公募増資を引き受けてくれる証券はほぼないのが実情です。
これらに対応するため、証券会社では多くの株式関連の資金調達手法を提供しています。その一方で、これらの手法に対する市場の理解も十分ではなく、また過去には株主の価値を棄損する形で実施された資金調達も世の中にあることから、実施することで希薄化率(発行済株式数の増加率)以上に株価が下落する資金調達手法が多いことも事実です。ただし、近年では、日本においても機関投資家が直接上場企業に投資するPIPEs(Private Investments in Public Equities)といわれる投資スタイルも一般的になってきました。こういった資金の出し手の活動が日本でもより認知されるようになると、中堅上場企業の資金調達の幅も広がるのではないかと思います。
【こちらもおすすめ】コーポレートガバナンスとは?中小企業で今から取り入れるべき事項を経営コンサルタントが解説
上場するかしないかも大切だが、事業成長はもっと大事
世の中では一般的に上場についてよいことが語られることが多いこともあり、今回はデメリットに力点を置いて紹介しました。今回ご紹介したデメリット以外にも、ガバナンスの維持・構築のためのコストや監査法人を起用し続けるコストも合計すると年間数千万円単位で発生することから、財務的にも上場はいいことだけではありません。
ただし、上場をすることによって実現できるメリットも当然あるので、「経営者ならば一度は上場」という考えを否定するわけではありません。上場を目指すにせよ、目指さないにせよ、持続的な事業成長のために考えられることはいくつかあります。まずはこれらのことに着手し、継続的に成長する見通しができてから上場について改めて考えるのはいかがでしょうか。下記にて具体的なアイデアをいくつか記載させていただきます。
①個人商店からの脱却
0→1のような新たな事業を担うのは経営陣でも、そうでなくてもよいですが、メインの事業は経営陣が仮にいなくとも自律改善のプロセスが回っている状況にしておきましょう。
②新規事業を生み出すための仕組みづくり
テクノロジーや社会環境の変化のスピードが速くなる中で、事業モデルのアップデートの頻繁も高くなっています。組織の中での経営陣・マネージャー陣の役割を規定し、責任者を決め新規事業開発は常に走らせておきましょう。
③事業伸長に必要な投資を明確にする
上場を含めた資金調達時には、持分の希薄化は必ず発生します。株主が納得のいく投資(≒希薄化を許容できるだけの投資利益率が見込めるか)と紐付いた資金調達であるかは、事前に十分検討するようにしましょう。
今回は一般的な上場のメリット・デメリットについての話でしたが、「具体的にこういった上場ではどうか?」など、お悩みの方は是非一度ご連絡ください!
*metamorworks, CORA, jessie, World Image / PIXTA(ピクスタ)
【こちらおすすめ】創業期、成長期、成熟期…中小企業の成長ステージ別!よくある課題と解決方法
【エクセル版チェックシートも】はじめてのオフィス移転お役立ちマニュアル