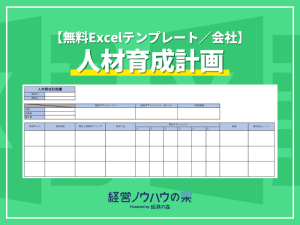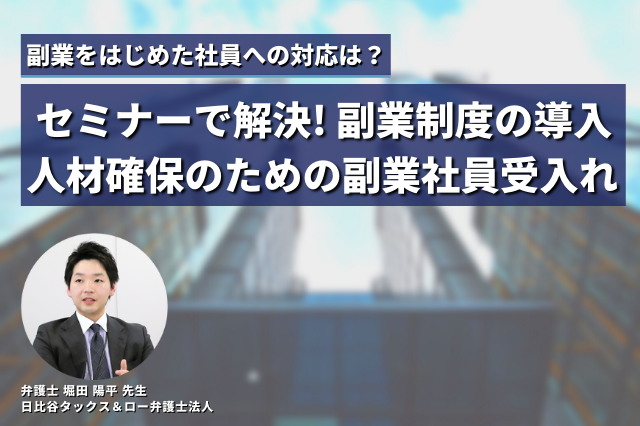【テンプレート付】会社の成長に必要な「人材育成計画」とは?作り方や活用法を解説
人材育成計画は、企業の成長に欠かせないものです。人材は企業の最も重要な資産であり、育成することで企業は更なる成長を達成できるからです。しかし、人材育成計画を作る際には、さまざまな要素を考慮する必要があります。本記事では、企業の成長に必要な人材育成計画の作り方について解説し、策定に役立つテンプレートを紹介します。
目次
人材育成計画とは
人材育成計画とは、企業が自社の従業員に対して、スキルアップやキャリアアップを図るために設定した計画のことです。これは既存の従業員のみが対象とは限らず、将来雇用する従業員のための計画も含まれます。人員育成計画は短期的な人材不足の解消のためではなく、中長期的な計画でなければなりません。どのような人材が必要かを経営戦略から導き出し、それに基づいて計画を立てます。経営の面から見て必要とされる人材像が、しっかりと計画に反映されていることが必要です。また、この計画は今後の指針にもなるため、現実の進捗状況に応じて適時見直していく必要があります。
【こちらもおすすめ】「人財」確保は会社の鍵!マニュアル化できない採用に関する相談まとめ
人材育成計画の必要性
人材育成計画が必要な理由は、経営戦略上必要な人材像に育成するための具体的な項目を可視化するためです。育成のために何をしたらいいのか明確化していないと、必要な人材像に育てられません。よって、具体的な項目を可視化することで、体系的な育成プロセスを実現するのです。
もし、人材育成計画が無く、経営者や社員たちの勘で人材育成を行っていたらどうなるでしょうか。たとえば以下のような弊害に繋がるでしょう。
- 教育に熱心な部署と熱心でない部署で育成の成果に差が出る
- 新人がキャリアに不安を覚え、離職の原因となる
- 経営上必要な人材が育たず、ミスマッチが発生する
経営理念を浸透させる
人材育成計画の策定と運用は、経営理念を社内に浸透させるためでもあります。人材育成計画は経営戦略をもとに策定されるため、必然的にそれは経営理念を踏まえたものになります。昨今は価値観が多様化し、働く意味や労働観も個々人で異なる時代となりました。それは望ましい変化ではありますが、昔のように自然な意識の統一がしにくいということでもあります。転職という考え方も当たり前になり、中途入社の社員が多い企業ではその傾向は加速する一方でしょう。そのような時代において、人材育成計画を通じて経営理念を浸透させることは、従業員が意識や理念を統一してひとつの目標に進みやすくなる効果があるのです。
【こちらもおすすめ】人が全然定着しない…経営理念が浸透していない会社の共通点3つと改善策
「リスキリング」を推進
現代は変化の激しい時代です。Web3やAIなどの新技術の急速な発達、コロナ禍やインフレによる経済不安を10年前に予想できた人がどれだけいるでしょうか? 10年後の未来が全く予測できない時代になっているのです。今後の変化した市場環境に対応するため、現在注目されている概念が”リスキリング”です。市場環境やビジネスモデルの変化についていくために、既存の人材にも新しいスキルを学ぶことが求められています。新入社員の育成だけではなく、既存社員のリスキリングを後押しすることも人材育成計画策定の目的なのです。
人材育成計画のたて方のステップ
人材育成計画は以下のようなステップで策定します。
1. 求める人材像の決定
まずは求める人材像を決定しましょう。経営理念から経営戦略を立て、経営戦略に基づいて人材像を決定する必要があります。たとえば、社内で新しくデジタル部を立ち上げることとなった場合、“プログラミングスキルを持っている”といった人物像が必要となるでしょう。
2. 現在の人材を分析し、目標を設定する
現在、自社にどのような人材がいるのかを分析し、求める人材像とのギャップを可視化します。このギャップが人材育成計画で習得すべきスキルとなります。育成カリキュラムは通常の業務と並行して行う必要があります。しかし、業務と並行して複数のスキルを同時に身につけるのは難しいでしょう。よって、もし必要なスキルが複数ある場合は、優先順位を付け、業務の妨げにならないように配慮する必要があります。
3. カリキュラムを設計する
習得すべきスキルや目標が定まったら、それを習得させるためのカリキュラムを決めましょう。カリキュラムは複数の方法があり、組み合わせてカリキュラムを設計することで効果が上がります。習得の方法には以下のような種類があります。
- OJT:実際の現場で業務を体験しながら学ぶ
- 集合研修(Off-JT):研修会場に集まりセミナー形式やチーム作業で学ぶ
- e-ラーニング:個人で動画教材や教育用ITシステムなどで学ぶ
- 自己啓発:従業員が自主的に会社外のカリキュラムで学習する
4. 実施・運用する
カリキュラムが決まったら、実施・運用しましょう。実施の際には、従業員に任せきりにするのではなく、細かくバックアップすることが重要です。学習が滞っている従業員をいち早く把握し、滞っている原因を解消しましょう。運用しながら現実に合わせて計画を適時見直していくことも大事です。
人材育成計画をうまく導入するためには
1on1ミーティングを合わせて導入する
人材育成計画の実施の際は、会社がこまめにフォローとバックアップをすることが大事です。従業員に任せきりだと学習のモチベーションが低下しやすく、計画の達成が難しくなるからです。そのため1on1ミーティングのような短いサイクルの面談を合わせて実施しましょう。1on1ミーティングとは、管理職と従業員が1対1で行うミーティングです。従業員の学習上の課題や悩みを管理職がよく傾聴し、自発的なスキルアップを促すことが目的です。
【こちらもおすすめ】どうしたら社員の本音を掴める?経営者が知るべき「社員とのコミュニケーション術」3つ
等級制度と連携させる
人材育成計画は等級制度と連携することで効果が上がりやすいです。等級制度とは、従業員のスキルの習得度合いに応じてランク付けし、従業員が現在どのようなスキルを持っているのか可視化するものです。従業員自身も現在いるステージが自覚でき、今後の個人的な目標が明確化されるので、モチベーションの向上に効果があります。
【もっと詳しく】等級制度の作り方をわかりやすく解説!真似すれば作れる図表解説付き
まとめ:人材育成計画のエクセルテンプレート
人材育成計画を策定したらドキュメントの形で保存し、いつでも閲覧できるようにしましょう。人材育成計画は1回作って終わりではなく、日々人材育成の指針とし、適切に見直しながら運用するものだからです。そこで、エクセルを使った人材育成計画のテンプレートを用意しました。ぜひダウンロードして人材育成計画の策定に役立てていただければ幸いです。
*YUJI, タカス, Xeno, ocsa, kikuo / PIXTA(ピクスタ)
【オフィスの課題を見える化】働く環境診断「はたナビPro」お問い合わせはこちら