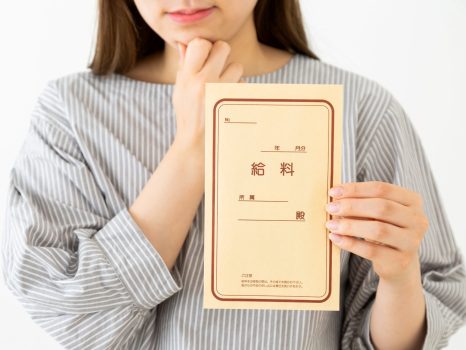経営者が知るべき退職代行と非弁行為|法律違反の判断基準&対処法を弁護士が解説
近年、「退職代行サービス」(以下、退職代行)と呼ばれるサービスを利用して会社を退職する社員が増えています。筆者が関与している会社でも、社員が退職代行を利用して退職届を出してきたというケースを年に数件は見かけます。
会社としては、自ら退職の意思を伝えてこない違和感や、トラブルへ発展する不安を抱えることもあるでしょう。そこで、今回は、経営者に向けて退職代行を利用した退職の対処方法を解説します。
目次
退職代行とは
退職代行とは、一般に、社員に代わって会社に対して退職の意思を伝えるサービスを指します。退職代行には、大きく3つのパターンがあります。
- 法律事務所による退職代行
- 労働組合による退職代行
- 民間企業による退職代行
法律事務所による退職代行
弁護士が運営する退職代行は、弁護士は弁護士法に基づいて代理人として依頼者に代わり退職の意思表示はもちろん、残業代・退職金の請求、有休消化、損害賠償交渉といった法律事務全般に対応することができます。
訴訟やトラブルが発生した場合でも、そのまま法的手続きに移行できる点も大きな利点です。経営者としては、弁護士名義での通知が届いた場合には、通知内容の確認とともに、法的交渉として正式に対応する姿勢が求められます。労働組合型や民間型とは異なり、代理人としての法的権限が明確にあるため、適切に社内の法務・顧問弁護士と連携することが望まれるでしょう。
労働組合による退職代行
労働組合が提供する退職代行は、「団体交渉権」に基づいて運営されています。労働組合法第7条により、組合は使用者との団体交渉を行う法的権限を持ち、従業員に代わって退職や労働条件に関する交渉を行うことが認められています。残業代請求や退職日の調整、有給取得に関するやりとりも合法的に行える点が特徴です。
ただし、交渉の正当性や権限の範囲には注意が必要で、形式上組合を名乗っていても実態が伴っていないケースでは非弁行為とみなされるリスクも。会社側は、通知元の労働組合が実在し、かつ労働者が構成員であるかどうかを確認した上で、団体交渉として対応する必要があります。
【参考】労働組合法/厚生労働省
民間企業による退職代行
一般の企業が提供する退職代行は、法的には「使者」として従業員の退職意思を伝えるにとどまる範囲であれば適法です。つまり、退職の意思を代わりに会社へ通知するだけであれば問題ありません。しかし、それを超えて退職条件の交渉や金銭請求といった法的調整に関与した場合、後述する非弁行為に該当するおそれがあります。
経営者側としては、通知内容に「代理」「交渉」などの文言が含まれていないか、あるいは金銭請求がされていないかを慎重に確認することが重要です。また、対応すべき相手が代理権を有しない場合は、交渉に応じず、本人との直接連絡や文書確認を優先すべきです。
退職代行は非弁行為にあたるのか
退職代行は、従業員の退職意思を会社に伝えることを代行する業務ですが、内容によっては「非弁行為」に該当するおそれがあります。
非弁行為とは、弁護士や団体交渉権を持つ労働組合ではない者が報酬を得て法律事務を行うことを指し、弁護士法第72条により禁止されています。違反した場合、同法第77条により2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。たとえば、退職金や未払い残業代の請求、有給休暇の取得交渉、損害賠償の要求など、法律関係の調整を含む行為は「法律事務」とされ、弁護士以外が行えば非弁行為となります。
経営者は通知内容や発信元をよく確認し、交渉行為が含まれる場合には適切な法的対応を行いましょう。
退職代行の利用に関わらず退職は拒否できない
そもそも退職代行の利用に関係なく、退職の申し入れがあった場合は拒否することができません。
前提として、社員には退職の自由が保障されており、理由を問わず退職することができるのが原則です(民法 第627条。ただし、後述するように、有期雇用の場合は、労働者からの退職にも制限があります)。従って、退職の意思表示がされてから、予告期間の2週間が経過した時点で、退職の効果が発生することになります。
退職代行は、社員の退職の意思を「代理人」又は「使者」として伝える役割を担っているため、退職代行を利用した退職の意思表示は、いわば「本人」からの意思表示と同じ扱いになります。理由を問わず退職は可能である以上、「退職代行を利用した退職は拒否する。退職するなら本人が直接伝えなさい」という反論は通らないのです。
【参考】民法 第627条/厚生労働省
【こちらもおすすめ】退職者こそ大切に! 退職トラブルを防止する6つの事
退職代行に直面した経営者が考えるべきポイント
退職代行は、いわば社員の退職意思を代わりに伝えているだけなので、トラブルになることは考えにくいです。ただし、稀にトラブルまで発展することがあります。そのため、以下で紹介するポイントを踏まえて適切な対応を取る必要があるでしょう。
- 非弁行為に該当するか否か
- 退職代行利用者の雇用形態
- 就業規則に則った引継ぎの調整
1. 非弁行為に該当するか否か
退職代行から連絡がきた場合、まずは運営元について調べて非弁行為にあたるかどうかを判断しましょう。前述したとおり、法的権限を持つ弁護士事務所または労働組合ではない民間企業だった場合は、非弁行為の可能性があります。
実際には、かなり線引きが微妙なことが多いですが、仮に退職代行の業者が民間企業である場合には少なくとも交渉ごとはできません。そのような業者が単に退職の意思を伝えるだけでなく、未払いの残業代の請求や有給休暇の取得など、法的主張を付加してきているような場合には、非弁行為である旨を指摘のうえ、交渉しないようにしましょう。
2. 退職代行利用者の雇用形態
労働者には原則として退職の自由があり、理由を問わず途中で辞めることができるのが原則です。
ただし、退職の自由は無期雇用契約の場合のルールです。有期雇用契約の場合には、退職の自由が適用されず、有期雇用契約を途中で終了させるには、たとえ労働者側であったとしても、「やむを得ない事由」がなければ辞めることができません(民法 第628条。ただし、契約期間が1年を経過した後は、自由に退職可能となります(労基法附則137条))。「やむを得ない事由」は、解雇権濫用法理よりも厳格であると解されていますので、かなりハードルは高いといえます。
まずは退職代行を使って退職を告げてきた社員が、無期雇用社員なのか有期雇用社員なのかを確認し、有期雇用社員である場合には、「やむを得ない事由がない」として退職を拒めます。
【参考】民法 第628条、労働基準法に関するQ&A(労働基準法第137条)/厚生労働省
3. 就業規則に則った引継ぎの調整
退職代行を利用する社員は、「もう会社には行きたくない」という人が多いといえます。
急に退職代行を利用して退職を告げられても、業務の引継ぎがなされていない場合があります。一般的には、就業規則の規定で引継ぎ義務が課されていることが多いため、退職代行を利用してきた場合であっても、引継ぎを命じることが可能です。
【こちらもおすすめ】去り際こそ起きやすいトラブル!退職に関連する相談まとめ
退職代行を利用した労働者への対応
退職代行を利用して退職の意思が示された場合、有期雇用であって契約期間が1年未満の場合でない限り、基本的には退職を受け入れざるを得ません。
退職代行を利用して退職の意思を通知された場合の企業の対応の流れとしては、以下の通りとなります。
- 退職代行の運営元を確認(民間企業かつ非弁行為にあたる場合は対応しない)
- 退職代行が正当な代理又は通知の権限を有しているか(本人の意思に基づくものか)を確認
- 当該社員の雇用形態および契約期間の確認
- 退職日、有給取得希望の有無の確認
- 引継ぎが必要な場合の出社可否の確認
- 退職手続
退職代行から考える経営者が気をつけるポイント
労働者には退職の自由が原則としてあります。しかも、労働契約法や民法では、書面で通知することも必須とされていません。理論的には労働者が電話や手紙で希望退職日を伝えたうえで予告期間が経過すれば退職の効果が発生します。
極めて容易に退職することができる労働者が、わざわざ退職代行を利用してくるというのは、よほど会社や上司へ言い出しにくい雰囲気があるか、後ろめたいことがある場合といえます。
退職代行の利用によって起こるトラブルもあるため、できるだけ自ら退職の意思を告げてもらえるよう、日ごろからの雰囲気、関係性づくりに努めることが重要といえるでしょう。今一度、自社を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。
【こちらもおすすめ】離職率が高い企業の特徴とは?計算方法と離職率を下げる対策をまとめて解説
*78create, yu_photo, metamorworks, nonpii / PIXTA(ピクスタ)