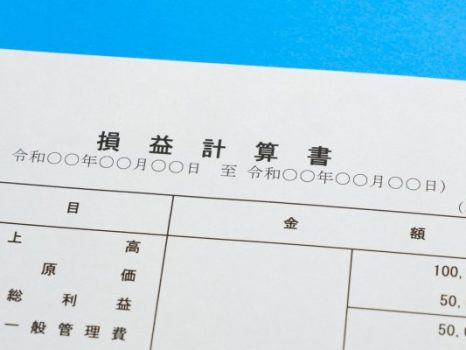経営者が知っておくべき決算書の読み方とは?財務三表の作成方法や分析方法を解説【第3回】
前回までの2回のコラムで、決算書の読み取り方のコツを掴んでいただけましたか? 決算書の読み方については今回が最終回です。前回までは損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書の読み方・考え方・その具体的な手順などを説明してきました。
第3回はキャッシュフロー計算書の読み取り方についての説明をした後に、企業の現状を把握する上で、非常に重要な時価評価への洗い替えという視点で分析手法を説明します。そして肝心の「決算書を作成してどう実際の経営に活かすのか」についても最後に述べます。より実践的な内容です。最後までお読みいただければ幸いです。
第1回:財務三表が示すモノを理解し、掴むべきポイントを把握、損益計算書を理解する
第2回:貸借対照表とキャッシュフロー計算書を理解し、財務分析の勘所を理解する
第3回:財務三表をどう作りどう分析して経営に活用するのか←今回はここ
それでは第3回の本編に入ります。
目次
キャッシュフロー計算書の読み取り方
少しおさらいですが、キャッシュフロー計算書は「期初から期末までの資金の動き」を表しています。つまり「1年間の資金の流れ」で、3つの収支を把握することができます。
(1)営業キャッシュフロー(本業による現金の収支)
(2)投資キャッシュフロー(固定資産や有価証券の取得、売却などの投資活動による現金の収支)
(3)財務キャッシュフロー(借入や社債の発行など資金調達による現金の収支)
ここでのフリーキャッシュフローは営業CFから投資CFを引いたものであり、その企業が自由に使える現金と言い換えることができます。長期借入金の返済原資となるフリーキャッシュフローの計算式は、経常利益+減価償却費-法人税などとなります。
細かい話にはなりますが、会計ルール上、利益は発生主義で計算されますが、キャッシュフロー計算書のフリーキャッシュフローは現時点で手元にある現金で計算されます。損益計算書から算出されるフリーキャッシュフローよりも、より実態に則した“使える余剰の資金”という意味合いになります。発生主義と実現(現金)主義の違いからくる差が存在するということです。
この微妙な違いは、理解しておくべき点と考えます。中小零細企業においての資金管理は実現(現金)主義のキャッシュフロー計算書の手法をベースとした、現金の推移がより鮮明に分かる、資金繰り表による管理が王道であると筆者は考えています。
経営者がキャッシュフロー計算書から読み解くべき情報
投資CFは、中小零細企業経営において頻繁に動きがあるものではないといえます。注目すべきは、本業たる営業CFと財務CFの状況です。覚えるべき4つのパターンで、営業CFと財務CFの状況ごとに経営者として対処すべき動きを説明します。
(1)営業CFがプラス・財務CFがプラスのケース
本業の資金繰りがプラスですが、財務CFもプラスなので、借入が発生している状態といえます。前回の借入時期と今回の借入時期についてどれくらい期間があいているのかを注意します。その期間が短い場合や、年間2回以上の運転資金借入がある場合などは、財務的に注意すべき状況といえます。
(2)営業CFがプラス・財務CFがマイナスのケース
本業がプラスで借入を返済している状態であり、この状態こそ「普通」といえます。営業CFが返済額より少ない場合は、資金不足に陥る可能性があるので注意せねばなりません。
(3)営業CFがマイナス・財務CFがプラスのケース
本業の資金繰りがマイナスなので、業務改善が必要な状態といえます。本業での資金不足を金融機関借入で賄っている状態で、資金は回っている状態にあります。この場合も前回の借入と今回の借入期間に注意すべきです。数年間分の借入実行時期を見直して、その間隔が短くなってきている状況ならば、財務状況は悪化傾向と判断できます。
(4)営業CFがマイナス・財務CFがマイナスのケース
本業の資金繰りがマイナスであり、財務CFもマイナスということは、早急に本業の改善を図らねばなりません。もし、改善が間に合わなければ追加融資、それもダメな場合は返済のリスケジュールを金融機関に打診しなければならない危機的状態といえます。
【こちらもおすすめ】利益はあるのに現金がない?「今すぐできる財務管理」でキャッシュフローを計算しよう【税理士が解説】
財務実態把握の勘所
貸借対照表の読み方はちょっとコツが必要です。なぜならば、記載されている情報に帳簿価額(簿価/取得時の価格・価値)と時価の勘定科目が混在しているからです。つまり、その企業の本当の純資産額は簿価の値を時価に洗い替えしないと分からないということです。
実は、企業の実態をシビアに判断しなければならない銀行などの金融機関は、決算期ごとにこの洗い替え作業を実施して、企業の財務的な実態を掴むような作業を行っています。このノウハウは企業の経営をしていく上で、非常に参考になるので、基礎的な2つの考え方をご紹介いたします。
(1)存続価値(継続B/S)
事業を永続させていく方針の企業が大事にすべき視点です。
事業の継続に必要な不動産、設備、機械などは簿価のまま計算します。事業継続に関係のない資産で、時価評価に直せるものは再計算をします。つまり、事業を継続できる状態で不要なものを現金化したと仮定しての純資産額が算定されます。
(2)清算価値(清算B/S)
事業から撤退、売却など引き際を検討している企業が重視すべき視点です。
事業からの撤退を前提としているので、すべて清算すれば果たしていくら現金が残るのかという観点で計算します。不動産の処分価格は取引事例や路線価から算出されますが、解体費用まで見込んで手残りの価値が計算されます。生産設備などは簿価の60%で評価されたり、在庫の処分価格は業種ごとに差があったりと、金融機関ごとで評価方法に微妙な差があります。
自社の業界や営んでいる地域性、清算時の勘定科目ごとの真っ当な評価などは、その業界に長けた経営者や経営幹部にしか分からないことかもしれません。根幹の経営判断の大きな材料になり得るので、決算が出るたびに手計算で構わないので、自社の本当の純資産額を計算しましょう。
【こちらもおすすめ】倒産の兆候を見逃さない!今さら聞けない「財務分析」のやり方【経営の基礎】
経営者として理解すべき決算書の作成プロセス
実は、簿記の基礎知識が自社の財務状態を読み解く上で必要不可欠であるという事実をお伝えしたいです。簿記会計の基礎知識がある経営者の方はおられるでしょうか? 経営者として、仕訳のプロにまでなる必要はないものの、決算書の作成プロセスを自身で理解し、その体制を主体的に構築して改良を加えていく姿勢は大切です。
仕訳作業⇒総勘定元帳⇒試算表作成(決算期に財務三表として作成)といった一連の作業手順を理解し、いかに自社の経営状態を正確に迅速に把握できるかという観点を持って、よりよいものになっていく工夫を行っていかねばなりません。
経理とは“経営管理”の略語です。仕事を取ってくるトップ営業だけが経営者の仕事ではありません。足元の財務状況、厳密にいえば、現金の状況を理解しないまま、仕事の受注のみにまい進すれば、最悪の場合”黒字倒産”という憂き目に遭ってしまいます。
経理体制の構築は、正確且つ迅速に翌月の15日までに試算表が完成することと表現できます。経営者の重要な業務として、たゆまぬ努力をしてほしいと思います。
【こちらもおすすめ】一覧表でチェック!毎日・毎月・毎年「基本的な経理業務」の内容をおさらい
まとめ・財務分析で得た情報をどう経営に活かすのか?
「計算式と評価される水準は分かった。しかし、その数値を知ったところでどうなるものでもないのでは?」という疑問が出てくる経営者の方もいるでしょう。数値を知り、そこから改善していくための施策への落とし込みが非常にイメージしづらく、難解に感じられる方も多いのではないでしょうか?
極端な意見かも知れませんが、まずは自社の財務状況が下記のようなレベル感を把握できるようになることが、財務分野にも素養のある経営者になる一歩目ではないでしょうか。
(1)健康そのもの
(2)少し風邪を引いた状態
(3)緊急手術を要する状態
細かくいえば、今回の3回シリーズで触れた金融機関の審査目線からの判断軸は、金融庁から求められる「財務格付・自己査定」という制度に基づいています。この「財務格付」制度を紐解いて行けば、さらに精緻な財務情報をピンポイントで得られ、より正確で的を射た経営施策を出す可能性が高まることでしょう。つまり、財務的情報が細かく正確であればあるほど、施策の成功率は高まります。
そして、自社の財務状況の情報を知れば知るほど、経営の羅針盤となる“経営計画”策定時に役立ちます。経営におけるすべての施策の根拠となり得る、クロスSWOT分析などのフレームワークを利用する場合、戦略と戦術を紡ぎ出す際に前提となる情報の精度が客観的で信頼度が高ければ高いほど、直感に頼る経営者と比べて施策の質で優位に立てることはいうまでもありません。
正しく財務状況を理解することで、その企業が未来に成長を描ける戦略と戦術を立案できると考えます。財務指標の把握から経営施策への落とし込み方は、文章で単純に表現できるほど容易なものではありません。
しかし、客観的な財務情報を得た場合、未来への仮説は立てやすくなるはずです。未来は当然ながら、神のみぞ知る世界です。しかし、仮説立案の判断材料として財務指標はきっと役立つはずです。数字に対して苦手意識や偏った先入観を持たず、正面から自社の数字と向き合って、その企業のあるべき明るい未来を描いてほしいと思います。
* metamorworks,Luce,タカス,mapo / PIXTA(ピクスタ)