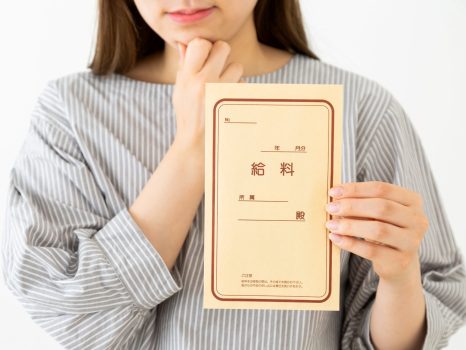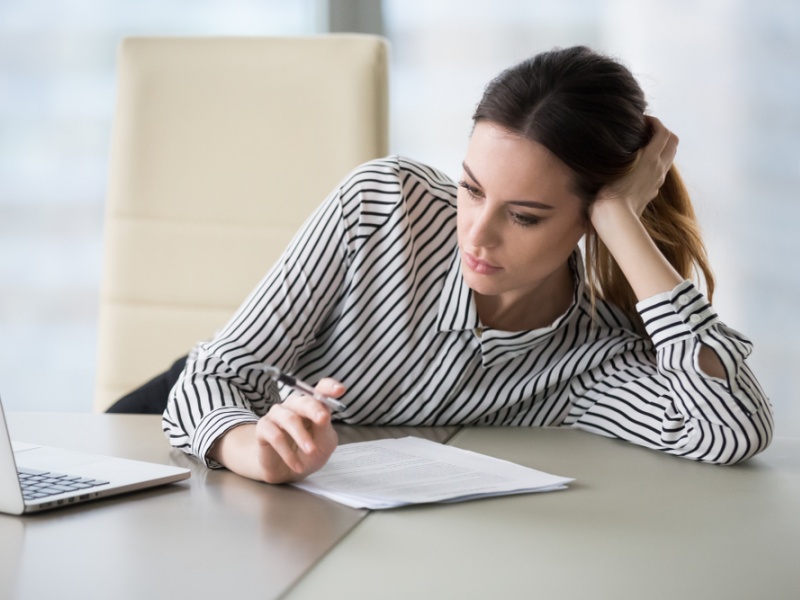
給料をもらうだけの「ぶら下がり社員」とは。定義と対策を解説
やる気がない、言われたことしかやらない、といった人のことを「ぶら下がり社員」と呼んだりします。経営者、管理職、人事の方からすると、頭の痛い存在であるぶら下がり社員。同様に、自分では努力をせずに、他のメンバーの成果を自分の成果とする「フリーライダー」も問題視されがちです。本記事では、ぶら下がり社員の定義をあらためて考え、そこから導き出される対処法について紹介します。
「ぶら下がり社員」の定義
そもそも、「ぶら下がり社員」とは一体どういう人のことを指すのでしょうか。似た言葉に「給料泥棒」という表現があるのですが、ここから「もらってる給料に見合わない人」のことを表していることがわかります。
冒頭でぶら下がり社員の例として、「やる気がない」「言われたことしかやらない」といった特徴を出しました。では、こういうぶら下がり社員とは、もらってる給料に比して何が足りないのでしょうか。ここでは、給料に比して足りないものとして、「本人の行動」に着目します。
ここで、「足りないのは『成果』では?」と感じる方もいるでしょう。たしかに成果も足りないのですが、成果とは行動の積み重ねの先にある、と筆者は考えます。一足飛びに成果に着目するのではなく、「適切な行動が足りないために十分な成果が出ない」というふうに、一歩手前の行動に焦点をあてることが大切です。
「外に表れている行動」に着目する
冒頭で挙げた「言われたことしかやらない」は、典型的な例といえるでしょう。他には、「いつもスマホをいじっている」「なにかと言い訳をする」などもよくあるケースです。
ここで注意してほしいのは、「足りない」と捉える対象は、あくまで「外に表れている行動」だということ。目に見えない「意欲」に着目してしまうと、上からの「足りていないよ」という指摘が、どこまでいっても水掛け論になってしまうでしょう。「やる気がない」というのは、意欲をやり玉に挙げているという点で、ぶら下がり社員への対処法を考えるうえでのNGパターンなのです。
【こちらもおすすめ】かくれモンスター社員放置の末路は組織崩壊…!?未然に防ぐ対応策とは
ぶら下がり社員には「青臭さ」と「血生臭さ」で向きあう
ぶら下がり社員に向き合うときは、「青臭さ」と「血生臭さ」という両面作戦が重要です。
青臭さというのは、「人は変われる」という人間観に立って、その人に向き合うこと。人は変われるのだから、変わるための手助けを惜しみなく与えます。一方、血生臭さとはその逆で、「人は変われない」という人間観に立つことです。人は変われないので、今の職場に無理やり合わせることはできない。ここではない別の場所、つまり「変わらない今のままのその人」が活躍できる別の職場へといざないます。
青臭さと血生臭さの説明を聞いて、「結局人は変われるのか、変われないのか」という疑問が出てくるのではないでしょうか。結論としては、どちらか一方に決めきることはできませんし、その必要もありません。大事なのは、一見相反する2つの人間観を、両睨みしながら本人に向き合うことです。
まずは青臭さでもって接し、結果として本人が変わればそれでよいでしょう。ただし、あらかじめ決めた時期を過ぎても変わらないのであれば、血生臭さにシフトします。会社にとっても、本人の今後のキャリアにとっても、時間は有限だからです。
まず青臭さで、それがどうしてもダメなら血生臭さへ、というのが両面作戦の正体です。
【こちらもおすすめ】問題社員はどう対処すればいい?トラブル回避法と過去の事例を一挙紹介
事実を提示する「青臭さ」
ではまず、ぶら下がり社員に青臭さでもって向き合うとはどういうことでしょう。ここでいう青臭さとは「人は変われる」という信念のこと。しかし、だからといって直接的にその人を変えようとしてはいけません。変えるのではなく、事実を提示するのです。青臭さの人間観においては、「本人は健全な判断力を持っているのだから、適切な情報を渡せばちゃんと判断できる(と信じている)」と考えましょう。
そうすると、ぶら下がり社員に対して青臭さで向き合うというのは、「ああしろ、こうしろ」と変えようとすることではなくなります。指示したり、改善を迫ったりするのではなくて、「あなたの行動はこのように見えてますよ」というふうに伝えましょう。これは、一般に「フィードバック」と呼ばれている手法です。
どうしても本人の意欲が気になるときは、「意欲」を「行動」に変換してフィードバックします。つまり、「やる気がない」というフィードバックではなく、「職場でスマホをいじっている行動は、『やる気がない』と映るよ」といった形で伝えるのです。
提示する事実は、耳の痛いことであっても「輪郭をはっきりさせて」伝える必要があります。よくあるNGパターンは、「こちら側だけイライラしている(けど本人には何も伝えない)」であったり、伝えるにしても具体的な言葉になっていないケースです。感じたことこそしっかり言葉にして、輪郭をはっきりさせて伝えましょう。
期限を決める「血生臭さ」
青臭さでもって向き合っても変化が見られないときには、血生臭さにシフトしましょう。配置転換や退職勧奨などを通じて、「変わらない今のままの本人」が活躍できる職場へといざなうことになります。ただし、これは言うは易く行うは難しの最たるもの。とにかく大事なのは、「具体的な指導を続けたにもかかわらず、本人に変化が見られなかった」という、事実と記録を積み上げることです。
ここに来て、「見て見ぬふりをせずにちゃんと指摘する」「目に見えない意欲ではなく、目に見える行動に着目する」という、青臭さの項で紹介してきた考え方が効いてきます。目に見える行動について指摘をするという、「記録に残る」対処であることが大切なのです。
対応をシフトするタイミング
青臭さから血生臭さへシフトするタイミングには、外的な基準を設けます。いつ本人に変化が表れるのかというのは、究極的には見通せません。
外的な基準とは、たとえば評価期間や人事異動のタイミングです。また、新規入社者であれば試用期間も大切な区切りとなります。本人と向き合うときには、「会社としてはこの時点までは青臭さでもって向き合うよ。でも、それまでに変化が見られなければ、血生臭さにシフトするよ」という会社としてのスタンスを、事前に提示しておくことも大切です。
まとめ
やる気がない、言われたことしかやらないなどの「ぶら下がり社員」への対処法を紹介しました。
「ぶら下がり」という語感から、ついついやる気やモチベーションといった目に見えないものに意識が向きがちです。しかし大事なことは、とにかく徹底的に、事実としての「本人の行動」にフォーカスすること。そのうえで、青臭さ(人材育成)と血生臭さ(評価/処遇)という相矛盾する向き合い方を、時期を決めて切り替えることが大切です。
*fizkes / shutterstock