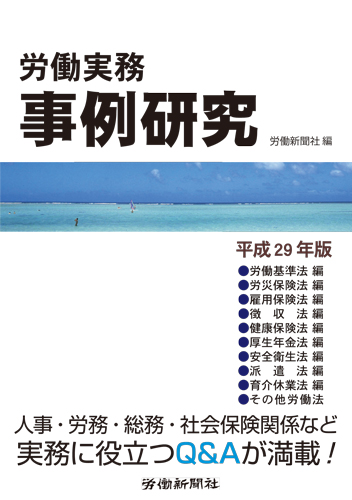- HOME
- コラムの泉
コラムの泉
専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら)
賞与総額は利益配分・成果配分から決めよ
-
カテゴリその他 > 経営最終更新日2014年08月21日 11:39
-
著作者
-
ポイント1,003,907ポイント ポイントランキング100!
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
経営テクノ研究所
2014年8月18日第1・3週月曜日発行
発行人:舘 義之http://www9.plala.or.jp/keiei-techno/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
★★経営のパートナー★★経営学で企業を再生する
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<目次>
★賞与総額は利益配分・成果配分から決めよ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★賞与総額は利益配分・成果配分から決めよ
1.賞与総額の算出方法には3つある
従来の賞与は、賃金の後払い、賃金の補充、あるいは賃金水準の調整とい
った考え方が強かったのですが、これからは、一般社員に対する賞与に関し
ては、利益配分・成果配分という方式に移行せざる得なくなります。
そのためには、利益配分・成果配分の基礎となる配分率を決定しておかな
ければなりません。つまり、賞与総額を算出して従業員個人に対する配分方
式を制定しておきことが必要になってきます。
賞与の総額を算定するには、大別して、次のような方法があります。
(1)標準生計費を基準に算出する方法
従業員が、その賃金によって生活を維持している以上、生活のために必要
とされる生計費を無視して決定するわけにはいきません。
どの程度の生計費が妥当であるべきかは、そう簡単に決めることができま
せんが、人事院の統計・調査資料を用いるとよいでしよう。
●標準生計費:年1回/人事院
(2)世間相場を勘案して決定する方法
各企業は、他企業と競争関係にあります。したがって、同地域、同業種と
の賃金水準との均衝を考えませんと、必要な従業員を確保し、満足させてい
くことがむずかしくなります。
●厚生労働省:毎月勤労統計調査・毎月/賃金構造基本統計調査・年1回/
賃金構造基本統計調査(初任給)・年1回/民間主要企業一時金調査(夏季、
年末)・年1回
●東京都産業労働局:中小企業の賃金事情・年1回/中小企業賃金・退職金
事情・隔年/東京都における一時金調査(夏季、年末)・年1回・人事院:
職種別民間給与調査年1回
●国税庁:税務統計から見た民間給与の実態調査・年1回
(3)経営成果を基礎にして計算する方法
企業が存続していくためには、経営成果から見て、その支払能力を超えて
賃金を支払うことはできません。
●経営成果を中心とする賞与総額の決め方
経営成果による賞与総額の決め方には、利益配分方式と生産性配分方式と
があります。
[利益配分方式]
●粗利益に対する一定比率による額
この方法は、労働生産性を強調していても、他部門の経営成果に対する貢
献度が示されておらず、経営全体の活動成果の表現が薄弱なので、適当では
ありません。
●営業利益に対する一定比率による額
この方法は、他部門の経営成果に対する貢献度が示されており、算定の基
礎として妥当といえます。
●純利益に対する一定比率による額
この方法は、営業外損益を加減しているため、賞与は、ある一定期間内に
おける従業員の収益に対する貢献度に比例するという建前に反するので、算
定の基礎としては妥当ではありません。
●(営業利益-社内留保)に対する一定比率による額
この方法は、企業が利益分配を先取りすることになりますが、企業の存立
は永遠であり、かつ、社会的生命を維持することを使命とする限り、営業利
益から社内留保を控除することは当然の措置といえます。したがって、この
方法が最も妥当です。
[生産性配分方式]
●生産価値に対する一定比率
生産価値=売上高-原材料費など=諸経費+人件費+減価償却費+利益
●付加価値に対する一定比率
付加価値=売上高-(原材料費+減価償却費)=諸経費+人件費+利益
賞与の配分基礎を、利益配分方式の(営業利益-社内留保)にするか、生
産性配分方式による生産価値ないし付加価値にするかは、両者のいずれを採
用しても、本質的な矛盾はありません。
2.社内留保を決めるには
社内留保金の中心的なものは、(1)危険保証、(2)拡張の準備、(3)
借入金または社債の返済などです。
(1)危険保証
景気の変動、競争の激化、不測の損害などに対する引当です。この危険に
対する留保をどのくらいにするかは各企業によって異なることはいうまでも
ありません。
一般的にいって、各企業の種類、規模を平均すると、年に3%の危険率に
なっています。自社の危険率を出す場合は、総資本利益率の過去の平均値を
出し、その平均偏差を出すことによって算出します。
(2)拡張の準備
過去の売上の統計から、売上の増加は平均何%であるか、また、同業者の
増加率は何%かを検討して、増加率を決めます。
この増加率によって、次の算出を行います。
総資本
●必要資本額=(売上高×増加率)×──────
売上高
必要資本額
●拡張率=───────
総資本
この拡張率のうち、どれだけを内部留保するかによって留保率が異なります。
・売上高 1,000万円
・増加率 年5%
・総資本 800万円
800
(1,000万円×5%)×──────=40万円
1,000
40
─────×100=5%
800
過去の統計から内部資金・調達と外部資金・調達が半々とすると、拡張準
備率は、2.5%となります。
(3)借入または社債の返済
借入金や社債を内部留保によって返済することは、他人資本が自己資本に
おきかえられることを意味します。これは、他人資本と自己資本の構成割合
をかえることです。
現在、自己資本40%、他人資本60%を5年後に50%対50%に変え
るとすると、10%他人資本を返済しなければなりません。
10%÷5年=2%留保率
この場合、拡張準備率の外部資金・調達分と内部資金・調達分の割合は5
0%対50%にする必要があります。
以上、示した内部留保を算出するには、
・危険負担率 3%
・拡張準備率 2%
・借入・社債返済率 2%
・払込資本 5ヵ年平均推定 5,200万円
・総資本 同上 50,000万円
払込資本
●内部留保=──────+(危険負担率+拡張準備率+借入・社債返済率)
総資本
5,200
────────+(3%+2%+2%)=7,104%
50,000
したがって、内部留保金は、
50,000×0,710=3,552万円
となります。
3.付加価値を中心とする賞与総額の決め方
付加価値に対する一定比率の配分ということは、総額人件費を表示するこ
とを意味しています。
●総額人件費=付加価値×労働分配率
この配分から賞与をみると、総人件費のうち、通常の支払賃金として支払
われた残余の部分が賞与総額となります。
●賞与総額=総額人件費-支払済み賃金
人件費と賃金水準との関係は、労働分配率から検討することができます。
労働分配率が異常に高い場合は、人件費の過大か付加価値額の過小によるも
のです。
この労働分配率についてラッカーが1899~1929年の30年間にわ
たる、アメリカの工業統計を3年間を費やして調査した結果、平均労働分配
率は39.395%で標準偏差は1.663%ということが明らかになりま
した。そして、その後の調査でも、この関係は変わっていません。
したがって、賞与総額を多くするということは、付加価値の増大に努めれ
ばよいのです。そのためには、売上の増加、新製品の開発などが不可欠な要
件となります。
4.貢献度に即応した個人配分を行え
賞与の性格が利益配分・成果配分的な方向である限り、その期の利益算出
の貢献度に即応する配分方式に重点を置くべきです。
したがって、その基本算出式は、次のようになります。
●基本給×勤務考課率×賞与支給率×出勤率
(1)勤務考課係数
考課段階を4・3・2・1の5段階とする
(2)賞与支給率
売上高や営業利益、あるいは投資収益率(ROI)などの経営指標の向上
は、社員の努力結果といえます。
●支給月数例(製造業)
そこで、営業利益率による支給月数の一例を示しておきますので、参考に
してほしいと思います。
営業利益率 半期賞与支給月数
7%以上 2.0ヵ月
6%以上 1.7ヵ月
5%以上 1.5ヵ月
4%以上 1.0ヵ月
3%以上 0.7ヵ月
2%未満 0.5ヵ月
(3)出勤係数
実際勤務日数÷所定勤務日数
5.賃金は総額人件費管理に連動させる
(1)総額人件費算出には財務諸表が必要
賃金は、一般的に職務給・賞与・年俸制・退職金(廃止・前払いの検討)
などに分類されますが、このいずれも、総額人件費との関連から配分を考え
いく必要があります。
賃金の支払能力は企業経営の重要な要素であり、経営者として常に注目し
ていなければならない問題です。いかに全社員に納得できる各賃金体系を決
めたとしても、支払能力がなければ成り立たなくなるからです。
そのために、企業としては、総額人件費管理という観点から、賃金総額が
毎年上昇してゆくのを避けるために成果主義を導入しようともしています。
それでは、賃金の支払能力はなんによって求められるかというと、それは、
経営成績と財務状態を示す財務諸表の中から賃金の機能と性格に関するもの
を選択することになります。
その財務諸表のうち賃金に直接関連のあるものは損益計算書(製造原価報
告書を含む)と貸借対照表です。そして、中心的な役割を果たすのは損益計
算書です。
●比率分析法
●損益分岐点法
●付加価値分岐点法
(2)比率分析法
比率分析法は、損益計算書から2個の数値を取りだし、これを比較して百
分比率を求めることにより支払能力を測定しようとするものです。
求めた百分比率を自社の数期間の連続比率・平均比率あるいは同業同種の
他企業の数値と比較して、分析結果を求める方法です。
一般に人件費に関する比率は、次のようなものが挙げられますが、単一の
比率のみで決めず、比率の組合せ・相互比較・期間比較などを駆使すること
が重要です。
●労働生産性=生産額÷従業員
●資本生産性=付加価値額÷使用資本
●人件費率=賃金総額÷売上高
●労働分配率=賃金総額÷付加価値額
●利潤分配率=純利益÷付加価値額
(3)損益分岐点法
損益分岐点法は、売上高と諸経費が等しくなる点、すなわち、売上高がそ
れ以上なら利益となり、それ以下なら損失という利益と損失の分岐点を求め、
この分岐点と人件費との関係から支払能力を測定しようとするものです。
[事例]
・売上高 12,000万円
・固定費 4,000万円
・変動費 6,600万円
・人件費 4,000万円
・当期利益 1,400万円
(利益積立金200万円 配当金500万円 超過支出金700万円)
・法人税 50%
・損益分岐点 8,900万円
固定費4,000万円
●損益分岐点=────────────=8,900万円
1-変動比率0,45
●賃金支払能力最高限度
企業経営において収益状態(売上高・総費用・利益の関係)をみた場合に、
売上高と総費用が等しいとすれば、現在の経営規模を維持することが精一杯
で、企業にとっては薄氷を状態といえます。この時点における売上高を、損
益分岐点売上高と呼んでいます。
そこで、人件費をこの損益分岐点売上高で割ったものが人件費率となり、
企業の賃金の最高限度額となるわけです。
その算式は、次のとおりです。
人件費 4,000万円
・賃金支払能力最高限度=──────────=─────────
損益分岐点売上高 8.900万円
=0.45
人件費の最高限度額は売上高の45%を超えてはならないことを示し、こ
の限度を超過すればとうぜん損失が発生することになります。
●賃金支払能力可能限度
企業経営において収益の状態が、賃金支払能力最高限度よりも売上高の点
で余裕のある状態です。この限度を超えればただちに損失につながりません
が、健全な経営とはいえません。
つまり、売上高で総費用・支払利息・税金などの超過支出金や利益積立金
をまかなうことは可能ですが、配当や社内留保までは手がまわらないという
状態を示しています。これを一般に売上危険点といいます。
この売上危険点と人件費の比率を賃金支払能力可能限度といい、この限度
を超えると経営の安定を欠くことになります。
固定費+超過支出金+利益積立金
・売上危険点=──────────────────
変動費
1- ─────
売上高
4.000万円+700万円+200万円
=────────────────────
1-0.55
=10,900万円
人件費
・賃金支払能力可能限度=──────
売上危険点
4,000万円
=──────────=0.367
10,900万円
したがって、超過支出金や積立金を維持するためには、人件費を売上高の
36.7%にとどめないと経営は不安定になる、という限度を示しています。
●賃金支払能力適正限度
企業経営が拡大再生産を行えるもっとも正常な状態にあることを示してい
ます。つまり、配当をできるだけ安定した経営の賃金支払限度をさしていま
す。その安定した経営のための売上高を剰余金保留点といいます。
この保留点と人件費の比率を賃金支払能力適正限度といい、この限度を超
える人件費の増加がおこれば、正常な経営状態から後退することになります。
したがって、配当まで可能な現在の水準を維持するためには、これが限界
であることを明らかにしているものです。
固定費+超過支出金+利益積立金+配当金
・剰余金保留点売上高=─────────────────────
変動費
1- ─────
売上高
4,000万円+700万円+200万円+500万円
=──────────────────────────
1-0.55
=12,000万円
人件費
・賃金支払能力適正限度=────────────
剰余金保留点売上高
4,000万円
=──────────=0.333
12,000万円
安定した経営を推進するための賃金支払能力適正限度は、売上高に対して
33,3%であり、剰余金保留点における人件費率になってはじめて安定し
た適正な人件費ということになるのです。
(4)付加価値分岐点法
付加価値分岐点法は、付加価値収益と費用との関係から賃金支払能力を測
定しようとするものです。その算式は、次のとおりです。
固定費
・付加価値分岐点=────────
付加価値変動率
固定費+超過支出金+利益積立金
・危険点=─────────────────
付加価値変動比率
固定費+超過支出金+利益積立金+配当金+剰余金保留金
・剰余金保留金=──────────────────────────
付加価値変動比率
(5)短期的な方法
貸借対照表による方法は、2つの項目の比率を求めて賃金支払能力の測定
を行うものです。
企業は、賃金を支払うための現金の準備が必要であり、その準備が不可能
になったときは、賃金の不払いや遅払がおきます。この支払に要する現金の
準備が正常であるかどうかを知ることが、賃金支払能力の判断としては重要
なのです。
この方法は、損益計算書による方法とは違い、賃金支払能力の状態を観察
・判断するためにあり、短期的な測定方法として用いられるものです。
主に用いられる比率を、次に挙げておきます。
流動資金
●流動比率=──────
流動負債
当座資金
●当座比率=──────
流動負債
現金
●亜現金比率=──────
流動負債
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★舘 義之のポジション
人事・IE・VE・マーケティングコンサルタント
人事・IE・VE・マーケティングの三輪で企業体質の仕組みを構築して、
厳しい経営環境の中で勝ち残っていく会社にすることを第一に支援します。
舘 義之への問い合わせstudy@sky.plala.or.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
経営テクノ研究所
2014年8月18日第1・3週月曜日発行
発行人:舘 義之http://www9.plala.or.jp/keiei-techno/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
★★経営のパートナー★★経営学で企業を再生する
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<目次>
★賞与総額は利益配分・成果配分から決めよ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★賞与総額は利益配分・成果配分から決めよ
1.賞与総額の算出方法には3つある
従来の賞与は、賃金の後払い、賃金の補充、あるいは賃金水準の調整とい
った考え方が強かったのですが、これからは、一般社員に対する賞与に関し
ては、利益配分・成果配分という方式に移行せざる得なくなります。
そのためには、利益配分・成果配分の基礎となる配分率を決定しておかな
ければなりません。つまり、賞与総額を算出して従業員個人に対する配分方
式を制定しておきことが必要になってきます。
賞与の総額を算定するには、大別して、次のような方法があります。
(1)標準生計費を基準に算出する方法
従業員が、その賃金によって生活を維持している以上、生活のために必要
とされる生計費を無視して決定するわけにはいきません。
どの程度の生計費が妥当であるべきかは、そう簡単に決めることができま
せんが、人事院の統計・調査資料を用いるとよいでしよう。
●標準生計費:年1回/人事院
(2)世間相場を勘案して決定する方法
各企業は、他企業と競争関係にあります。したがって、同地域、同業種と
の賃金水準との均衝を考えませんと、必要な従業員を確保し、満足させてい
くことがむずかしくなります。
●厚生労働省:毎月勤労統計調査・毎月/賃金構造基本統計調査・年1回/
賃金構造基本統計調査(初任給)・年1回/民間主要企業一時金調査(夏季、
年末)・年1回
●東京都産業労働局:中小企業の賃金事情・年1回/中小企業賃金・退職金
事情・隔年/東京都における一時金調査(夏季、年末)・年1回・人事院:
職種別民間給与調査年1回
●国税庁:税務統計から見た民間給与の実態調査・年1回
(3)経営成果を基礎にして計算する方法
企業が存続していくためには、経営成果から見て、その支払能力を超えて
賃金を支払うことはできません。
●経営成果を中心とする賞与総額の決め方
経営成果による賞与総額の決め方には、利益配分方式と生産性配分方式と
があります。
[利益配分方式]
●粗利益に対する一定比率による額
この方法は、労働生産性を強調していても、他部門の経営成果に対する貢
献度が示されておらず、経営全体の活動成果の表現が薄弱なので、適当では
ありません。
●営業利益に対する一定比率による額
この方法は、他部門の経営成果に対する貢献度が示されており、算定の基
礎として妥当といえます。
●純利益に対する一定比率による額
この方法は、営業外損益を加減しているため、賞与は、ある一定期間内に
おける従業員の収益に対する貢献度に比例するという建前に反するので、算
定の基礎としては妥当ではありません。
●(営業利益-社内留保)に対する一定比率による額
この方法は、企業が利益分配を先取りすることになりますが、企業の存立
は永遠であり、かつ、社会的生命を維持することを使命とする限り、営業利
益から社内留保を控除することは当然の措置といえます。したがって、この
方法が最も妥当です。
[生産性配分方式]
●生産価値に対する一定比率
生産価値=売上高-原材料費など=諸経費+人件費+減価償却費+利益
●付加価値に対する一定比率
付加価値=売上高-(原材料費+減価償却費)=諸経費+人件費+利益
賞与の配分基礎を、利益配分方式の(営業利益-社内留保)にするか、生
産性配分方式による生産価値ないし付加価値にするかは、両者のいずれを採
用しても、本質的な矛盾はありません。
2.社内留保を決めるには
社内留保金の中心的なものは、(1)危険保証、(2)拡張の準備、(3)
借入金または社債の返済などです。
(1)危険保証
景気の変動、競争の激化、不測の損害などに対する引当です。この危険に
対する留保をどのくらいにするかは各企業によって異なることはいうまでも
ありません。
一般的にいって、各企業の種類、規模を平均すると、年に3%の危険率に
なっています。自社の危険率を出す場合は、総資本利益率の過去の平均値を
出し、その平均偏差を出すことによって算出します。
(2)拡張の準備
過去の売上の統計から、売上の増加は平均何%であるか、また、同業者の
増加率は何%かを検討して、増加率を決めます。
この増加率によって、次の算出を行います。
総資本
●必要資本額=(売上高×増加率)×──────
売上高
必要資本額
●拡張率=───────
総資本
この拡張率のうち、どれだけを内部留保するかによって留保率が異なります。
・売上高 1,000万円
・増加率 年5%
・総資本 800万円
800
(1,000万円×5%)×──────=40万円
1,000
40
─────×100=5%
800
過去の統計から内部資金・調達と外部資金・調達が半々とすると、拡張準
備率は、2.5%となります。
(3)借入または社債の返済
借入金や社債を内部留保によって返済することは、他人資本が自己資本に
おきかえられることを意味します。これは、他人資本と自己資本の構成割合
をかえることです。
現在、自己資本40%、他人資本60%を5年後に50%対50%に変え
るとすると、10%他人資本を返済しなければなりません。
10%÷5年=2%留保率
この場合、拡張準備率の外部資金・調達分と内部資金・調達分の割合は5
0%対50%にする必要があります。
以上、示した内部留保を算出するには、
・危険負担率 3%
・拡張準備率 2%
・借入・社債返済率 2%
・払込資本 5ヵ年平均推定 5,200万円
・総資本 同上 50,000万円
払込資本
●内部留保=──────+(危険負担率+拡張準備率+借入・社債返済率)
総資本
5,200
────────+(3%+2%+2%)=7,104%
50,000
したがって、内部留保金は、
50,000×0,710=3,552万円
となります。
3.付加価値を中心とする賞与総額の決め方
付加価値に対する一定比率の配分ということは、総額人件費を表示するこ
とを意味しています。
●総額人件費=付加価値×労働分配率
この配分から賞与をみると、総人件費のうち、通常の支払賃金として支払
われた残余の部分が賞与総額となります。
●賞与総額=総額人件費-支払済み賃金
人件費と賃金水準との関係は、労働分配率から検討することができます。
労働分配率が異常に高い場合は、人件費の過大か付加価値額の過小によるも
のです。
この労働分配率についてラッカーが1899~1929年の30年間にわ
たる、アメリカの工業統計を3年間を費やして調査した結果、平均労働分配
率は39.395%で標準偏差は1.663%ということが明らかになりま
した。そして、その後の調査でも、この関係は変わっていません。
したがって、賞与総額を多くするということは、付加価値の増大に努めれ
ばよいのです。そのためには、売上の増加、新製品の開発などが不可欠な要
件となります。
4.貢献度に即応した個人配分を行え
賞与の性格が利益配分・成果配分的な方向である限り、その期の利益算出
の貢献度に即応する配分方式に重点を置くべきです。
したがって、その基本算出式は、次のようになります。
●基本給×勤務考課率×賞与支給率×出勤率
(1)勤務考課係数
考課段階を4・3・2・1の5段階とする
(2)賞与支給率
売上高や営業利益、あるいは投資収益率(ROI)などの経営指標の向上
は、社員の努力結果といえます。
●支給月数例(製造業)
そこで、営業利益率による支給月数の一例を示しておきますので、参考に
してほしいと思います。
営業利益率 半期賞与支給月数
7%以上 2.0ヵ月
6%以上 1.7ヵ月
5%以上 1.5ヵ月
4%以上 1.0ヵ月
3%以上 0.7ヵ月
2%未満 0.5ヵ月
(3)出勤係数
実際勤務日数÷所定勤務日数
5.賃金は総額人件費管理に連動させる
(1)総額人件費算出には財務諸表が必要
賃金は、一般的に職務給・賞与・年俸制・退職金(廃止・前払いの検討)
などに分類されますが、このいずれも、総額人件費との関連から配分を考え
いく必要があります。
賃金の支払能力は企業経営の重要な要素であり、経営者として常に注目し
ていなければならない問題です。いかに全社員に納得できる各賃金体系を決
めたとしても、支払能力がなければ成り立たなくなるからです。
そのために、企業としては、総額人件費管理という観点から、賃金総額が
毎年上昇してゆくのを避けるために成果主義を導入しようともしています。
それでは、賃金の支払能力はなんによって求められるかというと、それは、
経営成績と財務状態を示す財務諸表の中から賃金の機能と性格に関するもの
を選択することになります。
その財務諸表のうち賃金に直接関連のあるものは損益計算書(製造原価報
告書を含む)と貸借対照表です。そして、中心的な役割を果たすのは損益計
算書です。
●比率分析法
●損益分岐点法
●付加価値分岐点法
(2)比率分析法
比率分析法は、損益計算書から2個の数値を取りだし、これを比較して百
分比率を求めることにより支払能力を測定しようとするものです。
求めた百分比率を自社の数期間の連続比率・平均比率あるいは同業同種の
他企業の数値と比較して、分析結果を求める方法です。
一般に人件費に関する比率は、次のようなものが挙げられますが、単一の
比率のみで決めず、比率の組合せ・相互比較・期間比較などを駆使すること
が重要です。
●労働生産性=生産額÷従業員
●資本生産性=付加価値額÷使用資本
●人件費率=賃金総額÷売上高
●労働分配率=賃金総額÷付加価値額
●利潤分配率=純利益÷付加価値額
(3)損益分岐点法
損益分岐点法は、売上高と諸経費が等しくなる点、すなわち、売上高がそ
れ以上なら利益となり、それ以下なら損失という利益と損失の分岐点を求め、
この分岐点と人件費との関係から支払能力を測定しようとするものです。
[事例]
・売上高 12,000万円
・固定費 4,000万円
・変動費 6,600万円
・人件費 4,000万円
・当期利益 1,400万円
(利益積立金200万円 配当金500万円 超過支出金700万円)
・法人税 50%
・損益分岐点 8,900万円
固定費4,000万円
●損益分岐点=────────────=8,900万円
1-変動比率0,45
●賃金支払能力最高限度
企業経営において収益状態(売上高・総費用・利益の関係)をみた場合に、
売上高と総費用が等しいとすれば、現在の経営規模を維持することが精一杯
で、企業にとっては薄氷を状態といえます。この時点における売上高を、損
益分岐点売上高と呼んでいます。
そこで、人件費をこの損益分岐点売上高で割ったものが人件費率となり、
企業の賃金の最高限度額となるわけです。
その算式は、次のとおりです。
人件費 4,000万円
・賃金支払能力最高限度=──────────=─────────
損益分岐点売上高 8.900万円
=0.45
人件費の最高限度額は売上高の45%を超えてはならないことを示し、こ
の限度を超過すればとうぜん損失が発生することになります。
●賃金支払能力可能限度
企業経営において収益の状態が、賃金支払能力最高限度よりも売上高の点
で余裕のある状態です。この限度を超えればただちに損失につながりません
が、健全な経営とはいえません。
つまり、売上高で総費用・支払利息・税金などの超過支出金や利益積立金
をまかなうことは可能ですが、配当や社内留保までは手がまわらないという
状態を示しています。これを一般に売上危険点といいます。
この売上危険点と人件費の比率を賃金支払能力可能限度といい、この限度
を超えると経営の安定を欠くことになります。
固定費+超過支出金+利益積立金
・売上危険点=──────────────────
変動費
1- ─────
売上高
4.000万円+700万円+200万円
=────────────────────
1-0.55
=10,900万円
人件費
・賃金支払能力可能限度=──────
売上危険点
4,000万円
=──────────=0.367
10,900万円
したがって、超過支出金や積立金を維持するためには、人件費を売上高の
36.7%にとどめないと経営は不安定になる、という限度を示しています。
●賃金支払能力適正限度
企業経営が拡大再生産を行えるもっとも正常な状態にあることを示してい
ます。つまり、配当をできるだけ安定した経営の賃金支払限度をさしていま
す。その安定した経営のための売上高を剰余金保留点といいます。
この保留点と人件費の比率を賃金支払能力適正限度といい、この限度を超
える人件費の増加がおこれば、正常な経営状態から後退することになります。
したがって、配当まで可能な現在の水準を維持するためには、これが限界
であることを明らかにしているものです。
固定費+超過支出金+利益積立金+配当金
・剰余金保留点売上高=─────────────────────
変動費
1- ─────
売上高
4,000万円+700万円+200万円+500万円
=──────────────────────────
1-0.55
=12,000万円
人件費
・賃金支払能力適正限度=────────────
剰余金保留点売上高
4,000万円
=──────────=0.333
12,000万円
安定した経営を推進するための賃金支払能力適正限度は、売上高に対して
33,3%であり、剰余金保留点における人件費率になってはじめて安定し
た適正な人件費ということになるのです。
(4)付加価値分岐点法
付加価値分岐点法は、付加価値収益と費用との関係から賃金支払能力を測
定しようとするものです。その算式は、次のとおりです。
固定費
・付加価値分岐点=────────
付加価値変動率
固定費+超過支出金+利益積立金
・危険点=─────────────────
付加価値変動比率
固定費+超過支出金+利益積立金+配当金+剰余金保留金
・剰余金保留金=──────────────────────────
付加価値変動比率
(5)短期的な方法
貸借対照表による方法は、2つの項目の比率を求めて賃金支払能力の測定
を行うものです。
企業は、賃金を支払うための現金の準備が必要であり、その準備が不可能
になったときは、賃金の不払いや遅払がおきます。この支払に要する現金の
準備が正常であるかどうかを知ることが、賃金支払能力の判断としては重要
なのです。
この方法は、損益計算書による方法とは違い、賃金支払能力の状態を観察
・判断するためにあり、短期的な測定方法として用いられるものです。
主に用いられる比率を、次に挙げておきます。
流動資金
●流動比率=──────
流動負債
当座資金
●当座比率=──────
流動負債
現金
●亜現金比率=──────
流動負債
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★舘 義之のポジション
人事・IE・VE・マーケティングコンサルタント
人事・IE・VE・マーケティングの三輪で企業体質の仕組みを構築して、
厳しい経営環境の中で勝ち残っていく会社にすることを第一に支援します。
舘 義之への問い合わせstudy@sky.plala.or.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
閲覧数(46,862)
絞り込み検索!
現在22,868コラム
カテゴリ
労務管理
税務経理
企業法務
その他
≪表示順≫
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
経営ノウハウの泉より最新記事
スポンサーリンク
労働実務事例集
調査レポート
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
注目のコラム
注目の相談スレッド
スポンサーリンク